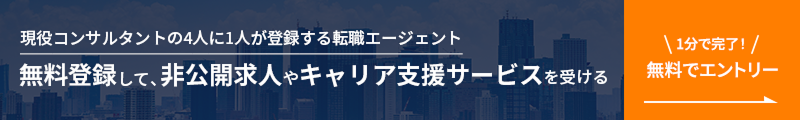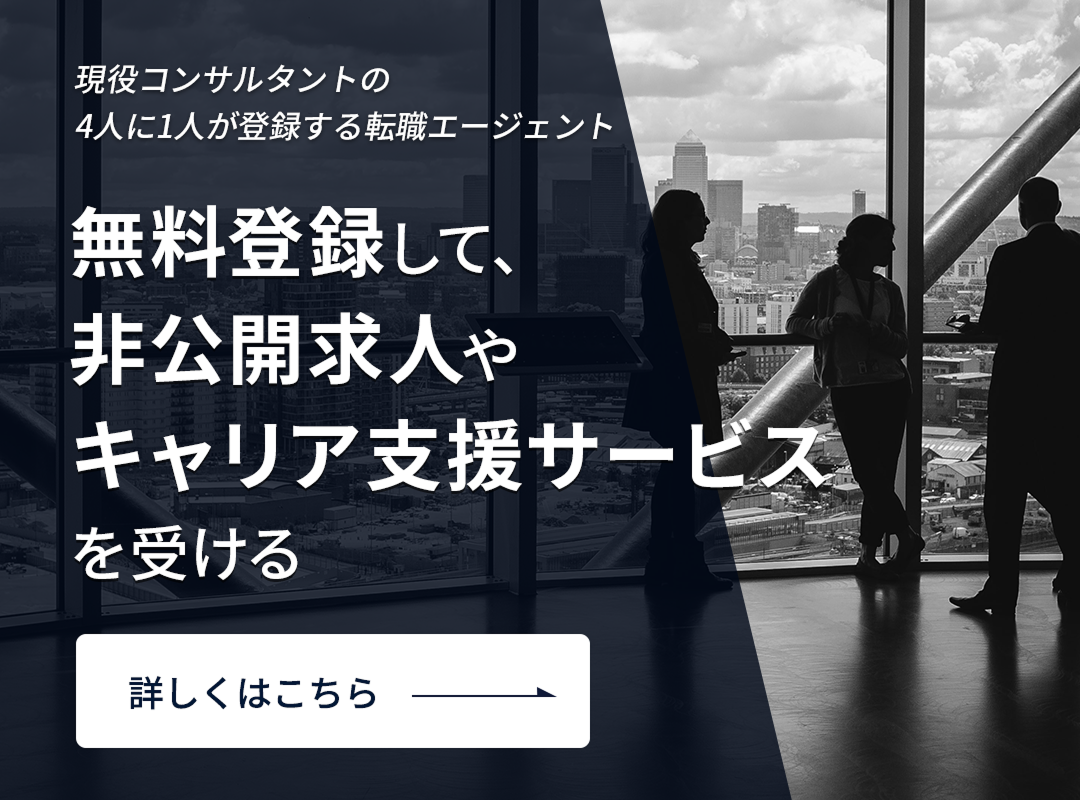【2025年版】年収1,800万円超のコンサルタントが知っておくべき節税対策まとめ

独立したコンサルタントや高収入の個人事業主は、収入が高いほど税金の負担が重くなり、お金を守る節税が欠かせません。本記事では、2025年の最新情報をもとに「コンサルタントの節税」のポイントと注意点をわかりやすく解説します。
<おすすめ記事>
ケース面接の代表的なパターンと例題・解答【売上推計と売上拡大策①<カフェ事業分析編>】
https://insight.axc.ne.jp/article/careernavi/2841/
Index
なぜ「コンサルタントの節税」対策が必要なのか
会社員から独立して個人事業主やコンサルタントとして働くと、収入が上がる一方で、税金の負担は大きく増えます。所得税・住民税・個人事業税を合計すると、合計負担税率が40%を超えることも珍しくありません。さらに、直近の税制改正により、インボイス制度の導入により独立初年度から消費税を納めることを考えるとさらに税金の負担率が上がります。
そのため、節税対策を怠れば売上が増えても手取りが少なく、資金繰りを圧迫するリスクも生じます。こうした背景から、コンサルタントが継続的に活動し、安定した可処分所得を確保するためには、早い段階から計画的な節税対策を行うことが不可欠です。
ちなみに、免税事業者であっても、的確請求書発行事業者に登録した場合は登録日以後、課税事業者として消費税の申告・納付が必要となります。初年度でも登録すれば納税義務が発生し得ますが、登録しない限りは基準期間売上1,000万円以下等の要件により免税となる場合もあります。
参照:国税庁 『インボイス制度の概要Q&A(免税事業者が登録する場合の取扱い)』
高収入コンサルタントの課税リスクが高まる背景
高収入のコンサルタントは累進課税の影響で年収が上がるほど手取りが減りやすくなります。さらに、正しく経費計上しなければ税務調査によりペナルティが課せられます。実際、令和5事務年度の『所得税及び消費税調査等の状況』でも、コンサルタント業が調査対象となる業種の中でも件数が多く、重点的に調査されやすい分野の一つとされています。
実際に調査を受けた人の大半は経費とそうでない費用の線引きが甘かったり、誤った節税情報を鵜呑みにして実行してしまったりしているケースがほとんどです。
たとえば、経費として認められるためには領収書が必要な事は当然ですが、業務との関連性を説明できる内容かどうかやその証拠が必要です。しかし、家族との私的な食事を接待交際費にしてしまったり、自宅用の家具を会社の備品としてしまったり、私的な観光旅行を出張費としてしまう、などといった間違った計上をするなどが典型的なNG例です。
また、『領収書があれば全て経費として計上できる』『法人化すれば必ず節税になる』といった極端な考え方のもとで考えてしまうと、本来は利用分に応じた案文計上が必要な車両費などを全額経費計上してしまうなどの間違いがあることもあります。こうした誤りは税務調査で否認され、追徴課税や信用低下のリスクを招きます。
コンサルタントとして”攻めの節税対策”は欠かせませんが、その一手を誤れば税務調査や顧客からの信頼低下につながり、信用リスクが一気に高まる危険もあります。
※参考:国税庁『令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況』
所得税・住民税・個人事業税の仕組みと実効税率の現実
高収入なコンサルタントは、売上規模が大きい分、課税所得も高くなりやすく、結果として所得税の最高税率(45%)に近づく可能性が高いと思われます。さらに、所得税に加えて一律10%の住民税、業種によっては3〜5%課される個人事業税が加算されます。これらを合算すると税率は40%を超えるケースも珍しくなく、年間の税負担は数百万円単位になることもあります。
※参考:東京都主税局『法人事業税・法人都民税』
※参考:東京都主税局『個人事業税』
さらに、前年の所得税額が15万円以上だった場合に、翌年の所得税をあらかじめ分割して前払いする予定納税をはじめ、住民税や個人事業税は前年の所得を基準に翌年度課税されるため、売上が減った年でも高額な税負担が発生し、資金繰りを圧迫します。
このため、高収入なコンサルタントほど、適切な節税戦略と資金管理の計画性が不可欠です。
<おすすめ記事>
ケース面接の代表的なパターンと例題・解答【売上推計と売上拡大策②<ビール会社のシェア戦略分析>】
https://insight.axc.ne.jp/article/careernavi/2843/
「コンサルタントの節税」におすすめの対策10選【実務対応ベース】
青色申告と65万円控除の活用
個人事業主であるコンサルタントが節税でまず押さえるべきは青色申告です。複式簿記での帳簿付けと電子申告により最大65万円の控除が受けられます(紙申告だと55万円に減額)。
電子帳簿保存法への対応も必須で、帳簿の形式や保存方法は税制改正により厳格化されています。また、青色申告を受けるためには以下の期限内に所轄税務署に届け出が必要になる点も忘れないようにしてください。
新規開業の場合:開業日から2カ月以内、またはその年の3月15日のどちらか早い日まで
すでに事業をしている場合:青色申告を適用したい年の3月15日まで
小規模企業共済やiDeCoで将来の備えと節税を両立
掛金全額が所得控除となる小規模企業共済やiDeCoは、将来の備えと節税を同時に実現できます。共済金は退職金扱いで受け取れるため、通常の給与よりも大幅に税負担が軽くなります。
具体的には、退職所得控除により勤務年数に応じた非課税枠が設定され、さらに課税対象額も1/2に軽減されます。その結果、同じ金額を給与で受け取るよりも、手取りが大きく残るため、節税効果が非常に高いのです。
生命保険料控除や扶養控除など所得控除を最大限活用
教育費が増える世代のコンサルタントに有効なのは、生命保険料控除や扶養控除などの所得控除です。直近の税制改正により、扶養控除や勤労学生控除の見直しがかかり、扶養控除の対象範囲が拡大されました。
扶養控除:48万円→58万円
勤労学生控除:75万円→85万
扶養する親にとっては、税負担の軽減が期待できる内容となっており、早めの確認と対応が重要です。扶養家族の条件を見直すことで、年間数十万円単位の課税所得減が可能です。
30万円未満の資産は一括経費(PC・ソフト・通信設備など)
中小企業者等(個人は青色申告者)に限り、 PCやソフトウェア、通信機器など取得価額30万円未満の資産は即時費用化が認められます(年間合計300万円まで)。また、10万円超20万円未満の資産については“一括償却資産”として3年間で均等償却する方法もあります。減価償却せずに全額をその年の経費として計上できます(年間300万円まで)。年末に購入すれば即効性の高い節税効果を発揮できます。2025年も適用可能な制度ですが、領収書や使用目的の明確化など証拠の保管は必須です。
※参考:国税庁 『少額減価償却資産の必要経費算入』
旅費規定による出張・打ち合わせ経費の計上
旅費規定を定めることで、出張や打ち合わせにかかる交通費・宿泊費を定額で非課税支給できます。領収書が不要になるケースもあり、事務負担を軽減できます。適用には事前に旅費規定を作成し、実態と乖離がないよう運用することが重要です。税務署も確認ポイントとして注視しています。
従業員や役員へ支給する旅費(日当等)は、合理的な旅費規程に基づき、通常必要と認められる範囲であれば非課税となります。ただし、出張命令書や精算書など証拠書類の整備は必要です。 一方、個人事業主本人に“日当”を支給しても非課税手当にはならず、原則として実費相当の旅費のみが必要経費となります。
※参考:国税庁 『給与所得となるもの(非課税とされる旅費の範囲)』
法人化のタイミング検討
年収1,800万〜2,000万円を超えるコンサルタントは、法人化による節税効果が見込めます。役員報酬の設定で所得分散が可能になる一方、社会保険料が増加する場合もあります。法人化のメリット・デメリットを比較し、収入見通しとライフプランを踏まえて判断することが重要です。
「コンサルタント」が経費として認められるものと認められないもの
経費として認められるものの例
業務関連の書籍
セミナーや研修受講料
オンラインサロン会費
通信費(インターネット・携帯代など)
打ち合わせ時の飲食費
自宅兼オフィスの家賃や光熱費(家事按分の割合による)
経費として認められないものの例
私的な旅行費用(家族旅行・観光目的の出張など)
家族や友人との食事代(事業に無関係な交際費)
自宅の生活費(家賃・光熱費・食費などの私的部分)
純粋な資産形成費用(株式投資、個人用不動産購入など)
罰金・反則金(交通違反の反則金などは経費不可)
所得税・住民税の納税額(税そのものは経費にならない)
医療費や生命保険料(個人的な支出のため)
経費として認められるものと認められないものを見分ける判断基準と気を付けるポイント
1. 事業売上に直接関係があるかどうか
経費として認められるためには、その支出が事業の運営や売上の獲得に直接必要なものであるかが重要なポイントです。また、金額が大きければ大きいほど、なぜ事業に必要な費用かを説明できるようにしておきましょう。
(例)仕入費、広告宣伝費、業務に必要な通信費など。
2. 私的な支出と区別できるか
個人の生活費やプライベートな支出はもちろん経費になりません。たとえば、事業に必要な消耗品と一緒にお酒やタバコなどの嗜好品を購入した場合、税務署はこれらをまとめて経費から除外(概算で按分して除く)することがあります。このため、私的な嗜好品などは事業用と明確に分けて購入・管理することが重要です。
(例)自宅の家賃のうち事業使用部分のみ経費化。事業に必要な文房具などの消耗品は単独で購入。
3. 法律や税法上の制限
法律や税法では経費として認められない支出が決まっており、たとえば罰金や反則金、所得税や住民税といった納税額は経費(損金)にできません。また、法律で認められた範囲を超える寄付なども経費として認められないため注意が必要です。
4. 経費計上の合理性・必要性
税務署に説明できる合理的な理由が必要です。単に節税のためだけに支出を増やすのではなく、実際に事業活動の中で役立つものであることがポイントです。たとえば、業務に使う消耗品や接待費は、取引先との関係維持に必要と認められれば経費になりますが、過剰な飲食やプライベートな趣味にかかる費用は合理性が乏しく否認される可能性があります。相場より高い価格で物品やサービスを購入していないかも確認されることがあります。
また、支出の内容や目的が明確であり、適切な証拠(領収書や契約書など)があることも必要です。税務署に説明できるよう、支出の背景や必要性を示せることが経費計上のポイントとなります。
「コンサルタントの節税」対策で注意すべき4つの落とし穴
過度な経費計上は税務調査のターゲット
経費を増やせば一時的に税負担を減らせますが、業務関連性が低い支出を多く計上すると税務調査で否認されるリスクが高まります。特に高収入のコンサルタントは調査対象になりやすく、家族旅行や高額接待などプライベート色の強い支出は要注意です。
対策としては、領収書には日付・会食相手・目的をメモしておくと、税務調査時の説明がスムーズになります。適正な経費計上と証拠保管が信頼維持の鍵です。
税理士に丸投げしっぱなしにしない
税理士に記帳や申告を依頼していても、経費の妥当性や証拠保存は事業主本人の責任です。電子帳簿保存法やインボイス制度の影響で、取引データや請求書の管理が厳格化しており、何かあった時に『知らなかった』では通用しないのが現実です。税理士との連携は不可欠ですが、自ら最新情報を把握する姿勢が必要です。
節税ファーストは危険
節税を優先するあまり、不要な設備投資や過度な経費支出を行うと、本業資金やキャッシュフローを圧迫するなど、本末転倒となってしまいます。特に高額な資産購入は資金回収まで時間がかかり、資金ショートの原因になります。節税は運営している事業の利益を残すためのひとつの手段であり、長期的な事業計画や資金繰りとセットで考えることが重要です。
最新税制改正の確認(電子帳簿保存法・インボイス等)
2024年以降、電子帳簿保存法やインボイス制度など、事業者を取り巻く税務ルールが大きく変わっています。対応が遅れると、控除が受けられない、経費が認められないといった直接的な損失につながります。高収入なコンサルタントほど取引規模が大きく影響も甚大なため、常に最新情報を把握する必要があります。
まとめ|専門家との早期連携(税理士・FP)で「コンサルタントの節税」とコストの最適化
高収入のコンサルタントほど、節税の有無で可処分所得に数百万円単位の差が生じます。重要なのは、見せかけの利益ではなく実際に使えるお金を最大化する戦略です。また、当然ながら事業を運営するための本質的な活動も重要です。そのためには、毎年の税制改正に合わせて節税策をアップデートし続ける必要があります。
青色申告や控除制度の活用、経費計上の精度向上だけでなく、将来の資産形成やキャッシュフローも視野に入れた計画が欠かせません。税務はもちろん、案件選定やキャリア戦略まで最適化するには、専門家(税理士)に加え、業界の知見が深いエージェントと早期に連携し、長期的な視点で事業を設計することが最善策です。
※本記事は国税庁・総務省・各種公的機関の公表情報をもとに一般的な節税対策を解説したものです。実際の適用可否や金額は、所得・家族構成・社会保険・自治体ルール等により異なります。具体的な申告や適用判断については、所轄税務署や顧問税理士に必ずご確認ください。
<おすすめ記事>
【ケース面接の代表的なパターンと例題・解答】<賛成・反対の立場表明④>「経団連が定める画一的な就活ルールの導入について」
https://insight.axc.ne.jp/article/careernavi/7217/