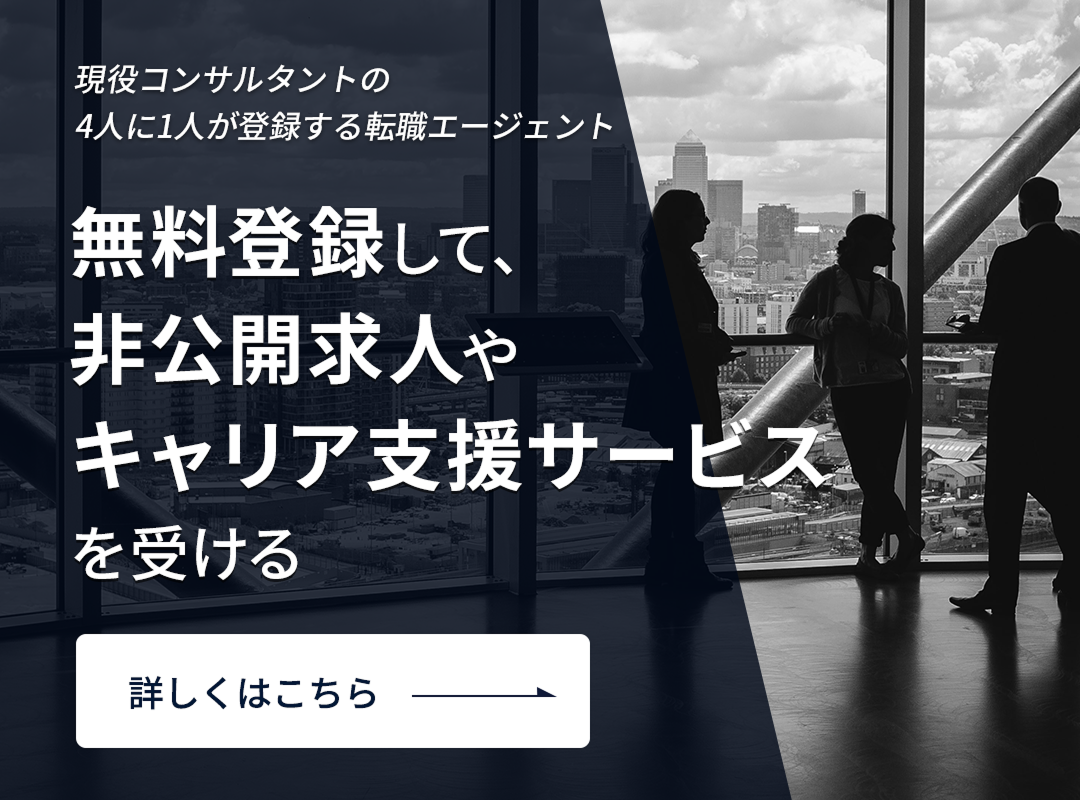M&A後のパターン別「PMIの成功事例」と注意点

コンサルタントとしてM&A関連のプロジェクトに従事している人もそうでない人もPMIという言葉は聞いたことがあると思います。PMIという言葉は何となくM&Aの後におこなう作業というイメージがあっても実際にどのような実務上のポイントがあるのかをコンサルタントとしての今までのキャリアと結びつけながら読んでイメージ頂ければ幸いです。
<おすすめ資料集(無料ダウンロード)>
PEファンド転職におけるテクニカルチェックのポイント
https://insight.axc.ne.jp/material/fund_preparation/310/
Index
M&Aの成功を左右するPMI、その定義と定性的な特徴
PMIとは
M&A(Mergers and Acquisitions、企業の合併・買収)において、取引が成立した後に必ず直面するのが「PMI(Post Merger Integration:ポスト・マージャー・インテグレーション)」です。これは、買収先と買収企業をどのように一つの組織として融合し、戦略や業務を統合していくかというプロセスを指し、事業会社でもPEファンドによる買収でも必ず課題になる論点です。
PMIの目的は単なる形式的な統合ではなく、M&Aによって掲げられた成長戦略やシナジーを最大限に実現することにあり、さらに人事や社風などの融合などの定性的な面も多分に持ち合わせています。
PMI失敗パターンの簡単な説明と重要性
しかし、現実にはPMIの失敗によって想定したシナジーが得られず、むしろ買収が経営の重荷となるケースも少なくありません。よくある失敗パターンとしては、統合のスピードが遅すぎること、経営層の意図が現場に浸透しないこと、組織文化の違いが軽視されることなどが挙げられます。
M&Aの成否を決めるのは、買収そのものではなく、むしろその後のPMIにあると言っても過言ではありません。このような失敗は事業会社でよく見られる傾向がありますが、これは一重にメンバーのM&Aにおける経験不足によって海外の買収先と言語面での壁を感じてしまいコミュニケーション面でハードルがあることに起因することがあります
PMIで統合するオペレーションの内容やアプローチ
PMIでは、統合の範囲が多岐にわたります。大きく分けると以下の要素があります。
経営体制の統一
ガバナンスや意思決定プロセスを一本化することが最重要課題です。取締役会の構成やCEO/COOの役割分担など、トップレベルでの指揮系統を早期に明確化する必要があります。これは買収者がファンドでも事業会社でも重要で、100%買収した場合には、株主の方から役員を過半数派遣する等のアプローチがあり得ます。
業務・内部システムの統合
企業ごとに異なる業務プロセスやシステムをどのように一本化するかが課題です。基幹システム(ERP)、会計システム、CRMなどの統合は短期的に混乱を招きやすく、事前の移行計画とリスク管理が不可欠です。ITに関する課題はM&Aでは思いのほか大事で、ITシステムの統合、既存のシステムやパッケージは使えるのかどうか等が課題になってきます。
人事・組織編成の統合
買収先の人材をどのように配置し、どのような評価制度を適用するかは極めて繊細な問題です。自分の頑張りがインセンティブに反映されないような杓子定規な報酬制度だと優秀な人材が離脱してしまう可能性があり、想定した成長シナリオが大きく揺らぎます。また既存の人材だけではバリューアップが難しい場合には、買収後に迅速にバリューアップを果たすために、彼らを一から教育するより外部からプロ経営者や財務、同業他社で経営幹部クラスの経験があるハイスキル人材を起用することが多いです。
社内文化・風土の統合
文化の融合がPMI最大の難所とされます。企業によって価値観や働き方のスタイルが大きく異なるため、摩擦が起こりやすいのです。形式的な施策ではなく、従業員が一体感を持てるようなコミュニケーション戦略が求められます。特に買収後には社員からの感情的な反感がある可能性もあるので、従業員の文化やスタンスを尊敬しつつ、自社の文化を融合できるように配慮することが肝要です。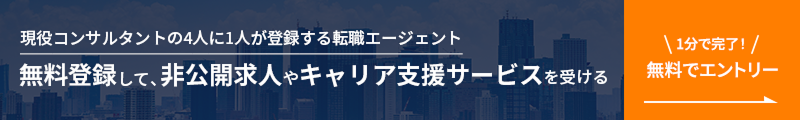
「PMIの成功」のために注意するべきポイント
PMIを成功に導くためには、いくつかの重要な視点があります。
統合計画の策定
PMIでは『最初の100日』が勝負と一般的に言われることが多いように思われます。PMIではいわゆる100日プロジェクトを立てることが多く、この期間にどのような統合ロードマップを描くかが成否を分けます。ダラダラ時間をかけていては買収して企業価値を上げるのに時間とコストだけ使ってしまうため、可能な限り迅速に進めることが求められます。具体的なタスク、責任者、リソースを明確にし、進捗を定期的にレビューする仕組みが欠かせません。ファンドが買収するときには投資委員会に置ける資料でも、買収後のアクションプランや、バリューアップできるのはどのようなエリアかを明記することがあるので、PMIと整合する事業計画も作成する必要があります。
目標やタイムラインの明確化
M&Aで掲げたシナジー効果(コスト削減、新規事業の創出、シェア拡大など)を定量化し、いつまでにどの程度実現するかを明確に設定する必要があります。曖昧な目標設定は現場の迷走を招きます。ですので、クロスセルによるシナジーなのか、調達先の最適化によるコスト減なのかなどを明確にして現場レベルで進めることが肝要です。
適切な意思決定メンバーとのコミュニケーション
経営陣だけでなく、事業部長や現場リーダーを巻き込み、双方向のコミュニケーションを徹底することが肝心です。「現場の理解と納得」を得られなければ、いくら戦略的に優れた統合計画でも実行段階で頓挫します。本社やファンド側から担当者をそのまま送るよりも、先ずは従業員とオフラインのコミュニケーションを重視して、徐々にコミュニケーションを融和することが肝要です。
従業員への透明性の確保
組織改編や人事制度変更などは従業員の不安を招きます。噂や憶測が蔓延するとモチベーションが低下するため、経営陣が直接メッセージを発信し、将来像を示すことが重要です。特に人事制度や報酬制度はモチベーションに直結するので、適宜外部コンサルタントと連携してから進めることが良いでしょう。
<おすすめ資料集(無料ダウンロード)>
PEファンド・投資銀行転職におけるLBOモデリングテストの解き方
https://insight.axc.ne.jp/material/fund_preparation/309/
事業シナジーを最大化させた「PMIの成功事例」と教訓
ここでは、実際に事業シナジーを引き出すことに成功したPMIの事例を紹介します。
ケース1:重複機能の整理による効率化
ある製造業のM&Aにおいて、両社は同じ部品を扱う部門をそれぞれ持っていました。統合後、重複部門を一本化し、購買・生産機能を集中させたことで、調達コストを15%削減。さらに、開発リソースを再配分し収益性が高い製品にR&Dのリソースを割くなどプロダクトミックスをレビューしつつ新製品投入のスピードも向上しました。このように、統合後のシナジーを製品別の収益性に着目しプロダクトミックスを改善させ具体的に数字で示せた点が成功要因です。
ケース2:新事業創出につながった戦略的統合
IT企業同士の統合では、買収企業が持つ強固な営業網と、買収先が持つ独自技術を融合させ、新規市場でのサービス展開を加速させました。買収側の企業は大病院向けの電子カルテを提供していましたが、小規模の病院はなかなかカバーできていませんでした。一方で、買収先の企業は中小規模の病院やクリニックを顧客としてカバーしていたので、結果として統合前は互いにリーチできなかった顧客層を取り込み、売上が3年で1.5倍に拡大。事業シナジー、特にクロスセルの機会を戦略的に描き、それを現場レベルで具現化した好例です。
組織文化の統合を成功させた「PMIの成功事例」
事業シナジーの実現と並んで、最も困難とされるのが組織文化の融合です。成功事例を見ていきましょう。
ケース1:異なる企業文化を融合させた成功例
ある外資系のファンドが日本に子会社を有する企業を買収した際、初期段階では意思決定スピードやリスク許容度の違いから摩擦が生じました。特に日本の子会社は東京の現地メンバーにより運営されており本社との意思決定スピードや商慣行の違いから摩擦が生じやすい環境にありました。
そこでファンドおよび経営陣は、双方の文化を無理に一本化するのではなく、『スピード重視』と『慎重な品質管理』を両立させる新しい行動指針を策定しました。また日本法人の社長を欧米のメーカーで勤務経験が豊富で英語が堪能な人材に入れ替えることで意思決定のスピードを速くすることもできました。同時にインセンティブ設計を入れ込んだ魅力的な報酬制度を設計し、高い士気がある土壌が醸成されました。
ケース2:従業員モチベーションを維持・向上させた例
国内のサービス業での統合では、買収される側の企業の従業員に不安が広がったため、統合直後から経営陣が定期的にタウンホールミーティングを実施しました。経営陣および新しいトップが直接各従業員に対して今後の方針を説明し、納得できない従業員にはパッケージを与えて退職していただく、残りたい従業員は意見を吸い上げる双方向型のコミュニケーションを行いました。
その結果、ロイヤルティの高い従業員が残り離職率も大幅に低下し、社風も悪化せずに済んだのです。
まとめ
M&Aにおいて、PMIは単なる「アフタープロセス」ではなく、むしろ成否を決定づける最重要フェーズです。これらはDDの段階からある程度どのポイントがPMIで重要になるかを見定めながら経営体制やシステム、人材配置といったハード面の統合に加え、文化や風土といったソフト面の統合にも真剣に取り組むことが不可欠です。
中堅からシニアのコンサルタントに求められるのは、クライアント企業が直面する統合課題を俯瞰的に整理し、経営層と現場をつなぐ「橋渡し役」としての視点です。また、現場のメンバーとコミュニケーションできる泥臭さも重要なポイントです。成功事例から学べるのは、PMIには計画性とスピード、透明性、そして人間的なコミュニケーションが不可欠だということと、人事や報酬面の工夫がカギになるという点です。
<おすすめ資料集(無料ダウンロード)>
PEファンド転職における財務三表の作り方
https://insight.axc.ne.jp/material/fund_preparation/311/