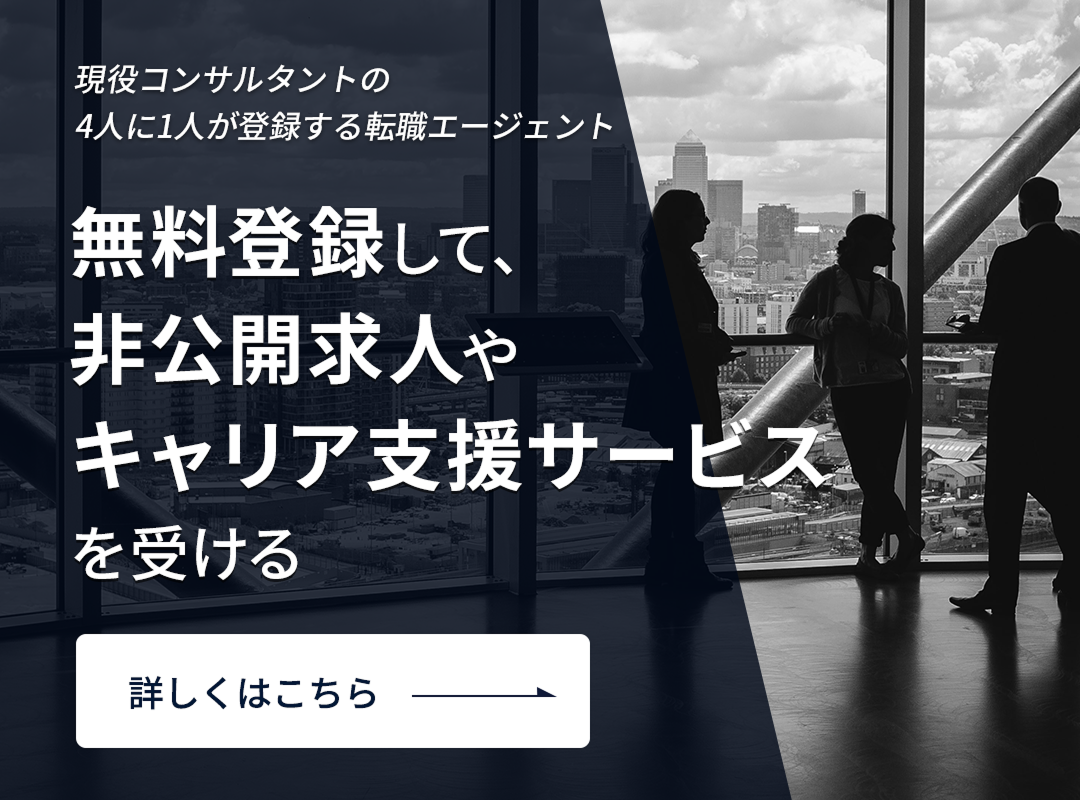三菱UFJリサーチ&コンサルティング 社会共創ビジネスユニット ヘルスケアコンサルティング室 インタビュー/先端医療から街づくりまで、官民連携と金融機能で実現する新時代のヘルスケアビジョン

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(以下、MURC)社会共創ビジネスユニット ヘルスケアコンサルティング室は、医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決と事業価値の創出を両立する特色ある組織です。同社の強みである官公庁とのネットワーク、シンクタンク機能による調査・分析力、そして三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)の金融機能を活用し、再生医療などの先端医療から中小企業の医療機器参入支援まで、幅広い領域でコンサルティングを展開しています。
特に注目すべきは、単なる産業支援にとどまらず、人々の健康と幸せを実現する社会システムの構築を目指す先進的なアプローチです。官公庁の案件である、2050年の未来を見据えた「ヘルスケアタウン構想」など、従来の医療の枠を超えた新しい価値創造にも取り組んでいます。
今回は、ヘルスケアコンサルティング室長の外石満様、マネージャーの戸田雅也様、コンサルタントの大坪佳右様に、同室の活動内容や目指す未来像、そしてチームの特徴についてお話を伺いました。事業会社での豊富な経験を持つ3名が語る、ヘルスケア分野の課題解決に向けた熱意あふれる取り組みをご紹介します。
※内容は2024年11月時点のものです
Index
事業会社での豊富な経験を生かし、ヘルスケア業界の革新に挑む – 再生医療からデジタルヘルスまで幅広い知見を持つ専門家集団
田中
まずは皆さまのご経歴と、現在どのような事をされているのかお聞かせください。
外石様
理系の大学院を卒業後、新卒でソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)に研究者として入社し、10年ほどキャリアを積みました。当初はヘルスケア領域とは異なる分野でしたが、途中からライフサイエンス機器の新規参入プロジェクトに携わりました。このプロジェクトでは、本分野への新規参入をゼロベースで検討し、途中で米国企業のM&Aも経験しながら、約5、6年で事業を立ち上げ、現在は100億円規模のビジネスにまで成長しています。その後、2社のコンサルファームを経て、2016年にMURCに入社しました。
入社当初は中堅企業向け経営コンサルティングの部隊に所属し、経営や財務など、それまで経験してこなかった全社を通した戦略も幅広く経験を積みました。そして4年前にセクター特化型の部門としてヘルスケアコンサルティング室を4名のメンバーで立ち上げ、現在は15名程度の人員まで増強しております。

田中
次にお二方の経歴についてもお聞かせください。
戸田様
理系の大学院修了後、理化学研究所でのポスドクを経て、国内大手の医療機器メーカーで約10年間、医療機器の開発に携わりました。その後、国内大手化学メーカーに転職し、医療分野以外にもコンシューマー製品やウェルネス関連など、幅広い事業の企画・分析・マーケティングを経験し、2023年12月にMURCに入社しました。
化学メーカーでの業務は、事業企画や事業推進、マーケティング調査など、社内コンサルのような立場での支援がほとんどでした。今回の転職では、事業会社のマーケティングも視野に入れておりましたが、自身のキャリアを棚卸しした際にこれまでのキャリアやスキルは、コンサルタントという立場でも活かす事が可能であり、立場が変わるだけで自身の仕事の本質は大きく変わらないと考え、事業会社よりも幅広い分野の案件に携わりたい希望もあり、MURCへの入社を決意しました。
選んだ理由は、MURCの持つ独自の強みにあります。1つ目はシンクタンク部門を持つという特徴から官との連携がしやすい点があります。2つ目はMUFGの一員として、事業支援だけでなく、金融面での提案も可能な点です。
そして私が最も重視した点は、医療機器産業の将来を見据えた支援ができる環境が整っている事です。現在、国内の医療機器市場は約3兆円、ヘルスケア機器市場は約8兆円規模です。大企業は豊富なアセットを持っているため自力で成長が見込めますが、この市場のさらなる発展には中小企業の育成が不可欠です。しかし、医療機器などの産業は規制が厳しく、簡単に新規参入できない分野の1つです。そこで金融の力を活用しながら中小企業の成長を支援し、ひいては日本の医療産業全体の発展につなげていく。このビジョンが、私の思いと強くマッチしました。

大坪様
新卒でニプロ株式会社に研究職として入社し、3年間在籍しました。主に再生医療など製品や再生医療・バイオ医薬品関連部材の開発プロジェクトに携わりました。特にコロナ禍では、ワクチン製造関連のシングルユース(使い捨て型)製品が国内で不足する事態を受け、新規事業立ち上げのメンバーとして活動しました。
コンサルティング業界への転職を決めた理由は、再生医療などの先端医療の実用化において、一企業では解決できない課題を実感した事がきっかけです。MURCでは、コンサルティング部門とシンクタンク部門で連携し、再生医療などの先端医療分野において官公庁と連携した社会課題解決に向けた取り組みをされていました。民間企業のコンサルティングだけでなく、社会課題の解決と企業支援の両立ができる環境だと感じ、2022年に入社を決意しました。また、シンクタンク部門と連携しているMURCでは、国の最新動向を把握している事で、クライアントに新たな示唆を提供できる事もあります。特に、発展途上の先端ライフサイエンス産業では、社会実装に向けた課題解決と企業支援の両立が求められ、実現できる環境にやりがいを感じています。

3本柱で差別化を図るヘルスケアコンサルティング室 – ライフサイエンス、デジタルヘルス、事業拡大支援を軸に
田中
ヘルスケアコンサルティング室の概要についてお聞かせください。
外石様
MURCにおいて、セクター特化型のコンサルティングを掲げているのは、現在ヘルスケアコンサルティング室だけです。自動車やエネルギー、環境などさまざまな分野がある中で、ヘルスケアは特に領域の専門性が求められ、官との連携なども重要な分野です。
大手の戦略ファームを含め、各社がヘルスケアセクターを持つ中で、どう差別化を図るかが当初からの課題でした。その中でわれわれの特徴は、シンクタンク部門との連携も生かした先端領域における専門性の発揮、官との連携を生かした事業化支援、そしてMUFGとのつながりを活用した金融や海外進出支援など、他社がリーチできない、もしくは他社に対して優位性のある領域でのサービス提供にあります。
田中
チームの体制について教えていただけますか。
外石様
現在は明確なチーム分けは行っていません。ヘルスケアと言っても、製薬、医療機器、官公庁案件、食品、介護領域などさまざまな業界やテーマがあります。メンバーはそれぞれ得意とする分野や業界を持ちながら、新規事業や海外進出といった機能も含めて幅広い経験を積んでいます。マネージャー層になると専門分野が固まってきますが、メンバー層はさまざまな業界やテーマを経験できるように柔軟な体制を取っています。
田中
主にどのような案件を手掛けているのでしょうか。
外石様
案件には、大きく3つの柱があります。1つ目は、再生医療、遺伝子治療などの先端的なライフサイエンス分野です。新しい創薬技術や基盤技術の開発を支援しており研究開発や制度設計なども含めて対応しています。2つ目は、デジタルヘルスです。従来の飲み薬か飲み薬や注射剤のみならずアプリ治療(デジタルデバイスを活用した、エビデンスに基づいた疾患の予防や治療・予後の管理)への展開や、データを活用した医療の実現、創薬への応用などを手掛けています。3つ目は、新規参入や事業拡大支援です。医療機器分野への新規参入支援や、海外進出支援、新事業領域への拡大などを行っています。これら3つの領域がそれぞれ約3分の1ずつの売上構成となっています。
田中
官民連携は、全ての案件で発生するのでしょうか。
外石様
必ずしもそうではありません。官だけのプロジェクト、民間だけで完結するプロジェクト、そして両者の連携が必要なプロジェクトと、さまざまです。たとえば研究開発の初期段階では、民間企業だけでは投資判断が難しい場合があります。そういった場合、官の支援も受けながら大学などとの連携で研究開発を進め、徐々に民間主導に移行していくというパターンがあります。また、規制産業という特性上、開発が進んだ段階で承認などの面で官との関わりが必要になる事もあります。このように、プロジェクトの段階や性質に応じて、官民連携の形は変化します。

医療機器の新規参入支援から再生医療の社会実装まで – 各メンバーが専門性を生かして取り組む最前線の課題
田中
現在、実際にどのような案件に携わられていますか。
戸田様
私は主に医療機器関連とヘルスケアデバイス関連を中心に担当しています。具体的には、新規参入支援や事業拡大支援です。企業様からは「新規参入したい」という相談から、「開発した製品をどのように販売すればよいか」という拡販に関する相談まで、さまざまなご要望をいただいています。
特に中小企業支援において重要なのは、企業様において経済産業省や日本医療研究開発機構(AMED)などで採択された国家プロジェクトの成果を持続的なビジネスに転換する事です。医療機器産業では、一度製品を市場に供給すると継続的な供給責任が生じます。そのため、単発的な成果で終わらせないよう、連続的なビジネスモデルの構築をサポートする事に注力しています。
田中
シンクタンク部門やMUFGとの連携について、現場レベルではどのようなメリットを感じていますか。
戸田様
医療機器産業は特に事業立ち上げに多額の資金を必要とします。そのため、金融機関との連携は非常に重要です。よって、資金調達面においてMUFGとの連携は大きな強みとなっています。
また、金融支援は一時的な資金提供だけではありません。医療機器を継続的に供給し続けるための経営基盤の構築・安定化において、金融機関との連携は最も重要な役割を果たします。特に中小企業の場合、この継続的な供給体制の構築が大きな課題となっています。
田中
大坪様はどのような案件を担当されていますか。
大坪様
私は主に再生医療、遺伝子治療などの先端的なライフサイエンス分野において、民間企業の新規事業参入支援や、同分野に関して、官公庁向けの調査や委員会事務局業務を実施し、社会課題解決に向けた政策提言なども行っています。
印象に残っている案件として、再生医療で用いられる他家細胞(※自分の細胞ではなく、他人から提供された細胞を培養したものを移植する細胞の事)の国内安定供給体制の構築があります。本事業では、再生医療関連企業や医療機関、有識者との議論を通して、課題の整理および解決に向けた取り組みなどを検討しました。細胞原料を提供いただくドナーの善意を裏切らないよう、将来の患者に再生医療など製品を届ける事を目指し、一般の方や、再生医療関連企業・医療機関の方々への情報発信やガイダンスの作成を行いました。
外石様
本事業は、非常に重要な産業政策の一環でした。再生医療は、自分の細胞を使用するのではなく、他者の細胞を培養したものを移植して治療を行うケースが増えています。これは輸血や臓器移植と同様に高い公共性が求められる分野です。
しかし、治療用の細胞に関しては、輸血や臓器移植とは異なり、製薬企業が細胞を培養させて投与するといった一定の加工が必要となります。人から無償で提供された細胞で利益を得る事の是非が問われるなど倫理的な論点が生じます。これまで日本はこれらのドナーとなる細胞原料を海外からの輸入に頼ってきました。しかし、今後の産業発展のためには、国内での供給体制の確立が不可欠です。この課題に対して、法制度の整備から、国民の理解促進、産業としての発展可能性まで、さまざまな側面から4、5年かけて取り組んできました。
田中
研究開発職からコンサルタントに転身されて、仕事の面で大きく変わったと感じる点はありますか。
大坪様
事業会社の研究職では特に、自社の新規技術や製品開発にフォーカスされがちです。しかし、コンサルタントとして企業をご支援させていただく中で、技術だけでなく、市場規模や顧客ニーズ、競合や規制の動向など、幅広い側面から開発戦略を考えられるようになりました。
ヘルスケア産業の未来を見据えた3つの重点分野 – 人々の健康と幸せを実現する社会システムの構築へ
田中
現在のヘルスケア業界において、市場環境やニーズがどのように変化しているとお考えですか。また、そうした変化の中で、チームではどのような役割を果たしていきたいとお考えでしょうか。
外石様
ヘルスケア分野における最大の課題は、国民の健康維持とそれを支える財源の確保という、相反する要素のバランスを取る事です。言い換えると、いかにコストを抑えながら質の高い医療を提供できるかという課題です。
この課題に対して、われわれは3つの重点分野で貢献していきたいと考えています。
1つ目は先端的なライフサイエンス分野です。たとえば、がん治療のような分野では、新しい技術開発が不可欠です。特にヨーロッパなどでは費用対効果の観点からの医薬品など治療法の評価が厳密に行われています。単なる効果効能だけでなく、経済性が評価されるわけです。われわれは、国との連携や先端的な知見を生かしながら、こうした新技術の産業化をさまざまな側面から支援します。
2つ目は予防医療の分野です。高血圧や糖尿病などの慢性疾患に対して、継続的な投薬に頼るのではなく、予防的なアプローチを強化する事で、医療費全体の抑制を図れる可能性があります。最近では「ウェルビーイング」という概念が注目されていますが、個人の努力だけでは限界があります。そこで企業が従業員の健康管理をサポートし、場合によっては人間ドックの数値が良好な場合にボーナスを上乗せするなど、インセンティブを設ける取り組みも出てきています。米国では医療保険会社がこうした取り組みを主導しているケースもありますが、日本でも機運が高まってきています。特に注目すべきは、世界的な潮流として、従来のGDP(国内総生産)に代わる新しい指標としてGWP(Global Wellness Product)の検討が進んでいる事です。これが企業評価の指標として定着すれば、投資家の関心も高まり、企業として社員への予防医療への取り組みが加速する可能性があります。
3つ目は医療・介護現場の効率化です。高齢化が進む中で、限られた財源で質の高い医療・介護サービスを提供するためには、介護の効率性の向上が不可欠です。介護ロボットなどの機器の活用も含めて、より効率的なサービス提供体制を維持する事で、一定のコストを抑制しながら、高齢者に安心安全なサービスを提供していく必要があります。
田中
チームの規模に関してはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
外石様
現在、新メンバーを含めると17名程度の規模になっています。2025年度の早い段階で20名程度まで拡大したいと考えています。MURCとしてヘルスケアセクターの全般のお客さまに対して一定の専門家を揃えて、トータルでソリューション提供する事を想定すると、30名前後が規模の目安となりますので、まずはそこを目指していきたいと思います。
田中
それぞれの立場から、今後の展望についてお聞かせください。
戸田様
われわれ社会共創ビジネスユニットの重要なミッションの1つは、日本の社会課題の解決です。医療現場の喫緊の課題として、外科医の減少(美容整形は除く)と外科医の平均年齢の上昇があります。このままでは、外科医不足により、必要な手術を受けられない時代が来る可能性があります。医師の育成には10年、20年という長期的な取り組みが必要ですが、その間の対策として、予防医療の強化や医療現場の効率化が重要になってきます。
具体的には、病気の進行を遅らせる取り組みや、限られた医療リソースの有効活用、手術時の切開を可能な限り少なくするなどの患者の体への負担を低減した低侵襲治療の促進などが考えられます。たとえば、通常の手術であれば1~2週間の入院が必要ですが、内視鏡手術であれば1泊2日で退院できるケースもあります。こうした低侵襲治療を増やす事で、病床の効率的な運用が可能になります。
現在、整形外科だけでも年間80万件の手術があり、今後は100万件を超えると予測されています。一方で外科医は減少傾向にあり、この需給ギャップは深刻な社会課題となっています。
2つ目に、日本の医療機器は輸入に大きく依存している状況です。今後、日本のGDP低下などにより、必要な医療機器が入手できなくなるリスクも懸念されます。こうした課題に対しても、中小企業による新規参入は重要な役割となり、支援を通じて社会課題の解決に貢献したいと考えています。

大坪様
日本の医薬品市場は約15年前には米国に次ぐ世界第2位でしたが、現在は中国に追い抜かれ、シェアは半減しています。また、創薬の標的分子が枯渇しつつあり、新薬開発の成功確率も25000分の1と言われるほど低いのが状況です。
このような状況に対して、AIなどのデジタル技術を活用して、新規の創薬ターゲットを探索する動きが出てきています。多くの製薬企業が海外進出を模索する中、国内市場向けの医薬品の安定的な供給体制の確保も、重要な課題です。たとえばたとえば、ジェネリック医薬品の供給不足も深刻な問題となっています。われわれには、このような社会課題とも向き合いつつ、企業の新規事業戦略を構築する事が求められております。
また、MURCでは、あらゆる分野に強みを持つコンサルタントが在籍しております。ヘルスケアと宇宙、ヘルスケアと自動車といった、ヘルスケアと異分野との掛け合わせによって、これまでにない価値創造が可能になると考えています。従来の枠組みを超えた、新しいヘルスケアの未来を切り開いていきたいと思います。
田中
お三方それぞれの視点から、ヘルスケア領域の将来像について興味深いお話を伺いました。特に印象的なのは、従来の医療の枠を超えた新しい価値創造の可能性です。この観点から、今後のヘルスケア領域において、どのような変革が求められるとお考えでしょうか。
戸田様
ヘルスケアは近年、さまざまな産業との境界が曖昧になってきています。たとえば、先ほど外石が説明したデジタルヘルスはITそのものですし、単なるものづくりではない仕組み作りも重要になってきています。本質的な目的は、人々が長く健康で、幸せな生活を送れる環境を作る事です。医療はそのための手段の1つに過ぎません。
重要なのは、ヘルスケアを単なる産業として捉えるのではなく、人々に安心安全を届けるための社会システムとして考える事です。これからの課題解決には、特定の技術や規制対応だけでなく、社会課題の解決に向けて幅広い視点で考えられる人材が必要です。そういった人材とともに、新しい価値創造に挑戦していきたいと考えています。
外石様
われわれは2050年の未来を見据えた時、病院での治療を中心とした従来型の医療から、生活全体で健康を実現する包括的なアプローチへと転換していく必要があると考えています。
冒頭でも少々触れましたが、官公庁の案件である、2050年のヘルスケアを特化したまちづくりについて、将来予測を行った際に、各種有識者の方々と議論を重ねました。そこで見えてきた共通のビジョンは、医療を病院内に限定せず、街での生活を通じて自然と健康になれる環境を作る事でした。
たとえば、日常生活の中で自動的に高血圧をチェックできたり、音楽を聴く事でメンタルヘルスが改善されたり、単に歩くだけでもメタボの改善につながるような仕組みを、駅や会社、学校などさまざまな場所に組み込んでいく。そういった未来のヘルスケアタウンの実現が、人々の負担を減らしながら健康を実現する1つの解決策になると考えています。
まちづくりの中にヘルスケアの視点を組み込み、日常生活の中で自然と健康になれる環境を整備していく。そのためには、医療機器、製薬、IT、都市開発など、さまざまな分野の知見を組み合わせていく必要があります。われわれはそうした未来に向けて、多様なアプローチから課題解決に取り組んでいきたいと考えています。
専門性と多様性を重視し、切磋琢磨できる環境づくりを目指す – 年齢や経験を問わない実力主義のチームカルチャー
田中
チームメンバーの構成について教えていただけますか。
外石様
中途採用者は、製薬企業や医療機器メーカーなどのヘルスケア業界の出身者が多いですが、新卒メンバーは多様なバックグラウンドを持っています。バイオ系の専門知識を持つ理系人材はもちろん、医療経済や法律を学んだ文系人材も在籍しています。志望者は理系バックグラウンドの方が多い傾向にありますが、特定の専門性に限定しているわけではありません。コンサル出身者も在籍していますが、それほど多くなく、コンサル未経験でも事業会社で企画業務など一定の経験を積んでいれば問題ないです。
田中
チームの特徴や、どのような人材を求めているのかについて、お聞かせください。
外石様
われわれが最も重視しているのは、それぞれが専門性を持ちながら切磋琢磨し、互いに足りない部分を補完しながら成長していける環境作りです。出る杭を打つのではなく、個性を生かしながら成長できる環境を目指しています。
たとえばたとえば戸田は医療機器のエキスパートとして専門性を発揮しています。求めるのは、その専門性に加えて、周辺知識もベースとして持ちながら、新しいテーマや社会に訴求できる課題を生み出せる人材が理想です。
戸田様
われわれの仕事は、野球チームに例えると分かりやすいかもしれません。ピッチャー9名では試合はできません。それぞれのポジションに応じた専門性が必要です。ヘルスケア産業自体が既にテクノロジーの垣根を越えている現状では、専門性だけでなく、周辺領域まで広く見渡せる視野が重要です。
特に重視しているのは、課題解決型の思考ができる事です。医療の世界では一歩間違えば不幸な事故につながりかねません。「注意一秒、怪我一生」と言われるように、病気や健康など人生に影響を与える産業だからこそ、目的は何か、そのための手段は何かを常に考えられる人材が必要です。
大坪様
若手の視点からお話しすると、私自身コンサル経験が全くない状態で入社しましたが、OJTやOFF-JTを通じてしっかりと育成していただいています。マネージャー層では、特定の領域での専門性が求められますが、若手に関しては、完璧な専門性は求められていません。たとえば、医療機器メーカー経験2、3年で入社される方が、同業界で十数年以上のキャリアを持つ方と同じレベルの専門性を持つ事は現実的ではありません。
むしろ重要なのは、ヘルスケア産業の未来について考え、自分の経験を生かして新しい価値を生み出そうとする意欲です。「こんな未来があるのではないか」という発想を持ち、それを周囲と共有し、実現までの課題や解決の施策などを考えられる人材を求めています。面接でもそのような話が自然と出てくる方は、入社後に大きく成長される可能性が高いと感じています。

メンバーの成長と社会課題の解決を両立 – 多様な案件と充実した支援体制が生み出すやりがい
田中
チームで働く中で、どのようなやりがいを感じていらっしゃいますか。
外石様
マネージャーの立場から申し上げると、私のミッションは、メンバー1人1人が働きやすい環境を整え、成長を支援しながら、きちんと成果を出していく事です。各メンバーの興味や適性を見極めながら、適切な教育機会を提供し、チームとして成果を上げていく事にやりがいを感じています。
実際に営業活動も行いながら、チャレンジングな案件に挑戦する機会を作り、メンバーの興味を引き出し、共に取り組んでいくプロセスも重要だと考えています。
戸田様
私は2023年12月の入社ですが、前職での経験が生かせる事もあり、スムーズに仕事に取り組めています。もちろん会社の文化に慣れる事への苦労はありましたが、日々楽しく仕事をさせていただいています。
特に若手メンバーと一緒に仕事をする際は、興味を持って取り組んでもらえるよう、チーム編成を工夫しています。コンサルティングファームは人材育成に注力しないイメージがあるかもしれませんが、OJTを通じて育成にかなり力を入れています。
また、さまざまなクライアントとお話をする中で、想定以上に困難な課題に直面しているケースに出会う事があります。そこから新しい気づきを得られる事も多く、それが仕事の面白さにつながっています。数値目標を達成しなければならないプレッシャーはありますが、それ以上に「MURCだからこそできる仕事がある」というやりがいを強く感じています。
大坪様
私が感じているのは、若手でも積極的に動ける環境が整っているという事です。他のコンサルティングファームでは年間1、2件の案件に関わる事もあると聞きますが、当室では同時に4、5件の案件を3カ月タームで並行して担当する事もあります。そのため、さまざまなプロジェクト経験を積む事ができます。
方向性が違う場合は適切な指導がありますが、若手でも主体的に動く事ができ、その結果、着実に成長を実感できる環境があります。
さらに、チームのリーダーではなくても、サブリーダーとしてプロジェクトを動かす機会も柔軟に与えられます。周囲も成果や行動をしっかりと見てくれており、社会共創ビジネスユニット以外の部署からも声がかかるなど、成長に応じて活躍の場が広がります。このように、やりたい事が実現でき、成長を実感できる環境がある事が、大きなやりがいにつながっています。
田中
最後に、皆さまから一言ずつメッセージをお願いします。
外石様
概して言えば、われわれは皆で成長していける土壌を用意しています。その中で一緒に成長していける方をお待ちしています。
成長の機会として、案件の規模はさまざまです。数千万円規模のものから100万円程度のものまであります。小規模案件では若手でも1、2名の少人数で担当する事があり、その経験を通じて大きな自信につながります。大規模なプロジェクトにおいて1つの特定タスクを担当するのと、小規模でも全体を幅広く担当するのとでは、得られる経験値が大きく異なります。
このように多様な経験ができる環境の中で、ヘルスケア産業に興味を持ち、共に成長していける方と一緒に働きたいと考えています。MUFGのバックグラウンドやシンクタンク機能など、成長を支える基盤は整っています。
戸田様
MURCには、お客さまの課題解決に必要なアセットが十分に用意されています。その中で重要なのは、お客さまの課題を解決し、喜んでいただける事に楽しさを見いだせるマインドです。コンサルティングでは、さまざまな制約がある中でお客さまの悩みを解決し、その達成感を味わえる事が魅力です。
また、医療機器に限らず、産業全体が急速にアップデートされている現在、常に新しい知識を吸収していく姿勢も大切です。そういった前向きな姿勢を持った方と一緒に働ける事を楽しみにしています。
大坪様
私は、特定分野だけでなく、幅広く興味を持っている方に来ていただきたいと考えています。
当室では製薬、医療機器、食品、介護など、さまざまな領域のプロジェクトを手掛けています。そのため、ヘルスケアの幅広い分野に興味を持ち、他の領域も積極的に学ぼうとする意欲のある方が活躍できます。経験がなくても、そういった意欲と積極性があれば、成長を後押しできる環境が整っています。ヘルスケアという分野に幅広い興味をお持ちの方と、共に働ける事を楽しみにしています。

大手電機メーカー、外資系調査/コンサル会社を経て、2015年にMURCに入社。入社後は中堅規模の企業に対する経営コンサルティングに従事する。特にシンクタンクとの連携でヘルスケアセクターの業務を多く手掛ける。2021年にヘルスケアコンサルティング室を立ち上げ室長に就任し、再生医療など他の外資系ファームに対して強みとなるテーマを武器としながらMURCでは唯一のセクター戦略でのコンサルサービスを提供。製薬企業や医療機器メーカー出身のメンバーも加えて、本セクターの事業を拡大中
自然科学系研究所、大手医療機器メーカー、化学メーカー勤務を経て、2023年12月MURCに入社。メーカーでは、医療機器の開発や事業戦略立案などに従事。現在は、医療機器、化学、機械加工、食品などの分野において、新規事業創出支援、事業戦略の策定などの戦略から実行支援まで幅広いコンサルティングに従事
医療機器メーカーの研究開発職を経て、2021年にMURCに入社。医療機器メーカーでは、再生医療など製品や再生医療・バイオ医薬関連部材の研究から開発・製造経験を有する。MURC入社後は、主に先端ライフサイエンス領域において、民間企業の新規事業戦略・事業拡大戦略策定および実行支援や、官公庁向けの調査・政策提言を担当

三菱UFJフィナンシャル・グループの総合シンクタンクとして、東京・名古屋・大阪の3大都市を拠点に、コンサルティング、グローバル経営サポート、政策研究・提言、マクロ経済調査、セミナー等を通じた人材育成支援など、国内外にわたる幅広い事業分野において多様なサービスを展開している。

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの求人情報
| 職務内容 | ヘルスケア/医療・介護分野で事業展開している企業や、当該領域への進出を検討している企業に対し、経営・事業戦略の策定から実行支援まで、一貫したサービス提供を行います。シンクタンク部門とも連携し、最新の技術・社会動向も取り入れながら、日本のヘルスケア産業を活性化させることをミッションとしています ■主なクライアント ■具体的には ・異業種からヘルスケア業界の新規参入支援 ・ヘルスケア業界におけるデジタル化推進 【プロジェクト事例】 |
|---|---|
| 応募要件 | 【必須条件】 【歓迎条件・求める人材像】 |