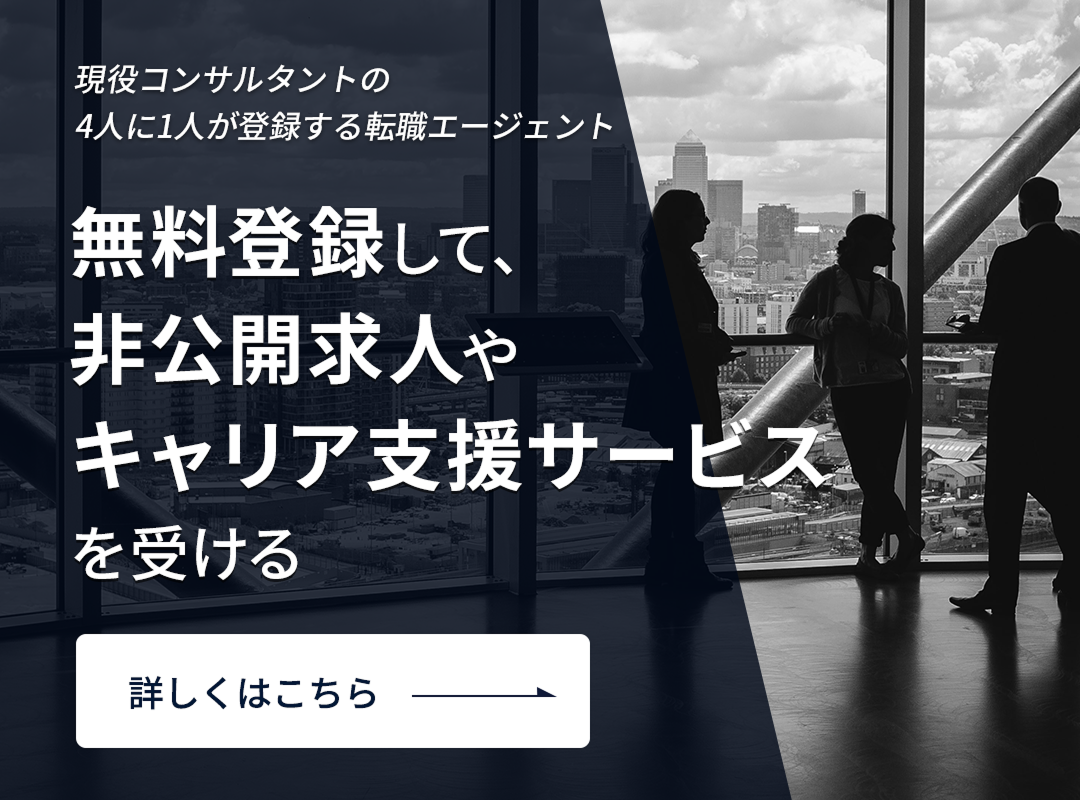三菱UFJリサーチ&コンサルティング 社会共創ビジネスユニット イノベーション&インキュベーション部 インタビュー/「シンクタンク×MUFG」の総合力で挑む社会課題解決、5つのアプローチで実現する経済価値との両立

「社会課題解決×ビジネス価値創造」をビジョンに掲げ、シンクタンク機能と三菱UFGフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)の総合力を生かした独自のアプローチで、企業の経営課題と社会課題の同時解決を目指す三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(以下、MURC) 社会共創BU イノベーション&インキュベーション部(以下、I&I部)。従来型のコンサルティングの枠を超え、技術R&D戦略、新産業共創、未来戦略、社会変革実装、地域活性という5つのユニットで、それぞれの視点から価値創造に取り組んでいます。今回は、社会共創ビジネスユニット長 兼 I&I部長の渡邉藤晴様、そしてユニットを率いる山本雄一朗様、木下祐輔様、鶴田陽平様、名和美南様に、社会課題とビジネスの両立に向けた独自のアプローチや、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集う組織の特徴、そして目指す未来についてお話を伺いました。
Index
社会インパクトへの共通の志―IT、製造、コンサルなど多彩な経験を持つ5人が語るMURCの魅力
田中
皆さまの経歴と入社の背景についてお伺いできますでしょうか。
渡邉様
外資系コンサルを経て、2013年に戦略コンサルティング部門立ち上げメンバーとしてMURCへ入社しました。入社当時は他の外資系ファーム出身者と共に大企業向けコンサルに従事していましたが、通常の戦略コンサルアプローチでは大手外資系ファームには勝てないため、MURCの強みであるシンクタンクやMUFGの協業が武器になると考え、2018年にI&I部を立ち上げました。当初は数名のI&I部も、現在では60名弱の組織に拡大し、2024年4月にヘルスケアコンサルティング室、グローバルコンサルティング部と共に社会共創BUを立ち上げました。
MURCを選んだ理由は2つあります。1つは事業開発の視点で新たなコンサルティング市場を開拓できる機会があったこと。もう1つは、新潟県佐渡島出身として地方活性化に貢献したいという思いがあり、シンクタンクであれば地方創生に関われると感じたことです。

山本様
現在、技術R&D戦略ユニットと新産業共創ユニットの2つのユニットを総括しています。また、MUFGと一緒に大企業領域や新テーマ領域の企画・開発も担当しております。入社は2017年で、新卒時は通信会社でした。先端的な技術やビジネスモデルに基づくアイデアをどのように拡大させ、日本の社会や経済、人類にどう実装するかという視点を、コンサルティングやファイナンスの力でどう実現するかに関心があり、入社を決めました。
MURCを選んだ最大の理由は、戦略的な目線でのアドバイザリーを行いつつ、それが実装につながるための金融機関のソリューション・顧客基盤をふんだんに活用できるからです。コンサルティング企業も百花繚乱となり、顧客に満足いただく意味のあるプロジェクトを組成・推進することが求められているのですが、日本に今最も求められる機能は単なるアイデアや支援だけではなく、骨太な構想に基づく実装だと考え、MUFGの力を活用したいと考え入社しました。
田中
入社時点で、どのような課題に携わっていきたいとお考えでしたか。
山本様
日本に対するインパクトを産業や地域という観点で創出していくために、既存の革新(トランジション)と新規創造の両方の課題に関心がありました。たとえば、水素エネルギーは既存インフラをどう変えていくかという点で既存の革新と言え、一方の宇宙産業は全く新しいものを作る創造的な課題というような形です。どちらにも大きな社会課題や事業機会が紐づいているので、その社会課題を産業という軸、地域や技術という軸からどう解決できるかに強い関心がありました。

木下様
未来戦略ユニットのリーダーを務めています。新卒でMURCに入社し、学生時代は理学部で宇宙物理を専攻し、宇宙や世の中の本質を追究するような研究をしていました。そのため、社会や経済の本質を追究しながら社会に貢献できるような仕事をしたいと考え、シンクタンクを含めたコンサル業界への就職を決めました。
当時、IT機能が大きな比重を占める会社が多い中で、むしろITがないことで純粋な戦略提案ができる立ち位置であることを選択の理由としました。また、社員との面談を通じて、非常に視座が高く、社会全体のことを考えている会社だと感じたことも決め手となりました。
今では未来戦略ユニットとして、未来社会を見据えた日本の産業や社会のあるべき姿をデザインし、創造していくことを目指しています。なお、私が考える未来社会とは、必ずしも遠い未来である必要はなく、社会課題が解決されている社会の状態を指します。
学生時代に宇宙や気象を研究していた関係で、当初はそういったビジネスの創出を考えていましたが、入社後は視野が広がり、社会全体の視野で、産業や企業としての戦略の最適解を考えるようになりました。1つの課題を解決すると別の問題が生じる可能性もあるため、課題の共通項や根本的な部分をしっかり考えていく姿勢で取り組んでいます。

鶴田様
早稲田大学理工学部情報学科を卒業後、自動車メーカーに入社し、IT部門に配属されました。しかし、システムの課題だけでなく、より広い経営課題の解決ができる人になりたいと考え、外資系大手コンサルティングファームに転職。その後、2社のコンサルティングファームを経て、MURCに入社しました。現在は社会変革実装ユニットのリーダーとして、社会課題の解決につながる新規サービス・新規事業の創出に携わっています。
MURCを選んだ理由は、純粋にコンサルタントとしての仕事に集中できる環境があったからです。他社では役職が上がるにつれて営業またはマネジメントの役割が増えますが、MURCではMUFGとの連携により、いわゆる「初期営業活動・機会発掘」をグループとの協力のもとで進められるため、コンサルティングサービスの提案・提供に専念できる環境があります。
社会課題の解決において大切なのは、誰か1人の課題が解決され、喜んでいただけた時の集合体として捉えることであると考えています。たとえば待機児童問題では、社会全体の仕組みを変えることも重要ですが、1人の待機児童がゼロになる瞬間には、具体的なサービスが存在し、それを利用しているはずです。今までになかったそういったサービスを新たに創造していく、いわば社会課題解決のラストワンマイルを担うユニットでありたいと考えています。

名和様
地域活性ユニットのリーダーを務めています。前職は大手製造業の事業戦略部門で、経営戦略やドメイン戦略、新規事業開発などを担当しており、2018年9月にMURCへ入社しました。
入社の背景には、“未来の子どもたちが安心して暮らせる社会を作りたい”という思いがありました。事業会社では既存のアセットに縛られがちですが、そういった制約のない環境で働きたいと考えました。また、面接で渡邉さんから「戦略だけでなく実行まで現場に入り込む」という話を聞き、コンサルティングファームでありながらそこまで踏み込める点に魅力を感じました。
前述の“未来の子どもたちが安心して暮らせる社会を作りたい”という思いは、前職で働いている頃から抱いていたものです。その背景は、われわれは現在、経済面だけでなく、環境問題など、さまざまな負債や課題を解決しきれないまま未来に引き継いでいます。これらの課題解決に少しでも貢献できる仕事がしたいという思いが、私の根源にあります。地域活性ユニットでは、こうした社会課題を捉え、特に地域の視点からアプローチをしています。
地方創生において、官から民の取り組みがある一方で地域の視点やそこで暮らす人の視点に立つことも、安心して暮らせる社会に必要だと考えています。また、都市と地域という二元論など、既存で整理された構図自体に問いを持ちながら、新たなつながりを創り、ある地域のリソースを他地域に持ってきて活性化するといったことに挑戦しています。

5つのアプローチで挑む社会課題解決―未来・技術・地域・実装・産業、それぞれの視点から価値を創造する
田中
I&I部では5つのユニットがあるとお聞きしました。各ユニットの役割や特徴について、全体像をお聞かせいただけますでしょうか。
渡邉様
I&I部の全体像からお話させていただくと、I&I部内には「未来戦略」「新産業共創」「技術R&D戦略」「地域活性」「社会変革実装」の5ユニットがあります。これらはセクターによる分類ではなく、アプローチの違いでチームアップしています。共通の社会課題解決のテーマに対して、それぞれのユニットが異なる視点やアプローチで取り組んでいます。そのため、1つのテーマに対して複数のユニットが関わることもあり得ます。アメーバ型に社会課題解決テーマに関われるような組織を、I&I部は目指しております。
木下様
未来戦略ユニットでは、未来社会を見据えて、社会課題が解決された状態を目指しながら、新規事業やオープンイノベーション、中長期戦略のご支援をしています。われわれは社会課題軸と技術軸の両面からアプローチしています。
具体的には3つの取り組みを行っています。
1つ目は「拡大しつつある“不確実性”の打破」で、経営インパクトの大きな“不確実性”を紐解き、既存の延長線では見落としがちな非連続の可能性を探索します。これは新規事業開発やR&Dの第一歩、ゼロからイチ(0→1)を生み出す段階です。2つ目は「戦略の具体化・合意形成」で、俯瞰的なマップを作成しながら企業の戦略を描きます。3つ目は「社会実装・事業化(マネタイズ・スケーリング)」です。
社会課題解決とマネタイズの両立のためには、1社単独では解決が難しいため、産学官連携を含め複数プレーヤーでエコシステムを形成し、社会課題を解決します。技術軸では、核融合・量子や人間拡張(テクノロジーによって人間の身体能力や知覚などを拡張させる技術)、ロボットといった未来技術をベースに、いかに社会に実装していくのかを含めたR&Dを支援しています。
山本様
技術R&D戦略ユニットと新産業共創ユニットの2チームを担当しております。これらの2チームの特徴は、通常の「戦略コンサルティング」を中核にしつつ事業機会の「探索」、金融機関・シンクタンクとしての「実装」、MUFGによる出資やアライアンス機能を活用した「当事者化」という4つの視点を持ってコンサルティングを推進している点です。
基本的な考え方として、日本の超大企業を中心的な顧客としながら、スタートアップ、金融機関、地場企業、アカデミアなど、日本が既に持っている多様な力を信じ、どう磨きあげるかを重視しています。その結果として日本独自の好循環を生み出すことを目指しており、チームのパーパスを「日本の戦略を編むチカラ」と定め、MUFGのパーパスである「世界が進むチカラになる。」を戦略面から体現する存在として位置付けています。
その結果、対応する事業領域は多岐にわたっており、ものづくりや半導体、GXといったグローバル競争力を担保する産業、それらを発揮していくソフトパワー戦略となる地域戦略、少子高齢化領域やウェルビーイング、組織改革、MUFGらしさも発揮される大規模な不動産・イベント開発、エネルギーや食、森林、海洋といった資源的な事業領域など、多種多様なテーマにおいてクライアントが存在しています。これらの事業領域や課題を編み合わせながら最適解を見つけ、実装に向けた戦略策定などの意思決定支援を行っています。
名和様
地域活性ユニットは、企業をクライアントとして経営アジェンダに応えながら、企業の持つリソースを地域へつなげることをデザインするという手法をとっています。これは、地域だけでなくクライアント企業に対しても多様な価値を生むものです。この動き方は、戦略コンサルのアプローチと地域理解の両方が必要です。そのため、チームメンバーと他の専門部門とのコワーク(協働)によってプロジェクト組成をすることが多くあります。
MURC内では他のセクターごとのコンサル部門や地域テーマの専門家、MURC外では大学連携や地域プレーヤーと協働します。また、全国に支店を持つMUFGの特長を生かし、地域産業や地域企業へのアプローチも行っています。
地域の視点やそこで暮らすヒトの視点に立つ現場でのフィールドワークも重視し行っています。戦略コンサルのアプローチと、現場事象を洞察し気づきを得るアプローチを一貫して行える点が他社にない特長だと考えます。
渡邉様
地方創生に対しては多くのコンサルティング会社が取り組んでいますが、われわれのアプローチは特徴的です。自治体への直接的な支援ではなく、全国にネットワークを持ち、地域創生が会社のミッションとなる企業と組んで戦略を立てることで、その企業のネットワークを活用して地方創生を実現していくアプローチをとっています。このような大企業との協働により社会課題解決の規模と速度を上げられるメリットがありますが、一方で、大企業だけの意向だけが優先されないよう、地元の企業や市民の視点に立つことは常に意識しています。
鶴田様
社会変革実装ユニットの特徴は3つあります。1つ目は、社会課題を解決するためには具体的なサービスの提供が不可欠だと考える点です。これは満たされていないニーズや困りごとに対して、体験価値のあるサービスを提供すること、それによって社会課題を構成する1つ1つ、1人1人の課題を解決することを意味します。併せて、いわゆる「プラットフォーム」が必要だと考えています。1つのサービスをお客さまに提供するだけでは広がりに限界があるため、プラットフォームを通じて規模を拡大し、より多くの企業を巻き込むことや、よりたくさんの企業やコンシューマーの課題を解決することで、大きな社会課題の解決につなげます。
2つ目は、大企業とMUFG、ベンチャー企業やスタートアップを結びつけて社会課題の解決を目指すことです。変革に必要なリソースやノウハウ、機能を持つステークホルダーを集めて、共に取り組んでいくことで、効率的かつ効果的な社会課題の解決を目指しています。
3つ目は、実装と伴走を重視し、「現場の1つ1つの課題が解決される」ところまでしっかりと取り組むことです。戦略部門にいながら「実装」という言葉をユニット名に冠しているのは、このような理由からです。
アプローチの多様性が生み出すシナジー―5つのユニットが織りなすI&I部ならではの価値創造
田中
各ユニットからそれぞれの特徴や取り組みについてお伺いしましたが、これらの多様なアプローチを持つことで生まれるI&I部固有の強みについて、渡邉様からお聞かせいただけますか。
渡邉様
ユニットリーダーの説明の通り、さまざまなアプローチが共存できている点が特長と言えます。大義名分を持ちながら地方創生に取り組む企業は、事業性、マネタイズが課題となります。一方で、地方創生に対しアプリなどのサービスを提供する事業性を重視する企業は、社会課題解決という大義名分を付加することで、そのサービスの取り組みに対する意義が明確になり、サービス導入の蓋然性が高まります。つまり、それぞれの企業や自治体の置かれた立場に応じて、I&I部の各ユニットが、1つのテーマに対し、さまざまなアプローチで補完できることが強みだと考えています。
山本様
このような複合的なアプローチは、従来型のコンサルティングファームではなかなか実現が難しい領域だと認識しています。
一般的には、コンサルティングファームは顧客企業単位でより広く課題解決をご支援するために、複数ユニットのコンサルティングサービスを連携します。たとえば戦略、次に業務、ITといった具合です。しかし、複数のステークホルダーが関わる社会課題解決テーマでは、個別企業の成長を考えるだけでは必ずしも社会全体の解決につながらない可能性があるため、I&I部ではこのような独特なアプローチをとっているのです。
鶴田様
われわれは決まったフォーマットを使わず、すべてクライアントや、その顧客を含むステークホルダー全体を考慮して、いわば「手作り」で対応しているのです。オープンイノベーションなどのプロジェクトでも、1つ1つの企業を見ながら手作りでアプローチしています。そういった柔軟な対応ができることに価値があると考えています。
渡邉様
大事な視点ですね。組織長の立場から言えば、仕組み化、パッケージ化できた方が管理上はポートフォリオが安定し、安心はできます。しかし、まだまだオーダーメードが求められる市場やテーマが世の中にたくさんあります。われわれ単体ではできないかもしれませんが、MUFGやシンクタンク部門との協働により、それが可能になっているのです。

社会課題×ビジネスで未来を創る―新規事業開発から地域活性化まで、I&I部の多彩なプロジェクト事例
田中
企業様と向き合う中で、多く寄せられる課題と、それに対してどのようなバリューを提供できているのでしょうか。また、MUFG様との連携や他社との違いについてもお聞かせください。
山本様
私は技術R&D戦略と新産業共創の2つのユニットを担当していますが、この2つは企業の異なる段階にアプローチしており相談される課題も少々性質が異なります。技術R&D戦略では、企業が有する新しい技術をいかに事業化するか?あるいは新たな技術インフラをどのように製造業の競争力につなげていくか?というもので、入り口に近い相談が多いです。技術の社会実装方法や、経済性と社会性の両立を10年後、20年後を見据えて考えるようなプロジェクトが多いのも特徴です。その最たる例が設備投資になります。設備投資は巨額の資金投資が必要なので、MUFGとして最も多いご相談の1つです。金融機関としての視点も重要なため他社との差異化ポイントとなっています。研究所や企業の技術開発部門、事業部門からの相談が多いですね。
一方、新産業共創ユニットは、そもそものR&Dのフェーズを突破している(しそう)で、新たな企業や地域の柱を創りたいクライアントからの相談が多く、むしろ出口寄りです。業界の1位か2位の企業からの相談が多く、また都道府県などの産業戦略面の相談も増えています。現在10億、20億規模、あるいは国レベルで重視され始めている事業や技術をどう大きくして日本や地方に根付かせるかが課題になりますが、これは当然1社では実現できないため、MURCやMUFG、さらにわれわれがお連れするベストパートナーと共にどのような展開ができるかという提案を求められます。
企業からも地域からも特に増えている相談としては、GX・DXや物流革新、観光領域、などのキーワードが挙げられます。これらは技術的には新しいものが多いのですが、現状の仕組みや前提に変化を求められるものも多く、国のトップランナーや企業、産官学金が一体となってマーケティングや設備投資、組織の他、ルールや市場を変えていく必要があります。その変革の方向性やトップ企業の役割についての戦略策定部分で助言を求められ、またそれに紐づく形でMUFGとの協業や出資、新しい金融手法検討などの相談も多くいただいております。これだけテーマが広く、深いと情報を取得するのも本来は大変なのですが、ここはMUFGの強みで、基本的に重要な情報や分析を持っている方がいらっしゃるので、その方と都度連携し、案件推進効率を飛躍的に高められる点が顧客からも評価されます。
木下様
未来戦略の観点では、多くの大企業が社内シンクタンク的な部門を持っていますが、彼らだけでは対応しきれない課題や専門性が必要な領域、新しい概念の整理などについて、われわれが俯瞰的な視点やアカデミアの視点、MUFGの視点を含めて整理・提案しています。
個別テーマでは、山本さんの話と共通する部分がありますが、入り口と出口の両方で課題を抱えています。入り口では、ディープテックなどの新しい技術の可能性など、影響の大きなメガトレンドや“不確実性”の紐解きにより、R&Dや事業テーマの検討を行っております。出口では、既に新規事業や組織を立ち上げてしばらく成果が出ていない製品・サービスについて、その存続をかけてマネタイズを検討するような相談が多くあります。
これらの課題解決の難易度は非常に高くなっており、従来のソリューションでは太刀打ちできないケースも増えています。そのため、I&I部では新しいソリューションを生み出すことに注力しており、ユニットリーダー間で議論を重ねながら難しい課題への対応を模索しています。
鶴田様
われわれのユニットは、I&I部に最後に加わったという経緯があります。8人ほどのメンバーのほとんどが他部門から移ってきており、社会課題解決という視点が後から加わった側面があります。そのため、新しいサービスを作る力を基軸に持っているのが特徴です。
具体的な例として、子ども向け自転車サブスクリプションサービスの戦略立案があります。子どもの成長に合わせて自転車を交換できるこのサービスは、当初は純粋な新サービス開発でしたが、振り返ってみるとサーキュラーエコノミーの実現という社会課題の解決にも貢献していました。自転車が戻ってくる仕組みを作り、戻ってきた自転車は少し安い価格で提供できるプライシングを設計しました。これにより使用実態の把握や製品改善にもつながり、非常に価値のあるサービスとなっています。
このように、サービスを作る力と社会課題解決の仮説を考える力、そしてそれを実際に実現した実績がわれわれの強みです。20年間でさまざまなサービスを作ってきた経験は、他社にはない特徴だと思います。
名和様
地域活性ユニットの観点から見ると、企業の課題として最も大きいのは新しい成長の種を見つけることです。特にここ数年、地域に着目する大企業が増えています。これまでもCSRとして地域貢献は行われてきましたが、今はビジネスとして地域を捉える相談が増えています。
その背景として、都市部での市場成長が頭打ちになっている一方、地方には独自の個性が残っていることが多く、新しい事業の可能性を感じさせることがあります。
企業の検討ステップは大きく3つあります。まず「地域」と言われても実態が分からないという段階。社会課題に関する情報は豊富にありますが、本質的な課題や背景の理解にはリサーチが必要です。次に、事業性を持った上で自社として何をすべきか、財務的・非財務的な成長につながる施策は何かを考える段階。さらに、次のステップでは周囲の市場環境への社会的インパクトが意識されるようになります。
最近では、これらの取り組みを可視化したいというニーズも多く、経済的・社会的指標を定量的に示すことで、次年度のリソース確保や資金調達、組織内での理解促進、地域の方々への説明や新たな仲間作りにつなげていただいています。

多様なバックグラウンドと”社会へのインパクト”への共通の志―事業会社・コンサル・新卒など多彩な人材が活躍するI&I部の採用哲学
田中
各ユニットそれぞれどのような属性の方がいらっしゃるのでしょうか。
渡邉様
全体像をまず申し上げると、I&I部全体で60名ぐらいの規模です。新卒入社とキャリア入社が半々となりますが、人数はチームごとにバラつきがあります。
山本様
私の担当する2ユニットは合わせて35名程度で、その内訳は新卒入社が10名強、元コンサルが4、5名、事業会社出身が20名程度という構成です。事業会社出身者のセクターは本当にバラバラで、商社もメーカーも流通も金融も、さまざまな業界から来ています。また、ユニットの特徴として出向者も多く、MUFGからの出向者もいれば、クライアント企業からの出向者も多数います。
田中
メーカー、金融、商社、さまざまなバックグラウンドの方がいらっしゃる中で、採用時はどのような点を重視されているのでしょうか。
山本様
正直なところ、われわれの活動領域はグローバルやソフト・ハードあるいは資源も含む広範なものなので、特定のセクターや業界出身者を求めているわけではありません。特に中途採用の方々は、前職で何かしらの課題に向き合っていた経験があり、そこで感じた限界を超えようとしている方が多いです。その「次にやろうとしていること」が事業・産業・技術のいずれであったとしても、われわれの提供できる切り口で実現できるかを重視しています。結果として、入社いただく方の産業背景や経験は多様であればあるほど望ましいという形になっています。実際、「コンサルの経験はないが、ある課題を解決したい思いがある」ということで一緒に案件組成に動き、それが案件化したような例も多いです。

渡邉様
共通する特徴として、大手通信会社や大手重工会社など、大企業出身者が多いです。彼らは新卒時に「社会を変えたい」といった強い志を持ってそれらの会社に入ったものの、大企業ならではの難しさの中で、やりたいことができない、あるいは社会課題解決への思いを実現できないといった経験をされています。そういった方々はMURCの理念に共感しやすく、親和性が高いように感じます。
鶴田様
私自身も自動車メーカーを辞めた経験がありますが、1つの企業では経営課題の解決、さらに社会課題の解決の能力・経験を身に付けられない、実現できない、という思いがありました。そういった思いに共感できる人であることが前提です。その上で能力も重要で、20年コンサルタントをやってきた中でさまざまなメンバーを見てきた経験から言うと、思いは強くても能力が伴わないと厳しいのも事実です。社会にインパクトを出したいという強い思いと能力の両方が必要です。
木下様
われわれの会社は他のコンサル会社とは少々異なる人材を求めているように思います。日本を良くしたい、社会を良くしたいという強い思いを持って社会的インパクトを追求したい人との親和性が高いですね。これは価値観の問題で、「3年でマネージャーになって稼ぎたい」とか「コンサルタントとしての威信を示したい」という方は、おそらく大手の戦略ファームを選ばれるケースが多いかと思います。面接時にもこの価値観の部分は個人的に重視しています。
渡邉様
興味深い傾向として、最近はMURCの選考を辞退された方が、他のファームへの転職ではなく元の会社に残るケースが増えています。候補者が在籍する企業が、転職を抑制するために社会課題解決につながる仕事や役職を用意するようになっているのだと思います。われわれにとって、いわゆるコンサルティングファームよりも、候補者の方が現在在籍している大企業が採用競合となってきているような印象があります。
鶴田様
私はBig4出身で当時の同僚たちと今でも親交がありますが、彼らの多くは業界やコンピテンシーごとに専門性を高めています。それに対して、われわれのユニットは「カオス」と言われるほど幅広い活動ができます。社会課題解決というキーワードさえ合致していれば、究極的に何でもできる。それがわれわれのユニットであり、MURCやI&I部の良さだと思っています。後は本人次第ですね。
田中
他の大手ファームのように、特定の業界や領域を限定するのではなく、社会課題解決という観点で幅広い可能性を提供できるということですね。
渡邉様
ただし、社会課題解決だけでは十分ではないという側面もあります。MURCに限らず多く会社が社会課題解決に取り組んでいますが、なかなかマネタイズができないという課題を候補者はお持ちです。そのような背景から、社会課題解決への思いと経済性の両立に悩む候補者が、社会共創BU、その中でも特にI&I部に興味を持っていただいています。
鶴田様
I&I部に来れば、その両立ができる可能性があるということです。
渡邉様
もちろん100%実現できるとは言い切れませんが、MUFGの一員として、経済性との両立を目指して活動していることは間違いありません。MURCでなら、その両立ができるかもしれないと思っていただける方に、ぜひ門をたたいていただきたいですね。
木下様
経済性と社会性の両立は確かによく聞くテーマです。しかし、それを誰がどのように実現するのかという問題があります。その実現に必要な機能の1つが金融であり、金融が果たす役割は非常に大きいのです。実際、金融以外にはその仲介役を担う存在はほとんどありません。特に、ファンドと銀行では視点やアプローチが大きく異なり、時間軸にも違いがあります。銀行は、本当の意味での経済性と社会性の両立を目指し、10年、20年といった長期的な視点で物事を捉えています。
経済性あるいは社会課題解決の検討に限界感じているお客さまも増えています。経済合理性か社会課題解決か、いずれを優先する場合でもわれわれとしてはお客さまの悩みに寄り添った解決策を提供するようにしています。よくクライアントと話す中で、「この企画は非常に良いと思うのですが、銀行からの金融支援を受けられません」という話になることがあります。銀行の金融支援が難しい場合、その解決策の実現は難しいということになりますが、そこで議論を終わらせないようにしています。投資家や金融機関が金融支援を承認するために何が必要なのかという議論に発展させていくことが重要になります。そこに社会課題解決と経済性の両立の可能性が生まれるのです。これは日々直面している課題であり、チャンスでもあります。

名和様
われわれのユニットでは、地域の視点・ヒトの視点に立ち、洞察することも重要視していますので、戦略コンサルのベーススキルに加え、多様なバックグラウンドを持った人に来ていただきたいです。
山本様
われわれのユニットに向いている人材には2つの特徴があります。1つは仕組みを変えたり作ったりすることが好きで、その仕組み自体を動かすことも好きな人材です。日本の仕組みに課題が多いからこそ社会課題が生まれ、経済性と社会性が両立しにくい状況になっています。その仕組みや仕掛けに興味を持てることが重要です。
また、自己変革が好きな人も求めています。成長には自分を否定する勇気が必要ですが、ハングリー精神を失わず、自分がさらに良くなれると期待している人が向いています。
渡邉様
MURCには、レバレッジを効かせられる環境があります。MURCはMUFGの看板もあり一定の知名度を有しております。また戦略特化のファームの中では比較的規模も大きく、社内にはシンクタンク機能も持っています。このような環境を生かして、社会課題や産業創造といった大きなテーマに関わりたい人、また、それを自分の力だけでなく、MUFG・MURCのさまざまなケイパビリティを活用して実現したいと考える方に、われわれは多くの機会を提供できると考えています。
“心の距離が近い”組織文化―チャレンジを歓迎し、価値ある対話を重視するI&I部の風土
田中
I&I部の組織カルチャーについて、どのようにお考えですか。
鶴田様
これまでの議論でだいたい見えてきているかもしれませんが、最も特徴的なのは、どのようなチャレンジも奨励されているという空気、素地があることです。私は別のユニットから移ってきたので、この特徴を特に強く感じます。I&I部はメンバー同士の信頼関係も強く、新しいことへの挑戦を互いに支援し合う文化があります。
田中
若手でも裁量を持てる機会があるとお聞きしましたが、実際にはいかがでしょうか。
渡邉様
クライアントと対峙するにはプロとして相応の力量が必要ですが、I&I部は、画一的な組織ではないため、自分で能動的にチャレンジできる環境は整っています。実際、そのような機会を生かすことで、若くしてクライアントと対等に対話できる若手も増えています。
鶴田様
私は、中身を考える力とお客さまをドライブする力は別物だと考えています。若いうちから中身を考える力という観点では、I&I部内ではどこでもチャレンジ可能です。「これをやりたい」という提案を積極的に歓迎しています。
ただし、クライアントとの関係構築は段階的に進めています。そこは私が顧客接点・顧客対応の面をサポートしながら、徐々に成長を促します。中身をしっかり考える力を身に付けていけば、自然とお客さまへの説明機会も増えていき、結果的に戦略コンサルタントとしての総合的な成長も早くなります。
木下様
コミュニケーションは、さまざまな工夫をしています。BU横断でコミュニケーションプラクティスという活動を行い、既存社員と新入社員とのランチ会や、リアルな場でのワークショップ、オンラインでのテーマ別対話など、多様な取り組みを展開しています。普段話さない人との対話を生む仕掛け作りを心がけています。
名和様
事業会社との大きな違いは、個性の尊重です。たとえば飲み会に行かない人も、「その人らしさ」として自然と受け入れられる風土があります。
渡邉様
われわれの組織の強みはアメーバ型の横のつながりにあります。MURCには専門家が多く在籍しており、いつでもどこでもヒアリングできる環境があります。その環境を生かせるかどうかは本人次第ですが、逆に言えば、本人にチャレンジ精神があれば学ぶ環境は無限と言えます。
たとえば、前職では社内の他部門の専門家と会話するためには複数の階層を経由する必要があり、なかなかアクセスもできませんでした。しかし、MURCの専門家へは新卒入社して間もない社員であっても直接話しかけられ、またそれが面白い提案であれば耳を傾けてもらえます。一方で、「面白い」と思ってもらえるテーマかどうかは重要になるため、聞き手にしっかりとこちらも価値を提供できるかどうかが求められてきます。年次や役職に関係なく、「面白い」と双方が思うテーマがあれば対話が生まれる。そういった実態のあるコミュニケーションが築けています。
鶴田様
一般的なコンサルティングファームでは、上位役職者は威厳を示すような雰囲気もあると思いますがI&I部のユニットリーダーの皆さんは実は相当な役職者なのに、そういった雰囲気を全く出していない。誰が話しかけてきても気軽に答えてくれる。渡邉さんも他のユニットリーダーも、心の距離が近いのです。
渡邉様
それは意識的に各リーダーにお願いもしています。単に役職が上だから、という考え方ではスタッフはついてきてくれません。常に新しい、面白い価値を提供し続けることが重要になります。I&I部にはお金のためだけに仕事をする方はおそらくいませんので、面白いプロジェクトを常に提供し続けることが、われわれリーダーの責務なのです。各リーダーがその認識を持ってくれていることで、排他的ではなく合理的で建設的なコミュニケーションができているのかもしれません。
鶴田様
だからこそわれわれは常に真剣に仕事と向き合っています。面白いものや価値の高いものを提供し続けないといけないという責任感が、リーダー全員にあるのです。
このような組織文化が、I&I部の特徴であり強みになっているのだと思います。

社会課題解決と経済価値の両立を目指す人材へ―5人のリーダーが語る、次世代へのメッセージ
田中
最後に、これからI&I部を目指す方々へのメッセージをお願いできますでしょうか。
鶴田様
世の中にない事業やサービスを生み出すことを通じて、社会へのインパクトや社会課題の解決を実現したい人に来てほしいと思います。大きなことを実現したいけれど、細かい部分もしっかり見ていきたいという、欲張りな人を待っています。コンサルの経験は不要です。入ってから育成していくという考えです。
名和様
さまざまな価値観やご経歴、スキルを持つ方々と共にお仕事をしたいと思っておりますので、異業種・異分野の方々も大歓迎です。
木下様
一緒に日本社会を良くしていきたいという思いで汗をかける覚悟のある人と働きたいですね。
山本様
2つの要素を重視しています。1つは、仕組みを変えたり作ったりすることが好きで、その仕組み自体を動かすことも好きな人。もう1つは、自己変革・成長にこだわりがあり、まだハングリー精神を失っていない、自分自身に期待する、自分の成長を信じ切れる人です。
戦略コンサルティングはプロに、プロとしてアドバイスをするという点で厳しい世界ですが、日本のさまざまな産業や技術、産業の深淵に毎日触れられるという点にやりがいを感じる方が向いていると思います。
渡邉様
あらためまして、MURCには国内トップレベルのシンクタンク機能と国内トップの金融グループであるMUFGとの連携といった強みがあります。この強みをレバレッジし、自分の力だけでなくさまざまなケイパビリティを活用して社会課題解決や産業創造といった変革を実現したい人と、われわれは一緒に仕事をしたいと考えております。ぜひとも、ビジョンに共感いただける方は、応募いただけますと幸いです。
事業会社、外資系コンサルティング会社を経て2013年にMURCに入社。社会課題解決に資する未来予測や先進技術など「半歩先の新テーマ開発」を目的に、2017年にイノベーション&インキュベーション部を設立。同部長。2024年4月には、「社会課題解決と産業創造の拡大」をミッションとする社会共創ビジネスユニットを立ち上げ、ビジネスユニット長に就任。MURCのシンクタンク部門や調査部、さらにはMUFGの大企業支援チームと連携し、「MURCにしか出せない価値」をお客さまに提供できるよう、パートナー企業や行政機関との協業プロジェクトを推進中
大手通信会社を経て、2017年にMURCに入社。戦略コンサルティング機能を活用した産業活性化に向け、MUFGの各機能と連携しながら推進。「技術R&D戦略ユニット」「新産業共創ユニット」の責任者。「日本の戦略を編むチカラ」というユニットスローガンの基、GXやDX、サーキュラーエコノミー、物流、地方創生・スマートシティといった日本の地域や産業のキーワードに関連した戦略案件が中心的な案件であり、直近ではエンタメビジネスや高付加価値観光・インバウンドなどの新たな潮流に対してもクライアントを拡大している
大学院を修了後、2007年にMURCに入社。2050年を見据えた未来予測や技術動向、俯瞰的な社会課題認識などを通じたバックキャストによる戦略検討を特徴としている部内組織「未来戦略ユニット」の責任者。未来を「予測する」だけでなく「創り出す」ことを重視しており、シンクタンク×MUFG×コンサルティングファームの使命として、よりよい未来社会や産業のデザイン・創造を志向。2023年からは東海国立大学機構名古屋大学の客員准教授に就任し産学連携・オープンイノベーションに従事
大学卒業後、大手自動車メーカー、会計系総合コンサルティングファーム、日系独立系コンサルティングファーム、ベンチャーコンサルティングファームにて主に通信・ITサービス・テクノロジー企業の戦略・マネジメントコンサルティングに従事したのち、MURCに入社。社会課題解決に必須な新規事業・サービスを実装させるためのラストワンマイルを担う「社会変革実装ユニット」の責任者。特にサービス業に対する新規事業・新サービスの戦略・企画・立ち上げ・セールス向上に向けた事業化支援を得意とする
大手製造業の事業戦略部門を経て、2018年にMURCに入社。企業への戦略コンサルティングをべースに、経営アジェンダへ対応しながら地域活性を生み出す「地域活性ユニット」の責任者。フィールドワークや地域実証と社会デザイン、ステークホルダー連携を得意としており、実行段階まで伴走。企業の力を地域の社会的・経済的価値につなげる仕組みづくりに、常に挑戦中

三菱UFJフィナンシャル・グループの総合シンクタンクとして、東京・名古屋・大阪の3大都市を拠点に、コンサルティング、グローバル経営サポート、政策研究・提言、マクロ経済調査、セミナー等を通じた人材育成支援など、国内外にわたる幅広い事業分野において多様なサービスを展開している。

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの求人情報
| 職務内容 | 大企業戦略コンサルタント |
|---|---|
| 職務内容 | イノベーション&インキュベーション部(I&I部)は、社会課題解決を主眼に、シンクタンクならでは・MUFGならではの価値提供を追求し、未来洞察・先端技術・先鋭ニーズなどによる新潮流を捉えたコンサルティングを、“研究”ではなく“実証実験≒事業化”の実現を目的に2017年4月に発足しました。I&I部は、事業化・経営課題解決を推進する戦略コンサルタントを中心に、専門性の高い当社のコンサルタント・研究員の他、スタートアップ企業や各分野の専門家、さらにはデザインファームと連係することで、個の力だけではなく、総合力でクライアントの課題解決、さらには社会課題解決への貢献を図ってまいります。また、MUFGの基盤も活用し、日本が強みとして保有する技術・サービスなどが世界標準となるよう支援していくことを目指します ◇未来戦略イノベーション ・具体的な取り組み内容 ◇主なクライアント 【プロジェクト事例】 ・中長期戦略支援 ・未来社会デザイン |
| 応募要件 | 【必須条件】 【歓迎条件・求める人材像】 |