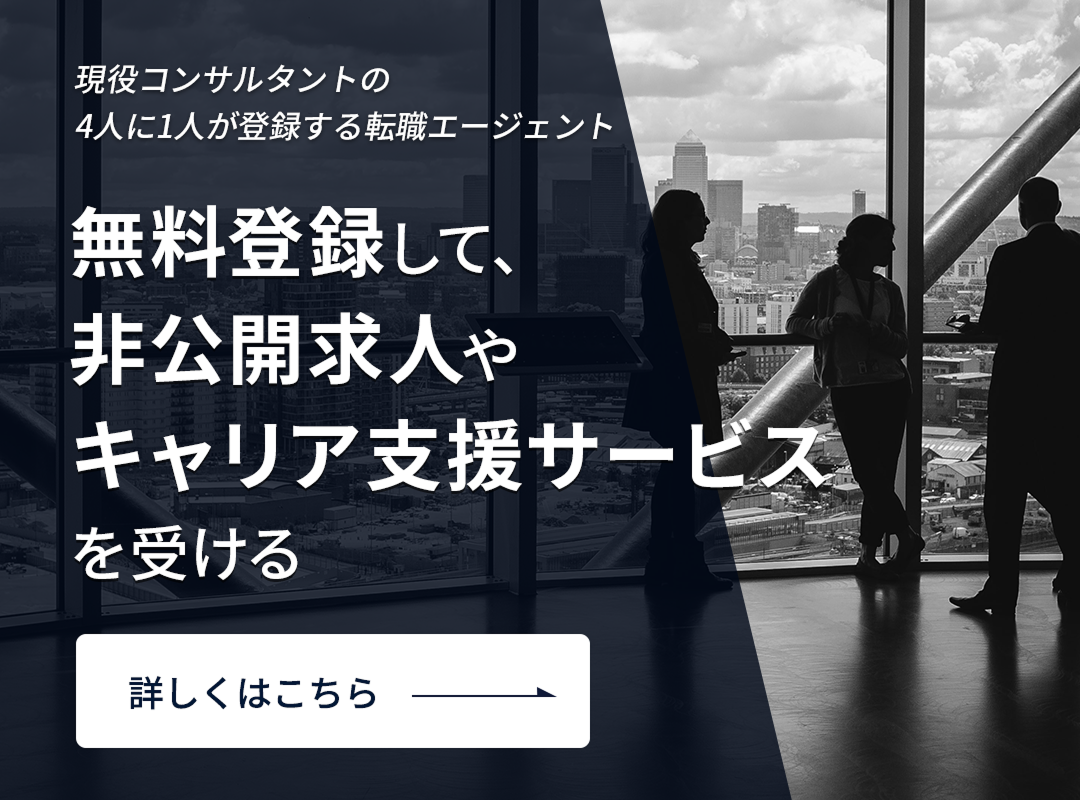ReGACY Innovation Group株式会社 パブリックセクター&ガバメントグループ インタビュー/地域産業クラスターの創出に、コンサルを超えた「総合格闘技型」支援で挑む

株式会社サムライインキュベートからスピンアウトし、2022年に誕生したReGACY Innovation Group株式会社。「日本のレガシー産業から新たなイノベーションを生み出す」をミッションに、パブリックセクター&ガバメントグループでは、大企業や自治体、大学・高専、官公庁などと連携し、インキュベーションやオープンイノベーションを推進しています。
特に地方創生や研究機関の社会実装支援において、単なるコンサルティングではなく、事業開発やファイナンス機能も備えた総合的な支援を特徴としています。
今回は、同社のパブリックセクター&ガバメントグループを率いる取締役 兼 執行役員 桶谷建央様に、地域イノベーションへの取り組みや、社会課題解決とビジネスを両立させる独自のアプローチについてお話を伺いました。
※2025年3月時点での内容です
Index
「構想」だけで終わらせない。レガシー産業に変革を
江頭
ReGACY Innovation Group様は、社内インキュベーターとしての活動を経て、スピンアウトという形で独立されたと伺っています。その背景や、創業時に込められた思いについて教えていただけますか。
桶谷様
ReGACYはもともと、国内の有力ベンチャーキャピタルの社内インキュベーション部門として発足しました。大企業や自治体、大学・高専、官公庁などと連携し、スタートアップ支援や新規事業の立ち上げを行ってきましたが、2022年2月にスピンアウトという形で独立し、現在のReGACY Innovation Groupとして再出発しました。
事業の柱としては、大きく2つあります。
1つは、大企業のアセットを活用してゼロから事業を創出する「インキュベーション」支援。もう1つは、スタートアップや外部プレーヤーと連携しながら既存事業を拡張していく「オープンイノベーション」です。
私たちが創業時に掲げたのは、「日本のレガシーな産業から、新しいイノベーションを生み出すこと」。これは、地域や産業が抱える構造的な課題に対して、経済性と社会性を両立させながら価値を生み出していく挑戦です。ただし、もともと所属していたVC(ベンチャーキャピタル)では「ファンド運営」と「インキュベーション」の両立に課題がありました。ちょうどファンド規模を拡大するタイミングで、私たちのような事業サイドが独立して動くことが中立性の確保にもつながると判断し、独立を決意しました。
社名の「ReGACY」は、「Legacy(遺産)」の頭文字を“R”に置き換えた造語です。「再構築」「再生」「変革」といった意味を込め、既存の価値を生かしながら新たな未来を作る。その意志を象徴しています。実際に私たちは、大企業のみならず、地方自治体や研究機関といったパブリックセクターとも密に連携しながら、日本全体にとっての“社会的インフラ”となるような事業創出に取り組んでいます。
江頭
ありがとうございます。ReGACY様全体として多様な領域に取り組まれている中で、桶谷様が担っていらっしゃる“パブリック領域”について伺えればと思います。具体的に、自治体や大学といったクライアントが抱える課題について教えていただけますか。
桶谷様
パブリック領域の課題には、自治体と大学、それぞれに異なる構造があります。
まず自治体についてですが、日本には「消滅可能性都市」と言われる地域が数多く存在しています。将来的に地域の存続が危ぶまれている自治体は、全体の過半数にも上るとされています。こうした地域が持続的に発展していくには、“イノベーション”以外に解決策はないと私たちは考えています。
自治体が産業を活性化させるアプローチとしては、大きく2つのアプローチがあります。1つ目は、特産品など自分たちの資源を活用して地域の価値を高める「オーガニック型」。2つ目は、工場や研究機関などを誘致する「インオーガニック型」です。
しかし、「消滅可能性都市」とされる地域では、どちらも実行が難しいのが現実です。既存の産業基盤が弱ければ、ECなどを通じた特産品販売で多少売り上げが伸びたとしても、地域経済全体に与えるインパクトは限定的です。一方で、外から企業を呼び込もうとしても、インフラが整った中堅都市と比べると、わざわざ人や設備を投下する必然性が生まれにくい。結果的に、どちらの打ち手も取りにくい八方ふさがりの状況になっています。
結果として、新たな収入源を作れず、若年層の流出や学校の統廃合が進み、地域の魅力がさらに失われていく。こうした悪循環が自治体の最大のジレンマです。
一方で、大学や高専といった研究機関も、また別の課題に直面しています。特に地方の国立大学では、かつてのように優れた研究を起点とした好循環を維持するのが難しくなっています。
その要因の1つが、科研費をはじめとする研究資金の削減です。研究資金が減れば、研究の質が下がり、優秀な研究者が集まりにくくなる。すると、学生も集まらず、学費収入も減って大学運営がさらに厳しくなる、という負のスパイラルに陥っている大学も少なくありません。
このような状況の中で、いかに自律的な資金モデルを作り、研究成果を社会実装につなげていくか。その突破口として、私たちが提供しているのが“イノベーション支援”というオファリングサービスです。
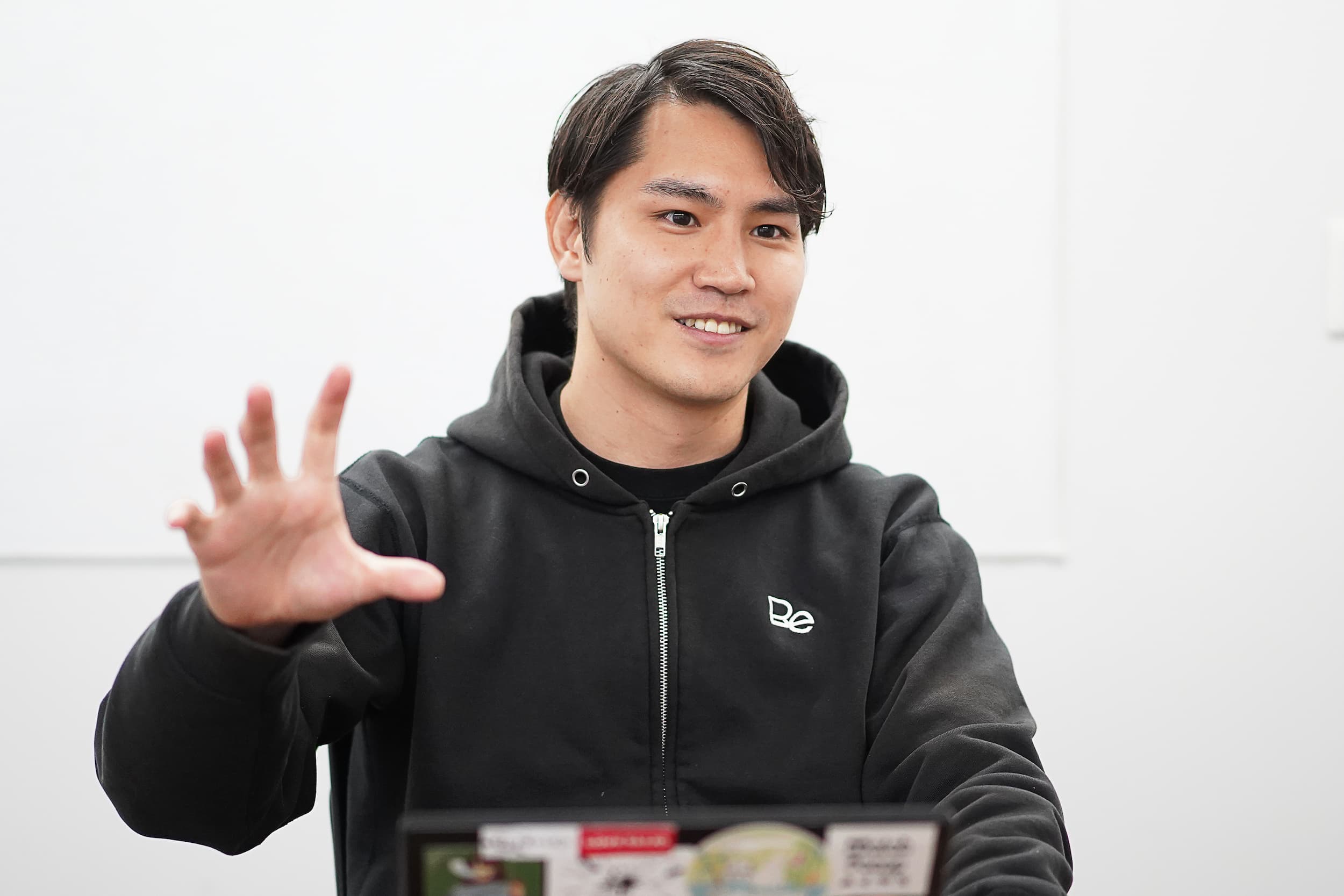
自治体から大学、研究機関まで。4領域体制で社会実装を加速
江頭
続いて、桶谷様が担っていらっしゃるチームの構成や特徴について教えてください。
桶谷様
私たちのチームは「ワンプール制」を採用していて、明確な部署分けはなく、案件ごとにメンバーが柔軟にアサインされる仕組みです。
案件のタイプとしては、以下の4つに大別されます。
・MO(Municipal Office):市町村向けプロジェクト
・AD(Administrative Division):都道府県向けプロジェクト
・RA(Research Administration):大学・高専など研究機関との取り組み
・PA(Public Affairs):官公庁や省庁との共同事業
メンバーは、それぞれ得意領域や専門性を持っており、すべてを網羅しているというよりも、特定の領域に強みを持つ人材が集まっています。
たとえばRA(大学・研究機関)では、博士号を持ち、研究開発と社会実装のギャップを深く理解したメンバーが活躍しています。AD(都道府県)では、戦略系ファーム出身者が都道府県の政策立案から実行支援までをリード。MO(市町村)では、VC出身者のファンド知見を生かし、地域密着型の事業作りを推進しています。そしてPA(官公庁)では、官僚出身のメンバーが国の施策と現場をつなぐような役割を担っています。
それぞれが専門性の「核」を持ちつつ、課題意識を共有し、徐々に他の領域にもスコープを広げていく。横断性と柔軟性を両立できる構造が、私たちの強みです。
江頭
ありがとうございます。アサインは、面接の段階で志向性や適性を確認されるのですね。
桶谷様
そうですね。履歴書や経歴からある程度見えてきますが、面接では「どんな社会課題に関心があるか」「私たちの目指す世界観に共感できるか」「変化の早い現場に向き合えるか」といった点を重視しています。特にパブリック領域は明確な“正解”がない分、向上心や自走力が求められます。そのため、志向性は非常に大事な評価ポイントですね。
江頭
チーム全体の年齢感や構成はいかがですか。
桶谷様
平均年齢は33〜34歳くらいです。構成としては、私の下にディレクターが1名、シニアマネジャーが3名、マネジャーが4〜5名、さらに複数のコンサルタントがいます。ピラミッド型というよりは、“しっかりした土台の上に屋根がある”ような安定感のある組織構造ですね。
「たけはらDX」で実現。‟総合格闘技で挑む地域イノベーション”
江頭
具体的な取り組み事例についてお聞きしてもよろしいでしょうか。
桶谷様
はい。MO(市町村)領域が中心になって取り組んだ、広島県竹原市で展開している「たけはらDX」はReGACYらしさが詰まったプロジェクトだと思います。
この取り組みで目指しているのは、地方における“産業クラスター”の創出です。たとえば竹原市では、「産業用廃熱のクリーン化」をテーマに、初年度は首都圏から有望なスタートアップや起業前の研究者など6組を招致しました。
ただ呼ぶだけでなく、地域の中小企業との協働体制=“座組”を組み、ReGACYのチームが実証や事業化に伴走します。事業が一定の成長段階に入った段階では、私たち自身が出資を行うこともあり、VCとしての役割も担っています。
目指すのは、いわば“○○といえばこの街”というような、新たな産業の中心地を地域に作ること。「スタートアップといえばシリコンバレーだ」とイメージされれば、投資家や研究者、事業者が自律的に集まり始める。そんな状態を育てていくのが、私たちの提供するMO領域のオファリングサービスです。
この構想の実現には、単なるコンサルティングではなく、事業開発(BizDev)やファイナンスといった多様な機能を統合した支援が不可欠です。だからこそ私たちは、地域振興に本気でコミットする“総合格闘技”のようなチームとして、現場に深く入り込んでいます。
江頭
他のアクセラレーターや新規事業支援と比べても、取り組みのスパンがとても長い印象を受けます。
桶谷様
おっしゃる通り、私たちのプロジェクトは時間軸が非常に長いのが特徴です。特に大きく分けて3つのフェーズがあります。
1つ目が“リード期間”です。これは実際に案件を立ち上げる前の準備段階で、市長や議会と丁寧に意見交換を行いながら、予算や戦略の整合性を取っていきます。合意形成に1年以上かかることもあり、単年度で売り上げを計上する一般的なコンサルファームでは対応が難しい領域です。
2つ目が、5年間のアクセラレーションフェーズです。スタートアップの誘致や事業開発に加え、必要に応じて出資も行います。VCとしての視点やファイナンス機能を生かし、単なる支援者ではなく、事業の当事者として地域産業の成長に伴走します。
3つ目が、6年目以降の自走フェーズです。ここでは地域ごとに特化型ファンドを組成・運用し、私たち自身が民間事業者として継続的に関与していく体制を構築します。こうしたファンドを柔軟に組成・運営できる組織は国内でも極めて限られています。
この3フェーズを一貫して担える体制を持つプレーヤーは少なく、コンペティションになることもほとんどありませんね。
江頭
ありがとうございます。ちなみにマネジャーや責任者の方の評価軸も、やはり短期ではなく長期視点になるのでしょうか。
桶谷様
おっしゃる通りです。プロジェクトオーナーに対して、「単年度で売り上げが上がっていない=評価が下がる」といった判断はしていません。中長期的な価値創出こそが私たちの軸であり、それは評価制度にも反映されています。

「志」と「手触り感」の両立こそが、キャリア選択の原動力に
江頭
ここまで、ReGACYの事業について伺ってきましたが、改めて、桶谷様ご自身がどのようなキャリアや経験を経て、現在の道にたどり着いたのかもぜひ教えていただけますか。
桶谷様
もともと東京都の出身で、幼少期はインドネシア・ジャカルタで過ごしました。大学を卒業してからは、大手の鉄鋼商社に入社して自動車メーカー向けの鉄鋼製品の取引や、投資先の経営管理などを担当していました。その後、独立系のVCやアクセラレーターにキャリアを移し、そこからスタートアップ支援や新規事業開発に関わるようになった、というのが大まかな流れです。
江頭
現在はパブリック領域を担当されていらっしゃいますが、その関心や視点はどのようにして生まれたのでしょうか。
桶谷様
パブリック領域への関心が芽生えたのは、社会人になってからNPO活動を通じて地方のリアルな課題と出会ったことがきっかけでした。たとえば、とある地域で出会ったのは、小学6年生でありながら弟妹の世話を担い、学校にも通えない女の子。子どもの貧困や不登校、ヤングケアラーといった問題が複雑に絡み合った現実を前に、強い無力感を覚えました。
インドネシアでの生活を通じて発展途上国の課題に触れてきた一方で、日本にも見えづらい“格差”が確かに存在する。そのギャップに直面した経験が、自分の中で「構造から社会を変えていくにはどうすればいいか」を考える原点になったと思います。
もちろん、NPOのような現場支援はとても重要で尊いものです。ただ、同時に「社会の仕組み」そのものに働きかける仕組みも必要だと感じました。そこで注目したのが、イノベーションとそれを支えるVCという手段です。経済性と社会性を両立しながら、構造課題に挑める。それが自分にとっての“志”と“手触り感”のどちらも実感できるアプローチではないかと。現在の仕事は、その思いを形にできるフィールドだと感じています。
共通点は“WILL”と“自走力”。多様なプロが集うパブリックセクター
江頭
採用についても伺いたいのですが、実際にご入社されて活躍されている方の背景や、ご自身として「こういう方に来てほしい」と思われている人物像について教えてください。
桶谷様
バックグラウンドでいえば、大きく3タイプに分かれます。コンサル出身者、官僚や自治体などパブリックセクター出身の方、そしてサイエンス系のバックグラウンドを持つ方です。
コンサル出身の方にとっては、絵を描くだけでなく、事業を実行や必要に応じた出資など、ファイナンスを含む一気通貫の支援に関われる点が魅力です。従来のパブリック系コンサルでは、ここまで踏み込むことが難しいため、そこに魅力を感じてジョインされる方が多いですね。
官僚や自治体出身の方には、「現場で手触り感のある政策実行に携わりたい」という思いを持っている方が多くいます。市長や町長と直接やりとりしながら、地域の産業振興を政策レベルから実装していくというプロセスは、現職では経験しにくい領域です。
そしてサイエンス系の方は、研究の社会実装に課題感を持っていることが多いです。研究開発をスタートアップとして形にし、さらに地域でスケールさせていく。その一連のプロセスに一人称で関われる点がエキサイティングだと感じていただいています。
江頭
まさにそれぞれの専門性が、社会実装というフィールドで生かされているのですね。では、パーソナルな観点で言うと、どういった方に来てほしいですか。
桶谷様
一言で言えば、「WILLがある人」です。言語化しきれていなくても構わないので、「こういう社会を実現したい」というビジョンや問いを強く持っている方。私たちは60人規模の組織で、手厚いOJTやキャリア支援制度は、まだこれから整えていく段階です。だからこそ、自分の軸を持って自ら動けるセルフスターターであることが大切だと考えています。
たとえば、「たけはらモデル」のような取り組みはスケールも意義も大きいですが、その分、現場は決して楽ではありません。本気で社会に変化を起こそうとするなら、挑戦し続ける意思が必要です。ぜひ、そうした“WILL”を持った方と一緒に挑戦していきたいですね。
江頭
なるほど。やはり自走力が問われるのですね。組織のカルチャーや雰囲気はいかがですか。
桶谷様
私はたまに厳しいフィードバックをすることもあるので、少し“怖い”と思われているかもしれませんが(笑)、だからこそメンバー同士の結束が強いです。「次、頑張ろう」とフォローし合う雰囲気がありますし、役職や年齢に関係なくフラットなカルチャーなので、風通しは良いチームだと思います。
江頭
働き方についても伺えますか?出張や在宅勤務のスタイルなどは。
桶谷様
出張は月に1~2回ほどですね。毎週月曜のみ出社で、その他は在宅勤務がベースです。ただ、地方案件に深く関わっているメンバーの中には、現地に入り浸っている人もいれば、小さなお子さんがいる方などは必要に応じて出張ベースで調整するなど、ライフスタイルに合わせて柔軟に働いています。

「出る杭は引き上げる」。挑戦する人に最大のリターンを
江頭
これまでのお話から、御社では個々の思いや自走力を重視されていることが伝わってきました。そうした中で、評価制度はどのような方針なのでしょうか。
桶谷様
われわれは“完全実力主義”を採用しています。成果を出せば年次や年齢に関係なく評価されますし、逆に成果が出なければ、ポジションが見直されることもあります。たとえば、2年前にアソシエイトだったメンバーが、現在はシニアマネジャーに昇進していたり、スピード感のある昇格もあったりします。
評価は半年ごとに実施され、1回で2段階昇格することもあります。一方で、シニアマネジャーがマネジャーに戻るようなケースも珍しくありません。昇格・降格を通じて、個々に合ったフェーズで活躍していただく、というのが私たちの考え方です。
江頭
なるほど。その評価は、売り上げなどの指標で判断されるのですか?
桶谷様
その点も弊社ならではかもしれません。よく「マネジャー以上になると売り上げが求められるのでは」と思われがちですが、弊社で“売り上げ責任”を明確に持つのはディレクター以上です。
マネジャーやシニアマネジャーはあくまで、「プロジェクトの品質と価値をいかに高められるか」が評価基準になります。つまり、現場でいかに価値あるデリバリーができているか、社会にどれだけのインパクトを与えられているか、という点を重視しています。
江頭
評価がストレートに年収にも反映されるのですか。
桶谷様
そうですね。たとえば、入社時年収が500万円だったメンバーが、2年後には1300万円になったケースもあります。私たちは営業で売り上げを作るわけではないので、知識や思考力を積み上げることで、ちゃんと上がっていける仕組みになっています。
江頭
ポジションアップのチャンスもまだまだあるのでしょうか。
桶谷様
あります。現状、MO・AD・RA・PAの4領域すべてを私が統括していますが、それぞれに執行役員を立てていく構想があります。つまり、今まさにそのポストが空いている状態です。新しい役割を担うチャンスは、これからたくさん出てくるはずです。
江頭
ありがとうございます。最後に、これから応募を考える方へのメッセージをお願いできますか。
桶谷様
あまり気負わずにお伝えすると、「こういう社会を実現したい」という思いや問いを持っている方と、一緒に挑戦していきたいと思っています。その思いを、ただの理想で終わらせずに、事業として、仕組みとして形にしていける場所がReGACYです。
社会の構造に手をかけながら、自分自身の成長も実感できる。そんなフィールドを一緒に広げていけたらうれしいですね。

筑波大学大学院 人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究群 経営学学位プログラム修了 (経営システム科学)
新卒では国内最大手の鉄鋼商社であるMetal Oneに入社。特殊鋼関連の事業部に所属し、自動車部品サプライヤー向け輸出入や投資先の経営管理に従事。
次に、独立系VCであるGLOBISのコンサルティングチームに転職。新規事業やスタートアップのバリューアップ、全社戦略・組織戦略の構築、取締役会の設計などのコンサルティングに取り組む。
その後、独立系VCのサムライインキュベートへ入社。製薬企業、地方自治体、中央官公庁、大学等のプロジェクトを中心に従事する。
2022年にReGACY社へ転身。執行役員としてPublic Sector & Government Groupを立ち上げ後、様々な自治体のイノベーション施策の企画・運営や、創薬・バイオを主とした大学発スタートアップの起業支援に従事。

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
ReGACY Innovation Group株式会社の求人情報
| 募集職種 | パブリックセクター&ガバメントグループ |
|---|---|
| 職務内容 | 【ディレクター】 【シニアマネージャー/マネージャー】 【コンサルタント/アソシエイト】 ・プロジェクトの推進に向けた各種作業(報告資料の作成、議事録の作成等) ・個別のプログラム(オープンイノベーション、研究シーズの事業化等)に対する、スタートアップや地域企業、大学研究者等への伴走支援 |
| 応募要件 | <必須スキル> 【シニアマネージャー/マネージャー】 【コンサルタント/アソシエイト】 <歓迎スキル> 【コンサルタント/アソシエイト】 <求める人物像> |