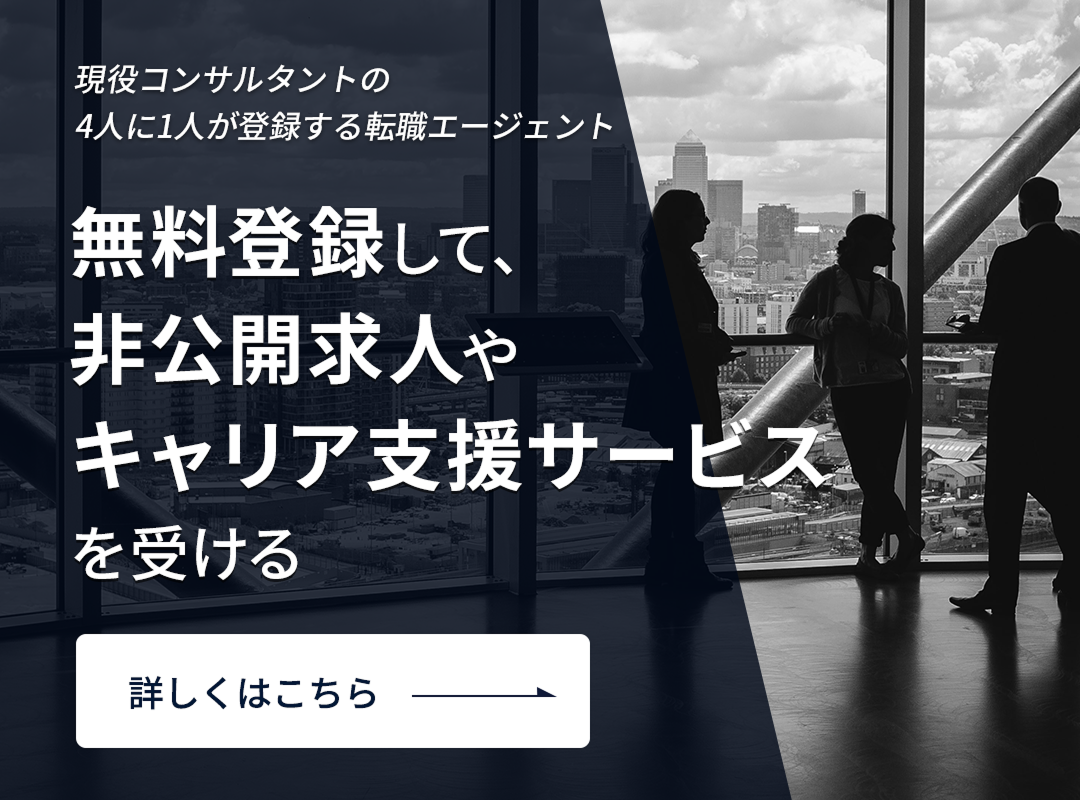ちゅうぎんフィナンシャルグループ インタビュー/次なる一手「BPOサービス」で地域経済を支える。コンサルティングからビジネスプロデューサーへ

2022年10月、中国銀行は、「金融を中心とした総合サービス業」を目指し、また地域へ新たな価値を創出する組織へ進化するため、持株会社体制へ移行しました。持株会社となった「ちゅうぎんフィナンシャルグループ」では、これまで以上にお客さまのニーズや課題に対応するため「業務軸の拡大」を主要戦略に掲げています。
この施策の一環として、2022年9月に株式会社Cキューブ・コンサルティング(Cキューブ)を設立しました。前回2022年8月のインタビューではその設立構想を伺いましたが、それから約2年半が経過した今、Cキューブは、着実に成長を遂げており、地域企業のDX支援や経営戦略の立案に加え、幅広い地域連携も実現し、地域経済の活性化に貢献しています。
今回は、ちゅうぎんフィナンシャルグループ イノベーション推進部長 白神賢治様と、Cキューブ・コンサルティング シニアマネージャー 力武裕様に、持株会社体制移行後の中期経営計画の進捗や組織変革の取り組み、そして、Cキューブ・コンサルティングの「ビジネスプロデューサー」としての新たな挑戦についてお話を伺いました。
※2025年3月時点での情報です
Index
長期経営計画「Vision2027 未来共創プラン」の進捗や持株会社体制での「業務軸の拡大」について—Cキューブ設立2年半で実現した地域企業との価値共創
竹本
前回のインタビューから約2年半が経過しましたが、あらためて「未来共創プラン」の進捗と現在の取り組みについて教えていただけますか。
白神様
「Vision2027 未来共創プラン」は、ちゅうぎんグループが2017年に策定した長期経営計画です。「地域・お客さま・従業員と分かち合える豊かな未来を共創する」というビジョンを掲げています。
背景には、マイナス金利政策の長期化により、厳しい経営環境に打ち克ち、持続可能なビジネスモデルの構築を目指すという目的がありました。
最初の3年間は構造改革に取り組み、業務の効率化や事業モデルの見直しを進めました。一時的に業績が低下していましたが、その後安定的な成長を続けています。また、業務軸を拡大させ、新たなサービスの提供も可能になっています。
※参考:「DX・SXコンサルティング×銀行グループで新たな地方創生モデルを!!」中国銀行がDX・SXを中心ソリューションとする戦略系コンサルティングファームを新設/代表取締役専務 寺坂幸治様、新規事業開発センター長 白神賢治様 インタビュー
https://insight.axc.ne.jp/article/company/3068/
竹本
計画を進める中で、想定外の課題はありましたか。
白神様
デジタル化やテクノロジーの進展が予想以上に速かったことです。そのため、昨年2024年5月に「ちゅうぎんDX戦略」を策定し、外部環境の変化に対応しています。
また、地方と首都圏のデジタル格差が拡大していることも大きな課題と感じています。首都圏ではAI活用やクラウド化が急速に進んでいたのに対し、地方では、「何をすべきかわからない」といった声もあり、対応は遅れがちでした。こうした状況を踏まえ、Cキューブ・コンサルティングや中国銀行のコンサルティング営業部でDX推進を行っているところです。
竹本
あらためて、Cキューブ設立の意図を教えてください。
白神様
Cキューブは、「Chugin (ちゅうぎん)」「Community(地域社会)」「Co-Creation(共創)」の3つのCを掛け合わせ、より大きな相乗効果を生み出すことを目的としたコンサルティングファームです。経営戦略の立案からDX戦略、サステナビリティ支援まで行い、地域企業の発展に貢献することを目指しています。
竹本
具体的な案件について教えてください。
白神様
たとえば、岡山県北部の林業再生プロジェクトでは、地域の林業関係者や地元企業、自治体と連携し「村の林業をどうしていくか」という根本的な課題から共に考え、実行計画の策定まで支援しています。地域課題を具体的に解決することは、従来の銀行だけでは手が届きにくい領域ですが、Cキューブはこうした案件の上流部分からもパートナーとして選ばれるようになってきています。

竹本
ちゅうぎんフィナンシャルグループとしてのネットワークを活用できる点もCキューブの強みですね。
力武様
その通りです。仮に銀行とのつながりがないまま当地で新規にコンサルティングファームを立ち上げても、ビジネスとして成立させることは難しかったと思います。しかし、中国銀行には、さまざまな業種の大企業から中堅・中小企業まで、東瀬戸内の広域にわたる取引ネットワークがあります。
さらに、それぞれの顧客が抱える課題や、経営者の悩みが交渉履歴として蓄積されているため、そうした情報を基に顧客へアプローチできることも大きな強みですね。
竹本
一方で、地方では「コンサルティング」という言葉にアレルギーを持つ企業も少なくないと思いますが、その点はいかがですか。
力武様
確かに、コンサルティング業界に対して「口だけで実行が伴わない」という印象を持つお客さまもいます。しかし、私たちはちゅうぎんフィナンシャルグループの一員であり、提案した施策が実行できなければ、その責任が伴う立場です。
そのため、Cキューブでは実現性・実効性の高い戦略を策定することはもちろん、DXやサステナビリティなど実行支援まで一貫して行うことで、従来のコンサルのイメージを払拭しています。「絵に描いた餅」で終わらせるのではなく、実際にお客さまと伴走しながら変革の支援を行っている点が高く評価されていると感じています。
竹本
今までにない新しい支援モデルが生まれているわけですね。
白神様
そうですね。地域課題を解決する新しいモデルと捉えていただき、問い合わせもあります。
また、大手コンサルティングファームではサービス単価が合わず、一部の企業しか利用できない状況かと思います。その点、Cキューブでは「適正なフィーを維持しつつ、地域企業にとって本当に価値のあるサービスを提供する」ことを目指しており、そこが他社との差別化のポイントの1つになっていると思います。収益だけでなく、持続可能な地域社会に貢献することが、地域に根ざした弊社グループにとって重要なポイントになります。
「出島」が変革の起点へ—Cキューブが浸透させる新たな銀行文化
竹本
Cキューブが主導する形で企業との共創が進むことで、立ち上げの段階から大きな価値を生み出していると感じます。今後、こうした成果をどのようにグループ全体に還元し、発展させていくことを考えていますか。
力武様
まさに現在進行形で進めていることですね。実際に成果も出始めていて、特にこれまで銀行が十分にアプローチできていなかった企業、つまり預金はあるが融資に至っていない企業への支援も広げています。
Cキューブは、そうした企業の経営者の壁打ち相手として、事業の成長戦略や投資の方向性を一緒に考える役割を担っています。
たとえば、
・売上成長に向けて、新たな収益の柱に対する投資方針を明確にする
・サプライチェーン改革を行い、新たな工場や物流センター開設の検討を進める
こうした戦略を共に練ることで、銀行としても適切な融資判断が可能になり、必要に応じて「ちゅうぎんヒューマンイノベーションズ」による経営人材の紹介や、「ちゅうぎんキャピタルパートナーズ」による投資支援につなげられます。現在、ちゅうぎんフィナンシャルグループ全体として、こうしたEnd to Endの支援体制を構築しているところです。

竹本
Cキューブでは、銀行とは異なるバックグラウンドを持つ多様な人材が集まり、銀行文化に新たな風を吹き込んでいます。実際、銀行グループ全体にどのような影響をもたらしていると感じますか。
白神様
1つの大きなポイントは、Cキューブが「出島」として機能していることです。Cキューブは、銀行という大きな組織の中にポンと異質な要素を持ち込み、化学反応を起こしていると思います。
竹本
一方で、いわゆる「抵抗勢力」のようなものもあるのでしょうか。
白神様
DX支援をいただいた当初は、私の部下もCキューブメンバーについていけず、苦労していましたが、徐々にお互いの距離は近くなってきたと思います。 Cキューブの存在が次第に受け入れられ、実際にDXを協業で進める中で、プロジェクトがうまく機能してきたと思います。
力武様
Cキューブのメンバー構成としては、約6割がコンサルティングファーム出身、3割が銀行からの出向者、1割が事業会社出身者です。銀行から来た出向者は、いずれグループに戻るわけですが、Cキューブでの経験を生かして、銀行の評価制度や組織文化の改善を進めることで、少しずつ変化が生まれます。こうした変革の積み重ねが、銀行全体のカルチャーをアップデートしていくわけです。
竹本
つまり、Cキューブが銀行のカルチャーを変える起点になりつつあるということですね。
白神様
そうなってほしいと思います。他のグループ会社もそうですが、中途で働くメンバーが組織内で活躍することが、グループ全体のダイバーシティーや成長や発展にもつながると思います。
竹本
これからますます面白い展開になりそうですね。
白神様
そうですね。銀行としても、デジタルやテクノロジーの活用を単なるオプションとしてではなく、企業文化の一部として取り入れる必要があると考えています。その変革の先導役として、Cキューブの存在価値は高まると思います。
地域企業の人手不足が深刻化、BPOサービスで企業を支援
竹本
今回、新たに「BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービス」を立ち上げられたとのことですが、その背景にはどのような経緯があったのでしょうか。
白神様
地域企業のお客さまと話す中で、5〜10年先の人材不足が深刻化することが見えてきました。特に総務、経理、人事などの間接業務に人材を割く余裕がないという多くの声を聞きます。また、デジタル化の進展に伴い、データ分析やセキュリティ強化といった新たな課題が発生し、企業単独で対応が難しくなっている状況です。
そこで、銀行が持つ事務の正確性やセキュリティに対する信頼を生かし、企業のバックオフィス業務の一部を受託することで、企業が“コア業務”に集中できる環境を整えたいと考えています。
BPOは単なる事務のアウトソースではなく、Cキューブのコンサルティング機能とも連携し、業務効率化や付加価値を支援する仕組みです。企業の成長を後押しし、地域経済全体の発展を目指しています。
竹本
つまり、銀行グループが企業のノンコア業務を担うことで、人材不足の解決を図るということですね。BPOの導入にあたり、どのような課題がありましたか。
白神様
BPOは一見シンプルに見えますが、実際に業務を切り出して運営するのは容易ではありません。たとえば経理業務1つとっても、どこまでをアウトソースするのか、意思決定に関わる部分はどのように管理するのかなど、詳細な調整が求められます。
また、専門性の高い人材の確保も課題です。現在は適切な人材を迎え、試行錯誤を重ねながらサービスを構築しています。デジタル活用を組み合わせることで、より価値のある支援を目指しています。
竹本
今後、BPO事業をどのように展開していく予定でしょうか。
白神様
まずは、ちゅうぎんフィナンシャルグループの子会社の間接業務の集約、いわゆるシェアードサービスセンター機能の構築から進めていきたいと思います。徐々に集約化する事務を拡大させて、BPO事業の骨格を作りたいと考えています。
その後、地域のお客さまの業務の一部を受託するようにしたいと思います。さらに、サイバーセキュリティやマーケティングといった地域のお客さまが単独で業務を行うには負担の大きい分野もご支援できればと感じています。将来的には、BPOを地域企業の成長を支えるインフラとして位置づけたいと考えています。銀行には金融機関としての信頼とネットワークがありますので、それを活用し、企業が安心して業務を委託できる仕組み作りを進めていきたいです。
竹本
一方、ちゅうぎんフィナンシャルグループ内でどのような位置づけになるのでしょうか。
白神様
昨今のデジタル化の進展により、銀行内の単純作業が減る中で、行員には企画や営業など、より付加価値の高い業務への適応が求められています。しかし、事務が得意な行員も多く、そうした方々がそのスキルを生かせる場としてBPOが機能するのではないかと考えています。
外部企業の業務を受託することでBPO自体が収益の柱となりますが、銀行グループ全体で、それぞれの適正や能力に合わせて幅広い働き方できるという面でも、貢献度は高いと思います。
挑戦を後押しする経営方針が「地域の総合商社」に進化
竹本
BPOサービスによって銀行はこれまでにない形で企業を支援できるようになってきたということですね。一方で、「お客さまと共に成長する」という理念を掲げる銀行は多いですが、実際に成果を出せる銀行とそうでない銀行には、どのような違いがあるとお考えですか。
白神様
新しいサービスを生み出すのは決して簡単なことではありません。私たちも最初から順調だったわけではなく、正直、手探りの状態です。
そこで導入したのが「オープンラボ」という仕組みです。社員が自由に新規ビジネスを提案し、実際に事業として形にするところまでを視野に入れています。結果として、ここから3~4案件が立ち上がり、そのうち2社では提案者がそのまま事業推進に関わっています。
この仕組みのポイントは、提案者自身が主体となって実装できる点です。成功すればもちろんのこと、仮に失敗したとしても次の挑戦につながる。銀行業界のように安定性を重視する環境では、どうしても新規事業へのハードルが高くなりがちですが、こうした仕組みがあることで挑戦しやすい土壌が整ってきていると思います。
竹本
オープンイノベーションを掲げる企業が多い中で、御行でそれが実際に機能している理由は何でしょうか。
白神様
グループスローガンである「やってみよう」にあるように、挑戦することを重要視する経営方針があると思います。「新しい価値を生み出すために、既存の枠にとらわれない」という姿勢を徹底していることが、挑戦を可能にしていると思います。
竹本
金融機関としての基盤を生かしつつ、多様な事業展開が新入社員や外部人材にとってどのような成長機会やメリットをもたらすのでしょうか。
白神様
当社の事業領域は従来の金融機関の枠を超えて、「地域の総合商社」的なポジションになりつつあると思います。グループ内には、ベンチャーキャピタル(VC)、コンサルティング、融資、人材紹介、エネルギーといった多用な事業があり、幅広い事業を経験する素地があります。
つまり、一般的な金融機関では得られない幅広い視点を身につけながら、自分の関心や適性に合ったキャリアを模索できる環境が整っているのです。「金融業に興味があるけれど、経営や新規事業にも関わりたい」といった人にとっては、非常に魅力的な環境だと思います。
竹本
企業成長を支えるさまざまなパーツを学べる環境が強みということですね。
白神様
その通りです。加えて、岡山は産学官金の連携が強く、自治体・大学・経済団体とのつながりも深いため、新たな事業を生み出しやすい素地があります。自社グループの多様な機能と、この地域ならではの環境を掛け合わせることで、地域経済に貢献しながら事業成長を最大化できるのが強みだと思います。

「地方創生の新たなモデルを作る」という強い意志を持つメンバーが、組織の核となっている
竹本
続いて、Cキューブが中途採用や中途人材を受け入れる際に、特に重視している点について教えていただけますか。
白神様
専門性は当然求めますが、それ以上に「学び続ける姿勢」や「地域を良くしたいという思い」も大切です。地域に根ざした仕事は、地道な業務も多いため、本気で地域企業の成長を支えたいと考えられる人でないと続けるのは難しいですね。
竹本
実際、地域への思いを持つ方は地方出身者が多いのでしょうか。
力武様
Cキューブでは地方出身者が多いです。一度東京で経験を積み、その知見を地域に還元したいと考えて戻ってくるケースが目立ちます。私自身も、九州出身で大学進学を機に上京し、コンサルティングファームで10年以上働く中で、地方に関わる仕事を模索してCキューブに出会いました。
白神様
「地域に貢献したい」という強い気持ちを持っている人が、組織を支える核になってくると思います。
竹本
Cキューブで求めるスキルやスタンスにはどのような特徴がありますか。
力武様
一般的なコンサルティングファームでは、お客さまがコンサルファームに依頼したいことがある程度明確で、プロジェクトのゴールが最初から決まっていることが多いです。一方、地方の中堅・中小企業ではそもそも経営者と対話しながら「何をゴールにすべきか」から考え、ピン留めするところから関わることが必要です。決められた枠組みで動くのではなく、不確実な状況下で試行錯誤しながら新しい価値を生み出す人材を求めています。
また、現在業務委託の方は地方の大規模案件を支援する役割が中心ですが、今後は中小規模の案件でも顧問的に入っていただくことや、弊社自体の事業成長にも関わっていただくことも可能性として考えています。副業の方を含め、「Cキューブに関わっていただいたからこそできる仕事」を増やしていきたいですね。
竹本
与えられた仕事をこなすのではなく、事業の立ち上げや成長に主体的に関わることが求められるということですね。
力武様
その通りです。Cキューブでは、決まったフォーマットや型がほとんどありません。そのため、自ら考え、主体的に動ける人材が活躍しやすい環境です。

竹本
新規事業を進める中で、特に求める人材の特性に違いはありますか。
白神様
イノベーション推進部は、新しい価値を創出し、未来の事業を形にする役割を担っています。そのため自ら機会を見つけ、ゼロから事業を生み出すことに挑戦できる起業家マインドが欠かせません。
また、今後はデータサイエンティストなどの専門職も重要になってきますが、地域における活用モデルはまだ確立されていません。そのため、 首都圏の専門人材と地域をつなぎ、ノウハウを共有しながら、新しいビジネスの「型」を作れる人材を求めています。
竹本
地域の課題を理解し、それを実際のビジネスとして形にする力が求められているのですね。
力武様
その通りです。Cキューブの環境では、経営者と直接向き合いながら課題を解き、ビジネスを成長していく手触り感を感じられることも魅力です。新しい挑戦を楽しみながら、地域の成長に貢献できる人に、ぜひ関わってほしいですね。
コンサルタントではなく、地域経済を動かす「ビジネスプロデューサー」としての新しいあり方
竹本
Cキューブは現在30人規模ですが、組織としての成長や今後の展望についてどのようにお考えでしょうか。
力武様
「30人の壁」とも言われるように、組織が一定の規模に達すると、スピード感を維持しつつ安定した運営が求められます。
たとえば、これまでは イノベーター型の人材が組織をけん引してきましたが、今後は組織の安定や成長を支える仕組みを作る人材も必要になります。新しいメンバーと既存メンバーが融合するフェーズに入っており、価値観や働き方の違いをどう統合するかが重要になっています。
竹本
このフェーズにおいて、組織のDNAやカルチャーをどう受け継いでいくかも大切ですね。
力武様
まさにそこが悩みどころです。Cキューブのビジョンや理念を維持しながら、新しい人材を迎え、組織を進化させる必要があります。
竹本
現在のCキューブの組織体制はどのようになっていますか。
力武様
現在は、地域企業の課題に幅広く対応するために、あえて業界別・機能別の組織にはしていません。ただ、成長フェーズに入る中でさらなるナレッジの蓄積やチーム運営の工夫が必要になってきています。
また、これまでの「コンサルタント」という枠組みを超えて、「ビジネスプロデューサー」という新しい役割も求められるようになりました。企業同士をつないで新たなビジネスを生み出すことや、産官学金で連携し地域課題を解いていくことも必要になっています。
このような役割を私たちが確立できれば、非常に画期的なことだと思います。
竹本
銀行グループの枠を超えたビジネス創出の視点は、まさにCキューブならではの価値ですね。
白神様
その通りです。これまでは銀行業務の延長としての支援が中心でしたが、今後は地域の経済全体を視野に入れ、新しいビジネスや産業を生み出すことも必要だと思います。
まだまだ道半ばですが、「新しい価値を生み出し続ける組織」として、地域の可能性を広げ、企業の成長を支える存在でありたいと考えています。
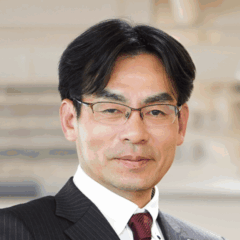
1999年に中国銀行に入行し、融資部 経営改善サポートセンター、R&C(リサーチ&コンサルティング)センター、西日本豪雨災害復興支援センターに従事、そのほか、岡山大学でMBAを取得するなど、多岐にわたる経験を積む。2019年からは総合企画部で中期経営計画策定プロジェクトや地方創生SDGs・新規事業開発プロジェクトを担当。2021年には総合企画部 新規事業開発センター長に就任し、2022年にはちゅうぎんFG 経営企画部 新規事業開発センター長、同年12月にはちゅうぎんFG 経営企画部 副部長を歴任。2024年6月より現職のちゅうぎんFG イノベーション推進部長として、中銀グループおよび地域のイノベーション推進に尽力する。
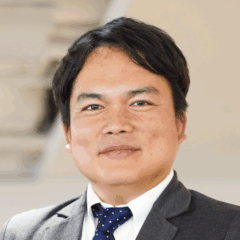
大手日系コンサルティングファーム、大手外資系コンサルティングファームを経て、2022年Cキューブ・コンサルティング創立のタイミングで参画。製造業を中心としたクライアントに対し、全社構造改革の構想策定~実行を支援。特に、経営管理高度化を目的とした大規模ERP導入や間接業務BPR、SCM改革、調達コスト削減、AIを活用したオペレーション効率化、全社DX推進の伴走支援(推進スキーム構築、チェンジマネジメント)など、プロジェクト経験多数。
Cキューブ・コンサルティングでは、製造業や建設業に対するDXビジョン策定~実行支援、経営管理高度化、金融機関に対するDX戦略策定~BPR支援など複数プロジェクトを推進。
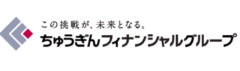
ちゅうぎんフィナンシャルグループ(FG)は、岡山県岡山市に本店を置く中国銀行を中心とする総合金融グループです。中国銀行は⾧い歴史の中で、数多くの地域の銀行との合併により成⾧しており、東瀬戸内経済圏の6県(岡山県、広島県、香川県、兵庫県、愛媛県、鳥取県)に拠点を有する広域地銀。同経済圏において強固な顧客基盤を構築している。
2022年に「金融を中心とした総合サービス業」を目指し、地域に新たな価値を創出するために持株会社体制へと移行しました。これにより、従来の金融サービスに留まらず、総合的なサービスを提供しています。
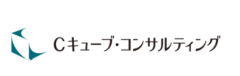
当社は、2022年9月1日に株式会社中国銀行の子会社として設立され、事業を開始しました。お客さま・地域が直面する複雑な課題に正面から向き合い、 DX/SXをはじめとした解決策のご提案や、実現に向けた伴走支援などの各種コンサルティングサービスを提供しています。

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
株式会社Cキューブ・コンサルティングの求人情報
| 募集職種 | 株式会社Cキューブ・コンサルティング立ち上げスタートアップメンバー |
|---|---|
| 職務内容 | 【担当業界】 【担当領域】 |
| 応募要件 | <求めるご経験> <求める資質> |
| ※掲載求人(フリーランス) | 案件概要:業務課題に対してRPAやAI等のソリューションを活用してDXを推進・実行 |
| 人材要件 | 必須要件: 尚可要件: 【期間】ASAP~ |