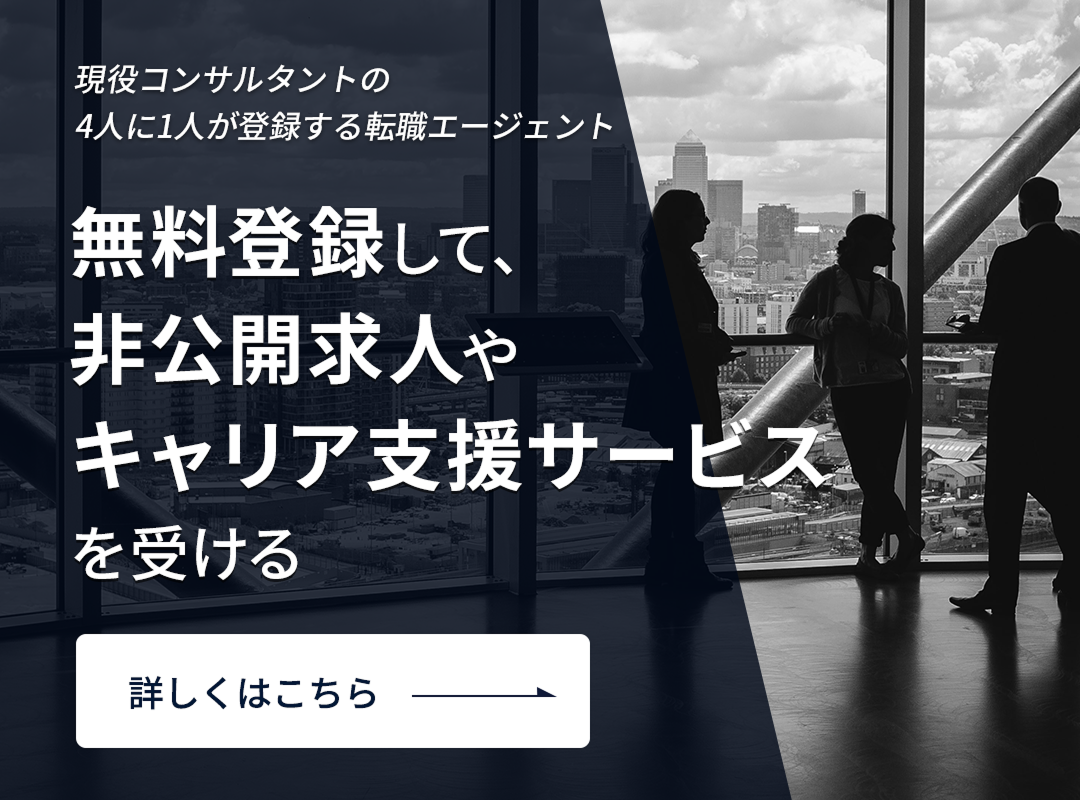キャディ株式会社 インタビュー/マッキンゼー出身CHRO が語る、累計エクイティ調達額257.3億円のキャディが仕掛ける製造業変革の全貌

キャディ株式会社は、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、製造業向けAIデータプラットフォーム事業を展開するスタートアップ企業です。2017年の創業以来、累計エクイティ調達額約257.3億円の資金調達を実現し、製造業AIデータプラットフォームCADDiはT2D3を大幅に超える急成長を遂げています。
現在はSUBARU、川崎重工業など日本を代表する大手製造業への導入が進み、日本、ベトナム、タイ、アメリカの4カ国・700名超の体制でグローバル展開を加速。数千兆円規模の世界製造業市場への挑戦を本格化させています。
今回は、マッキンゼー出身の創業メンバー、2024年10月に部門執行役員 JapanCHROへ就任された幸松大喜様に、急成長を支える組織戦略、製造業×AIの可能性、そして現在注力する「ソリューション本部」で募集している「Enterprise BizDev」の人材要件について詳しくお聞きしました。
Index
キャディ創業メンバーCHRO・幸松氏 。マッキンゼー出身、3カ月町工場で“ネジの穴”をあけ続けた現場経験も
佐藤
まずは、キャディについて教えていただけますか。
幸松様
キャディは2017年に創業した製造業向けのスタートアップです。現在は日本、アメリカ、タイ、ベトナムの4カ国に拠点を構え、グローバルで約700名のメンバーが在籍しています。
資金調達は累計エクイティ調達額で約257.3億円に達しており、2025年にはシリーズCエクステンションラウンドにて91億円(エクイティ40億円、デッドファイナンス51億円)を調達しました。リード投資家には欧州のグロースファンドAtomicoを迎え、海外の投資家からも高い評価をいただいております。
現在は、製造業のデータを活用したSaaS型のAIデータプラットフォーム事業を主軸としています。事業の詳細は後ほどご紹介しますが、すでに日本を代表する大手製造業への導入が進んでおり、着実な成果を上げています。
佐藤
幸松様のご経歴を教えてください。
幸松様
2014年に大学を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社しました。約4年間在籍し、マネジャーとして主に半導体製造装置メーカーや自動車メーカーを対象に、SCM(サプライチェーン・マネジメント)やオペレーション領域のコンサルティングに携わってきました。
キャディには、マッキンゼー時代の同期である加藤(現CEO)と、スタンフォード大学を飛び級で卒業し、Apple本社でプロダクト開発リードを務めていた小橋(現CTO)が創業したタイミングで、3人目のメンバーとして参画しています。
佐藤
スタートアップへの転身には、どのような思いがあったのでしょうか。
幸松様
「産業全体にインパクトを与える仕事がしたい」という思いがあったからです。コンサルティングの仕事は非常に刺激的でしたが、より手触り感のある現場に立ち、モノづくりの本質に触れながら課題を解きたいと感じていました。
その決意を自ら確かめるために、キャディ入社前に、町工場で3カ月間、無償でネジの穴をひたすらあけるという現場体験を積みました。実際に現場に身を置くことで、製造業の構造的な課題や現場の知恵に触れられたことは、今の自分の意思決定にも大きく影響しています。
2024年10月からは部門執行役員 JapanCHRO(最高人事責任者)に就任し、組織づくりや人材戦略にもさらに力を注いでいます。

「製造業」という構造的チャンス×ブレない戦略がキャディ急成長の後押しに
佐藤
キャディの事業領域である製造業について教えてください。
幸松様
製造業は、私たちの暮らしを支えるインフラのような存在です。スマートフォンをはじめ、身の回りのほとんどのモノは製造業によって生み出されている。日本では名目GDPの約2割を占めますが、グローバル全体で見ると日本の製造業が占める割合はおよそ5%。一方、グローバルでは数千兆円という巨大な市場が広がっており、まさに世界を動かす巨大産業とも言えますね。
佐藤
そんな巨大市場に、キャディはどのように切り込んでいったのですか。
幸松様
キャディは創業当初、発注者と中小の加工会社をマッチングする「CADDi Manufacturing」という事業(以降、Manufacturing事業)からスタートしました。自動見積もり技術を活用し、価格・納期・品質までを一気通貫で支援する、部品調達のプラットフォームです。
そして、AIが注目を集め始める前、2022年にリリースしたソフトウエア事業が「CADDi Drawer」です。図面などの製造業のあらゆるデータを活用して原価低減や業務効率化を支援するこのプロダクトは、ユーザーからの高い支持を受け、T2D3を大幅に超える急成長を遂げてきました。
その勢いを背景に、構造変革をより早く実現するため2024年7月には従来のManufacturing事業を「製造業AIデータプラットフォーム」事業に統合・一本化。データを起点としたプロダクトを軸に、より広く、より深く製造業全体の変革に挑んでいます。
佐藤
急拡大できた背景をもう少し詳しく教えてください。
幸松様
背景には2つの要素があります。
1つは市場の構造です。製造業はプレーヤーの数が非常に多く、非効率も多く残っています。それにもかかわらず、製造業の深い理解とプロダクト開発の両方を持っている企業はこれまで存在していなかった。そこに、私たちはチャンスを見いだすことができたのです。
2つ目は、創業初期から積み重ねてきた認知です。創業当初から大手企業向けにManufacturing事業を展開していたことで、経営層や業界のキーパーソンとの接点ができ、信頼を得られたことが事業拡大のベースになったと思います。
佐藤
創業メンバーの優秀さも、成長を支えた大きな要因ではないでしょうか。
幸松様
ありがとうございます。そう言っていただくと少々照れくさいのですが(笑)、私自身は2つの側面があると思います。
1つは、長期的なビジョンを信じて、ずっとブレずに走り続けてきたこと。創業当時は、「ソフトウエアで製造業を自動化するなんて無理だ」と言われることも少なくありませんでした。しかし、それでも信じ続けてきた。自分たちならできるという、信念を持ち続けているんです。
もう1つは、志の高い仲間が集まってくれていること。キャディは“優秀な集団”だと言っていただくこともありますが、私が本当にすごいと感じているのは“やり切る力”です。地に足をつけて行動し続ける実行力があるからこそ、ここまでの成長が実現できていると感じます。
佐藤
組織もかなり大きくなってきていますよね。
幸松様
おかげさまで組織の拡大も含めて、私たちは常にスケールの大きなチャレンジに挑み続けています。
「年間で何兆円、何十兆円の事業を生み出す」といった、通常なら非現実的に聞こえるような目標であっても本気で掲げ、具体的な四半期KPIにまで分解し、日々のアクションに落とし込んでいます。「どうすればできるか?」を全員が本気で考える。そんな前向きな思考と熱量が、キャディのカルチャーそのものだと思っています。
佐藤
今後の事業拡大について、どのような戦略を考えていますか。
幸松様
戦略は大きく2軸あります。1つ目は「新規導入社数の拡大」です。現在、キャディのプロダクトを導入されている大手企業は着々と増えていっていますが、まだ多くのホワイトスペースが残されています。
加えて、私たちが注目しているのがアメリカ市場です。日本では、ソフトウエアが占める市場構成比は全体の約7〜8%ですが、アメリカでは50%を超えるとも言われており、ソフトウエアに対する需要そのものが桁違いです。つまり、アメリカに行くだけで7倍近い市場があるということです。
この大きなチャンスを捉えるために、キャディではCEOの加藤が現地に移住し、本格的な展開を進めています。今後はアメリカに加えて、ヨーロッパやインドといった他の有力市場にも順次展開していく方針です。
もう1つは「1社あたりの提供価値最大化」です。たとえば川崎重工業様では、最初は車両カンパニーでの導入でしたが、今ではロボット部門にも広がっています。
キャディのプロダクトは、設計・調達・生産・品質など複数部門で使えるため、部署が広がれば自然とユースケースも増え、利用者数も伸びる。そうすることで、1社あたりの価値提供が広がり、結果として単価向上につながっていくのです。だからこそ、キャディのプロダクトにはまだまだ大きな可能性があると思います。
時間軸や空間の制約を超えて、製造業の“経験知”を活かす
佐藤
キャディが提供する「製造業AIデータプラットフォーム CADDi」は、どのような考えから生まれたのですか。
幸松様
私たちは「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」というミッションを掲げています。そしてその“ポテンシャル”とは、製造業に蓄積されてきた「過去の経験知の総量」だと定義しています。
日本の製造業は、100年以上の歴史を持つ企業も多く、グローバル展開や国内に多数の工場を持つようなスケールの大きな業界。その中で、長い時間軸や組織の距離を超えて蓄積された知見が、各所に分散してしまっているのが現実です。
もしそれらの知見を正しく活用できれば、より迅速な意思決定や、トラブルの再発防止、業務の最適化につなげられるはずですが、実際にはそれが難しい。これは「認知の限界」、すなわち、人間が持つ時間・組織・空間の制約によって起きている問題です。
こうした限界を超える鍵になるのがAIだと考えています。AIは、正しく学習すれば過去の出来事や他部署・他地域の知見も統合的に活用し、最適なアウトプットを出すことができます。
しかし現在の生成AIは、主にオープンな一般知識を学習しており、製造業のように業界特有、かつ企業固有の知識については十分に対応できていないのが実情です。そこで私たちが重視しているのが「データの統合と基盤づくり」です。
AIを活用するには、まず企業内に点在するデータを整理し、形式を問わず統合する基盤が必要です。そして、AIがそれらを解析・構造化することで、さらにデータが蓄積され、活用が加速する。このサイクルが今後、製造業においても非常に重要になっていくと考えています。
佐藤
どのような経緯を経て「製造業AIデータプラットフォーム」が生まれたのでしょうか。
幸松様
Manufacturing事業からスタートした当初、私たちは日々、膨大な二次元の図面データや紙のスキャンと向き合うなか、人の目だけで確認するには限界があると痛感していたのです。
そこで自社内の業務効率化を高めるために、AIによる図面解析や見積もりの最適化のテクノロジーを独自に開発していました。
その技術を社外にも展開したのが、「CADDi Drawer」です。PDFやExcel、WordなどをAIで解析・構造化し、連携させることで情報の探索性を大きく向上させてきました。
たとえば以前は、設計図面と調達記録がバラバラの形式で保管されており、情報を突き合わせるために人間がその都度検索し、手作業で結び付ける必要がありました。それがAIの活用によって、自動でデータ同士がひもづき、最適な調達先やコストまでサジェストできるようになったのです。
つまり、AIで社内のデータを構造化し、統合。その基盤の上にさまざまなアプリケーションを乗せていくことで、製造業における調達・設計・品質などの業務を、より高度かつ効率的に最適化が可能となる。これが私たちの提供する「製造業AIデータプラットフォーム」になります。
佐藤
実際に導入された企業からは、どのような声があがっていますか。
幸松様
大きく短期的な業務効率化と、中長期的な部署横断の最適化という2つの側面で評価いただいています。
たとえば、ある企業では「紙の図面が何億枚も存在し、その所在を把握しているのが特定のベテランパート社員だけ」という現場がありました。キャディのプロダクト導入後は検索時間が激減し、その方が「ようやく好きな時に休めるようになった。これは福利厚生だ」と言ってくださったのが印象的でした。
また、調達部門では、部品価格のバラつきをAIが可視化し、価格最適化や調達戦略の高度化に貢献しています。
さらに、中長期的には、設計・調達・品質といった部門をまたぐナレッジの連携が進み、「この素材が高騰している」「この設計は不良率が高い」といった調達部門の声が設計部門にフィードバックされるようになりました。これは、製造業などでいわれる“フロントローディング”の実現であり、キャディが目指す「部門を超えた知見の活用」につながっていると感じます。

日本の製造業全体に手触り感を持ってインパクトが出せるEnterprise BizDev
佐藤
キャディの事業について理解が深まりました。ここからは、その中でも特に重要なポジションについて伺いたいです。今回はどのような方にジョインしてほしいと考えていますか。
幸松様
今回は「ソリューション本部」の「Enterprise BizDev」のポジションについて、お話しできればと思います。
当社にはすでに、図面や業務データを構造化・統合し、活用するプロダクト基盤が存在します。しかし、お客様の現場で本当に業務が改善されるためには、それだけでは不十分です。「あとこれがあれば一気に変わる」という最後のピース=ラストワンマイルを埋める必要があります。そのラストワンマイルに向き合うのがソリューション本部です。
佐藤
まさに、現場起点でソリューションを作る役割なのですね。
幸松様
そうですね。お客様の業務構造を深く理解したうえで、「どんなアプリケーションを作れば業務が変わるのか?」を設計し、実装・導入までやり切ること。最先端の技術を踏まえて実現可能性を見極め、現場にフィットするソリューションを形にする。特に大手製造業のように、課題そのものが明確でないケースも多いため、課題の言語化から技術との接続までをリードすることが求められます。
加えて個社対応から得た知見をもとに、汎用的なプロダクトの立ち上げも担うポジションです。実際、現場からは何十、何百という改善要望があがってきます。その中から「今この業界で本当に求められていることは何か?」「この機能を汎用化すれば、他社にも大きな価値があるのでは?」と見極め、プロダクトとしての勝ち筋をつくり、新たな収益の柱へとつなげていきます。
この職種は、目の前のお客様に向き合う“ソリューションの実行者”と、複数の成功事例を未来の事業に転換する“プロダクト化の起点”として機能しています。
職務としては、お客様の経営課題をヒアリングするところから始まり、その解決策を構想・設計し、プロダクト・エンジニアチームと連携して具体的な要件に落とし込んでいきます。そのうえで、ソリューション開発・導入をリードし、成果を実際に現場で定着させる。さらに、得られた知見を他社にも展開可能な形に抽象化し、汎用的なプロダクトとして磨き込んでいくと。非常に裁量が大きく、花形とも言えるポジションです。
佐藤
お話を伺っていて、コンサル出身の方にも親和性が高そうだと感じました。その違いについて、どうお考えですか。
幸松様
私自身もコンサル出身なので実感があるのですが、大きく2つの違いを感じています。
1つ目は「スピード感」。大手コンサルティングファームではシステム開発を外注し、要件定義からリリースまで1年近くかかることもありますよね。実際、ある企業の比較コンペでは他社が「開発期間1年」の見積もりを提示したのに対し、キャディは「2週間で動くデモを出します」と即答したのです。実際、翌々日には本当にプロトタイプを持参し、お客様を驚かせた、ということがありました。自社で設計から実装まで完結できるからこそのスピードです。
2つ目は「手触り感」。戦略を考えて終わりではなく、自分たちで設計し、実装し、お客様に届けて、その現場がどう変わったかまでを見届けられる。これは非常にやりがいがあり、自分の仕事が“手触りのある変化”につながっていることを実感できます。
佐藤
実際のチーム運営やKPIは、どのように設計されているのでしょうか。
幸松様
KPIは大きく2つあります。1つは、お客様との商談・提案活動に関する「営業的KPI」。もう1つは、導入後に成果を生み出す「デリバリーKPI」です。チームは現在、業界ごとに3つのユニットに分かれていて、今後の事業拡大に合わせて、業界別か機能別かで再編成していく可能性もあります。プロジェクト期間は中長期になるケースも多いため、フェーズごとにマイルストーンを区切って成果を定義する運営を行っています。
佐藤
Enterprise BizDevのやりがいは、どんな点にあるのでしょうか。
幸松様
特に面白いのは、ソリューションの企画から提案、実装・デリバリーまでを一気通貫で担える点です。たとえば、ある半導体製造装置メーカーで売り上げを2倍にできたら、それはその企業だけでなく、日本のGDPにも影響を与えるレベルの話になります。業界単位、さらには日本の製造業全体にまでインパクトを与えられる。そんな大きな手応えを感じられるポジションだと思います。
実際、あるお客様とのプロジェクトでは、役員の方々との議論を重ね、「リードタイムが長い」「部署間での意思決定が分断されている」といった最上段の経営イシューに踏み込みながら、根本解決に取り組んでいます。こうした経営課題に直結するソリューションを、最前線でつくっていけるのはこのポジションならではの醍醐味です。
また、私たちが扱っているのは図面データや部品情報、不良トラブルなど、世の中に公開されていない非常に“ディープ”な非構造化データばかりです。こうした情報をどう解析し、どう価値に変えていくか。これはデータ活用に興味がある方や、好奇心旺盛な方にとってはまさに腕の見せどころだと思います。
高い視座と実行力が求められるEnterprise BizDev
佐藤
こうした難易度の高いミッションに挑むうえで、Enterprise BizDevではどのような要件が必要なのでしょうか。
幸松様
Enterprise BizDevは、CxOクラスの方々と向き合いながら、テクノロジーパートナーとして課題を深掘りし、解決までリードしていく役割です。業務課題や経営課題をヒアリングから、ソリューションの設計、開発、デリバリーまで一気通貫でやり切る。そして、そのソリューションをどう横展開していくかまでを見据える必要があります。
もちろん、すべてを1人で担うわけではありませんが、それでも非常に高い視座と実行力が求められるチャレンジングな役割だと思います。
バックグラウンドとして、コンサルティングファーム出身の方であれば、戦略系・総合系、IT/DX系など、実務経験がある方。また、データサイエンティストやデータコンサルタントの方は、PythonやRなどを使った実務経験、SQLを用いたデータベースの操作など、技術的スキルをお持ちの方が対象です。
ビジネスデベロップメントの役割では、ソリューションをどう事業化し、継続的な収益につなげていくかといった視点が欠かせません。スタートアップやベンチャーでSaaS事業の企画した経験がある方や、大手企業でAI領域の事業企画に関わった方などは非常にフィットすると思います。
佐藤
実際にはどのようなメンバーが在籍しているのでしょうか。
幸松様
チームをリードしているメンバーを2名ご紹介したいと思います。
1人目は、現在35歳で入社3年目のメンバーです。前職はIBMで、大手メーカーに対してDXの大型案件を多数リードしてきました。2024年にはソリューション本部のヘッドに就任し、部門執行役員として事業をリードしています。
もう1人は、事業会社側での経験が豊富な42歳のメンバーです。彼は楽天で広告営業やECコンサルティング、新規事業などに携わり、2017年からは楽天データマーケティングの設立にも参画。2024年にキャディにジョインし、現在はソリューションチームの部長職を務めています。
佐藤
キャディの採用計画についても教えてください。
幸松様
採用は今、最も注力しているテーマの1つです。昨年は年間100名の採用計画でしたが、今年は一気に400名を目標にしています。来期はさらにそのうえを見据えており、事業の成長スピードに対して人材の獲得がまったく追いついていないというのが正直なところです。
Enterprise BizDevについても直近でどんどん仲間が増えており、チームとしての成果も出ているため、今後さらに採用スピードを上げていく予定です。
佐藤
報酬制度についても見直しがあったと伺いました。
幸松様
はい。大きく2つアップデートを行いました。
1つ目は、固定給のベースアップです。この職種は会社としても非常に大きなインパクトを持つポジションであり、優秀な方には初めから高めの報酬で応え、機会損失を防ぎたいと考えています。そのため、現在は、成果を100%達成した場合の水準を、あらかじめ固定給として設定しています。
2つ目は、賞与制度の見直しです。特にデータサイエンティストなど、数字で直接計りにくい貢献を正当に評価するため、チームとしての成果に連動した賞与を導入しました。
キャディが直面しているのは、これまで誰も解決できなかった産業の課題です。そこに挑戦するからこそ、大きな裁量とリターンがある。価値創造の最前線に立ちたい方にとって、非常にやりがいのある環境だと思いますね。

東京大学を卒業後、マッキンゼーにて約4年間勤務。マッキンゼーでは米国や中国を含む、国内外の製造業を中心にオペレーションやSCM分野を担当。マネージャーとして1万人を超える組織のIT戦略や組織改革などをリード。その後、板金加工会社の現場に勤務し、町工場の実情を肌身で学ぶ。2017年末にキャディ株式会社の3人目社員としてジョイン。パートナーサクセス本部長、Manufacturing Operations本部長、執行役員 Manufacturing事業部 品質保証部部長などを歴任した後、2024年10月に部門執行役員 JapanCHRO就任。

キャディ株式会社は、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、点在するデータ・経験を資産化し、新たな価値を創出する「製造業AIデータプラットフォームCADDi」を開発・提供するスタートアップ企業です。アプリケーションである「製造業データ活用クラウドCADDi Drawer」「製造業AI見積クラウド CADDi Quote」をはじめ、今後もプラットフォーム上に様々なアプリケーションを提供予定です。日本をはじめアメリカ、ベトナム、タイを含む4カ国で事業を展開し、製造業のグローバルな変革を実現していきます。累計エクイティ資金調達額は257.3億円。

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
キャディ株式会社の求人情報
| 募集職種 | Enterprise Bizdev |
|---|---|
| 職務内容 | ■募集背景 幅広いスキルが求められますし、動かすものが大きい、難易度の高い仕事です。何より「私がやらなきゃ誰がやるんだ」という壮大な野心を持った方と、まずはお話させていただきたいです。 ■具体的な仕事内容 ■業務イメージ ■入社後のイメージ |
| 応募要件 | ■必須 ■歓迎 |