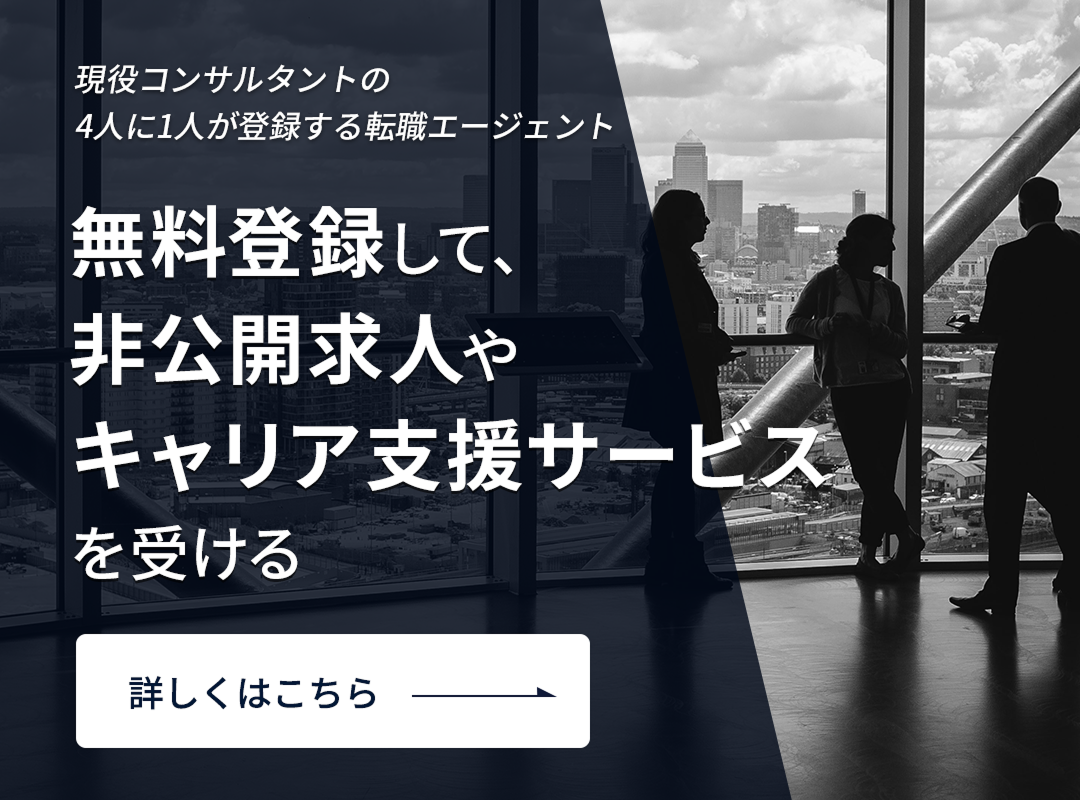ドルビックスコンサルティング株式会社 インタビュー/「金融法人部」新設で外販比率8割へ、銀行チャネル活用による地域の中堅・大企業の開拓戦略

「商社発のコンサルティングファーム」という独自性を武器に急成長を遂げるドルビックスコンサルティング株式会社。創業5年目の現在約150名の体制から、10年以内に2,000名規模への拡大を目指す同社は、2025年に「金融法人部」を新設。メガバンクや地方銀行との連携を通じて、これまで大手ファームがアプローチしきれていなかった地域の中堅・大企業層への本格参入を図っています。
外販比率を現在の5割から将来的に8~9割まで引き上げる組織改編の中核を担う同部門は、金融機関をチャネルとした新たなコンサルティングモデルの確立を目指しています。
今回は、取締役COO の武藤覚様とマネージングディレクター金融法人部長の後藤尊志様に、急成長を支える戦略的取り組みと、地域の中堅・大企業の経営変革を通じた日本経済活性化への思いについて詳しくお話を伺いました。
※2025年6月時点での内容です
Index
2,000人は通過点、M&Aと採用強化で組織拡大中
田中
まずは御社の現状についてお聞かせください。
武藤様
弊社は2021年1月に丸紅資本で創業し、今年5年目を迎えました。これまで順調に案件開拓や人材採用を進めており、業績も継続的に急拡大しています。現在約150名のプロフェッショナルが在籍しており、過去4年間で累計400件を超えるプロジェクトを実施してきました。
新卒採用を開始し、来年4月には中途採用とあわせて200名規模の体制を目指しています。長期的には10年以内に2,000名規模を目指し、大手コンサルティングファームと肩を並べる体制を目標にしています。
ただし、2,000名は通過点であり、最終的には“商社発のコンサルティングファーム”として国内ナンバーワンを目指しています。そのためには人材の質と量の両面を強化しており、中途・新卒を問わず未経験層も積極的に採用し、OJT以外に階層別研修やIT基礎研修などを通じて育成を図っています。
田中
成長戦略として今後はどのようなご予定でしょうか。
武藤様
人材採用によるオーガニックな成長に加え、丸紅の資本力を活用し、M&Aによるインオーガニックな拡大も進めます。すでにM&A戦略を策定し、いくつかの具体的なM&A案件も検討しており、今年度から実行フェーズに入る予定です。
また、外販比率も2023年度で4割程度、2024年度には5割程度、今年度は6割程度へ伸ばし、将来的には8〜9割を目指します。
田中
M&Aの戦略的な方向性を詳しく教えてください。
武藤様
M&Aにおいては、「業界軸×サービス軸」で構成されるマトリックスの中で、リーチしきれていなかった領域を戦略的に補完していく方針です。
業界軸では、製造業、金融、TMTなど、もともとコンサルティング活用が進んでおり、投資意欲の高い業界に強みを持つ企業を優先的に検討しています。
サービス軸では、弊社がこれまで注力してきた戦略立案、新規事業開発、業務改革、IT構想といった上流領域に加え、今後はIT実装支援やPMO、さらに将来はBPOなど、より下流・実行フェーズに強みを持つ企業との連携や統合も視野に入れています。
田中
丸紅グループ全体の中で、貴社はどのような役割を担い、どのような貢献を果たすことを期待されていますか。
武藤様
我々は総合商社・丸紅を母体に持つ企業として、ビジネスのスケールを追求することは当然の前提です。そうした背景のもと、成長性の高いITを中心としたコンサルティング領域をいかに広げていくかは、大きな期待として寄せられています。
実際、情報ソリューション分野は丸紅の中期経営計画でも戦略の中核に位置づけられていますし、弊社としてもその成長を支える役割を担っていくことが求められています。
市場環境としても追い風があります。ある調査によれば、日本のコンサルティング業界は2024年に約1.6兆円、2028年には3.2兆円へと倍増する見込みで、年平均成長率で20%近い勢いです。そうした成長市場の中で、我々のビジネスにも大きな拡大余地があると見ています。

外販比率8割を目指す組織改編、営業開発部&金融法人部が担う役割
田中
続いて、今年度「金融法人部」を新たに設立された背景についてお聞かせください。
武藤様
背景には、外販比率の拡大という大きな方針があります。
これまでも「事業開発室」という組織を設けていましたが、今回の組織改編により「事業開発本部」に格上げし、その中に「営業開発部」と「金融法人部」を新設しました。
営業開発部は、丸紅本体やグループ会社との連携による案件開拓を担う部門で、2024年度からは丸紅グループの取引先企業への提案活動にも本格的に着手しています。今後はその取り組みをさらに強化していく方針です。我々は、丸紅グループを“チャネル”と見立て、その先にいる企業のお客様へコンサルティングサービスを届けることを目指しています。
一方の金融法人部は、メガバンクや地方銀行といった金融機関と連携し、各行の取引先企業に対してコンサルティングサービスを行っていく部門です。こちらも同様に、金融機関をチャネルとし、地域に根ざした中堅・大企業向けに提案活動を展開していきます。
これまでも丸紅からは地方銀行に出向者を送り、地方企業への支援に“部分的”には取り組んできました。ただ、今後は“面”での関係性を築きながら、より体系的かつ広範囲に金融機関との連携を強化していく構想です。
田中
では、金融機関の取引先企業に対して、ドルビックスとしてどのような強みを発揮できるとお考えですか。
武藤様
大きく2つあります。まず1つ目は、“ハンズオン型”の支援スタイルです。我々は、外部の第三者的な立場で戦略だけを描いて報告書を提出するといったスタイルとは異なり、丸紅グループのインハウスコンサルティングで培った、構想策定から実行、運用改善に至るまでを一貫して伴走する支援に強みがあります。
実際のプロジェクトでも、新技術を活用した新たな事業を立ち上げて収益化するまで支援することや、クライアントと一緒に事業運営に入り込むケースも少なくありません。
クライアント側から補強人材として強く要請され、上流工程を担っていたコンサルタントがそのまま運用フェーズまで関与し、「Day1」のサービスインを完遂するだけではなく、「Day2」や「Day3」のサービスインまで継続的に支援するケースもありますね。
田中
実行にも深く入り込んでいるのですね。
武藤様
はい。そして2つ目は、幅広い業界・テーマに対応できる総合力です。我々は丸紅グループのコンサルティングファームとして、商社案件を通じて非常に多様な業界・領域に関わってきました。そうした知見を活かし、地方企業が抱える様々な経営課題にも柔軟に対応できる体制を持っています。
田中
具体的には、どのような企業やテーマでご支援されてきたのでしょうか。実績を教えていただけますか。
武藤様
地域の中堅・大企業の案件事例を3つご紹介します。
1つ目は、建材メーカーの工場におけるDX支援です。自律的な工場操業に向けた施策の一環として、自動化による効果の最大化を図り生産工程にロボティクスを導入する構想からスタートし、技術面での実現可能性を見ながら実際の導入・実現まで一貫して伴走支援する案件です。省人化をはじめ多様な取り組みによるコスト削減を期待されています。
2つ目は、自動車部品メーカーの基幹システムの刷新に向けた構想策定支援です。古いシステムを使い続けている企業は少なくなく、ソフトウェアやハードウェアのサポートが終了しているため「どこから手を付ければよいか」というお悩み段階の相談がよくあります。 我々はまず、現行の業務とシステム課題を洗い出すところから着手し、次期システムの構想立案、システム化計画の策定、さらに刷新プロジェクトの実行推進まで一気通貫で支援しています。
3つ目は、半導体製造装置メーカーの人材管理体系の刷新支援です。背景には、若年層の人口減少に加え、就職氷河期世代の採用抑制により、企業の中核を担うリーダー層が手薄になっているという構造的な課題があります。 一方で、働き方や価値観は大きく変化しているのに、人事制度が旧態依然のままというケースも少なくありません。
この案件では、今後の経営戦略を踏まえた際にどのような人材が必要となるのか、そのような人材をどのように採用、育成し定着を図るかという人材戦略の立案からスタートし、人事制度の刷新を支援しました。このテーマは地方企業に限らず、丸紅グループの支援先でも類似の事例が多く、共通性の高いテーマだと感じています。
田中
金融機関との取り組みについてもお伺いできますか?
武藤様
金融法人部では、金融機関の取引先企業の支援を進めていますが、一方で、金融機関自身の経営課題についてのご相談も増えています。例えば、ある地方銀行との協業では、地域新電力事業の立ち上げを丸紅と連携して支援しています。
また、損害保険会社にはITシステム更改に伴うPMO支援を行い、証券会社ではバックオフィスの業務改革(BPR)に取り組んでいます。こうした実績を通じて得た知見やノウハウは、今後、他の銀行や金融機関にも十分に展開可能だと考えています。
田中
金融法人部の立ち上げにあたり、主にメガバンクや地方銀行の先にいる企業へのアプローチを進めていると伺いました。ただ近年、金融機関自身がコンサルティング機能を強化し、内製化も進んでいる印象があります。そうした中で、ドルビックスとしてはどのような役割を担うのでしょうか?
後藤様
おっしゃる通り、2010年代に入り金融庁が金融機関に対して「事業性評価」の重要性を提唱し、企業の本質的な成長性を見極めた融資・支援を求めるようになりました。それをきっかけに、金融機関でも取引先に対してコンサルティング機能の発揮を図るために、外部への出向などによる人材育成を行い、自行でコンサルティングを手掛け内製化が進んでいると認識しています。
特に中小企業に対しては、金融機関自身で対応するケースが増えていますが、取引先が中堅企業や大企業に成長していく過程で、経営課題の解決における対応が難しくなってきているという声も多く聞かれます。こうした場面でこそ、私たちのような外部のコンサルティングファームとの連携が生きてくる。つまり、金融機関と連携しながら、彼らが手の届きにくい領域を補完していく形で、役割の棲み分けが進んでいるのが実態です。
田中
とはいえ、Big4などの大手コンサルティングファームも、そういった企業にすでに入っているケースが多いのではないでしょうか。
後藤様
確かに、マッキンゼーやBCGなど大手戦略系ファームは主に超大手企業が対象ですので、我々とバッティングすることはほとんどありませんが、Big4や独立系コンサルティングファームなどは、地域の中堅・大企業にも対応しており、弊社も一部でこうしたファームと競合することがあります。ですが、事業再生など特定の領域に偏ったり、また案件を受注しても顧客からの期待値に応えきれていなかったりと、実際に地域の中堅・大企業のニーズに対してすべてを網羅しきるのは難易度が高いといえます。
大手コンサルティングファームやBig4の出身者が多く、こうした地域の中堅・大企業のニーズに対応するために、不足しているピースを埋める役割を持つことができるのが私たちの強みです。さらに、総合商社である丸紅の知見やネットワークを活用できること。これは、他の独立系・外資系コンサルティングファームにはない、明確な差別化要素となっています。
銀行×Big4×行政の経歴を持つ後藤氏が率いる金融法人部のミッション
田中
改めて、今回新設された「金融法人部」をリードされる後藤様のご経歴について伺えますか。
後藤様
大学卒業後、大手都市銀行に入行し、その後、Big4を経て、独立系コンサルティングファームに転職しました。独立系コンサルティングファーム在籍中には、金融庁の監督局への出向も経験し、地方銀行の監督や企画業務にも関わりました。2025年5月からドルビックスに参画しています。
私のキャリアには3つの特徴があります。
まず1つ目は、銀行での現場経験、企業向けのコンサルティング経験、監督官庁での金融行政の経験という、金融を3方向から見てきた点ですね。金融を多面的に捉えられるバランス感覚が強みだと思っています。
2つ目は、ゼロから金融機関との関係構築に多数関わってきたこと。Big4や独立系コンサルティングファームでも、金融機関本体や金融機関取引先の課題解決などを通じて、全国の様々な金融機関の役職員とネットワークを築いてきました。
3つ目は、成長支援から事業再生まで幅広いフェーズにある様々な地域の中堅企業に対して、戦略から戦術における個々のテーマで課題解決に向き合ってきたことです。こうした経験が、今の実務にも大いに生きています。
田中
ドルビックスの金融法人部での役割はどのようなものでしょうか。
後藤様
当部の主な役割は、外販活動の強化です。具体的には、金融機関内の各部におけるキーパーソンとの関係構築と潜在案件ニーズの発掘、弊社のコンサルティング部門や親会社の丸紅との連携を通じた課題解決のための提案活動、そして案件受注後には案件進行中のフォローアップや完了後のアフターフォローまでを担います。
田中
金融法人部で働くことの魅力についても教えてください。
後藤様
大きく3つあると思っています。
1つ目は、プロフェッショナルとして成長できる環境があることです。中堅・大企業の課題解決に関して、金融機関はコンサルティングファームとの協業に積極的な状況にあります。自社のコンサルタントや丸紅という事業会社の知見を活用し、銀行と一体となって顧客の課題解決に関わる経験は、貴重なキャリアになりますね。
2つ目は、顧客や金融機関から信頼や感謝される経験が自身の財産になることです。壁は高いものの、関係者と同じ船に乗り、相手の本質的な課題の解決に向き合うからこそ、パートナーとして信頼を得て、やりがいを感じられます。
3つ目は、会社の成長フェーズにおいて、立ち上げ期の事業開発に直接携われることです。こうしたダイナミックな環境で、事業開発の仲間と共に自らの手で会社の成長に貢献できるのは大きな魅力ですね。
田中
今後、どのような体制を目指していかれますか。
後藤様
まずは3年以内に5名程度のチーム体制を整えたいと考えています。弊社内での売上貢献のプレゼンスを上げて、金融法人部が外販拡大の中核の一翼を担うことが目標です。加えて、中堅・大企業の企業価値を向上できるプロフェッショナルなソリューション人材の育成・輩出にも力を入れていく方針です。
田中
営業の進め方として、まず金融機関様に提案し、その後、クライアント企業につなげていく形でしょうか?
後藤様
はい。ただ、正確にはまず金融機関様との対話を通じて、何に困っているのかを丁寧に引き出すところからです。一例として、本部や営業店、例えば、本部でいえば法人企画、法人ソリューションなど、営業店でいえば本店営業部や各エリア拠点などに伺い、対話の中で潜在案件のヒントを探ることもあれば、勉強会や事例紹介を通じて、担当者の困りごとを引き出すこともします。そのうえで、「一度話を聞いてみませんか」と持ちかけ、弊社のサービスラインをご紹介する。その後、意見交換を行ったうえで、金融機関様がクライアント企業様のニーズに合いそうだと納得した場合、金融機関様を通じてクライアント企業様との面談の場が設定されます。
そこで仮説に基づいた経営課題の提示を行い、何度かのやり取りを経て、具体的な提案フェーズに進みます。提案書の提出を行い、クライアント企業様がその提案を了承して初めて正式な案件化となる流れです。
田中
関係構築に時間をかけて、信頼を積み重ねていくモデルですね。
後藤様
おっしゃる通りです。まずは金融機関様との関係構築に時間がかかります。一般的にコンサルティングファームでは、初回面談でさえ、金融機関様に対応してもらえないのが通常です。弊社の場合、丸紅が全国の金融機関様と関係があり、かつ私自身のこれまでの個人的な金融機関様との関係を組み合わせて、現状は私自身がフロントに立ち、会社の知名度を高め、サービス理解につなげています。今後は、こうした基盤を活かして、案件獲得のスピードも加速していくはずです。
田中
実際の案件フェーズでは、どの程度まで関与されるのでしょうか?
後藤様
私たちは、例えば、いわばコンダクターのような立場です。演奏するのはコンサルタントですが、金融機関様の期待値を踏まえながら課題解決に向けた案件の仮説を描き、社内の適切なチームを組成していくのが私たちの役割。場合によっては、複数のコンサル本部が絡むため、その調整役も担います。また、社内的には芸能人のマネージャーのような存在ともいえるでしょう。舞台には決して立ちませんが、コンサルタントが表部隊で活躍できるように、関係者との調整を行い、事前準備を整えて、本番を迎えることを行っていきます。コンサルタントを裏から支えて、企業価値向上という成果を、舞台袖から支える黒子でありたいと考えています。
田中
つなぐというより、設計する立場でもあるわけですね。
後藤様
まさにその通りです。ですから、戦略的な思考を持ち、様々なリソースを活用して課題解決を行いたい方にこそぜひ挑戦していただきたいと思っています。

求めるのは“自走力、チーム力、金融知見”
田中
先ほど求める人物像についてのお話がありましたが、今回の金融法人部で活躍される方の採用要件について、具体的にお聞かせいただけますか?
後藤様
人材面では、大きく3つのポイントがあります。
まず1つ目は、自ら考えて行動できる方。最終的には、自分なりのストーリーを描いて動けるようになってほしいと思っています。言われたことだけをこなすのではなく、自発的にニーズを探しにいける姿勢が大切です。
2つ目は、チームプレーを重視できる方。金融機関自身の課題や地域の中堅・大企業の課題解決に向けたプロフェッショナルな組織を構築したいと考えています。その中で、チーム全体としてレベルアップを行うには、チーム内のメンバーをライバル視するのではなく、良い情報や経験を共有し仲間として一緒に成長しあえる関係が必要だと思っています。
そして3つ目は、高いコミュニケーション能力ですね。地方を含め、多様な関係者とやり取りする機会が多いため、場面に応じた柔軟な対応ができる方を歓迎します。先ほども申し上げたように、金融機関様との関係構築や社内外の連携など、“芸能人のマネージャー”的な動きが求められる場面も多いため、関係者と柔軟に協働できる力が不可欠です。
スキル面では、金融機関、特に銀行での勤務経験がある方が望ましいと考えています。もしくは、アドバイザリー、コンサルティング、ファンドなどで金融機関向けの営業やプロダクトの業務経験を持っている方も適任ですね。
金融機関との対話では、金融機関の業務の構造やサービス内容をある程度理解している必要がありますし、その先にいる顧客企業の課題認識や事業性評価への理解も欠かせません。
専門知識を深く求めるわけではありませんが、経営課題の捉え方やソリューションの導き方を理解している方が望ましいですね。加えて、実際に中堅・大企業の課題解決に関わった経験があれば、より即戦力としてご活躍いただけると思います。
田中
候補となる方々は、普段から経営層や役職者とやり取りされていると思いますが、コンサルティングファームでの営業経験がない場合でも、「この課題にはこのDXソリューションが合うのでは?」といった仮説構築のような力も求められるのでしょうか。
後藤様
即戦力としてすぐに活躍いただくには、多少時間がかかる部分もあると思います。ただ、私自身もこれまでに何度も新しい領域に挑戦してきました。
大事なのは、お客様の課題を正確に捉える力です。そのうえで「この課題なら社内の誰に相談すべきか」を判断し、適切な連携ができればいいのですから。具体的なソリューション提案や知識の習得は、入社後に学んでいただければ十分です。
田中
御社のコンサルタントの方々の印象についても伺いたいです。後藤様はご入社されてまだ日が浅いとは思いますが、どのような印象をお持ちですか?
後藤様
まだ在籍して1カ月ほどですが、大手コンサルティングファーム出身者が多く、それぞれが何かしらの専門性を持っている印象があります。一方で、丸紅グループ内の案件を行ってきたコンサルタントも多く、金融機関や金融機関の取引先にどのようなニーズがあるのか、など金融機関についてよく知らない人が多いのが実情です。今回、金融機関向け営業専任部門が立ち上がったことで、より外に向けて「攻め」の姿勢が加わることで、良い意味でソーシングにおいて役割の補完関係が築けると感じています。
武藤様
実は、社内の営業力にもばらつきがあるのが現状です。営業マインドや人脈は人によって異なりますし、属人的な営業体制では組織としての成長が難しい。だからこそ、今回の金融法人営業や丸紅のネットワークを活用した「チャネル営業」に力を入れています。個々の属人的な営業に頼らず、組織的・戦略的に案件を獲得していく体制づくりが狙いです。
後藤様
実際に、コンサルタント自身が営業まで担うと、どうしても工数が足りず、売上にも波が生じやすくなります。結果として稼働率も下がりがちです。営業専任部門が一定の案件をストックし、顧客のニーズに基づき適切なタイミングで供給できる体制を整えることで、コンサルタントが安定して価値提供に集中できる環境が実現できると考えています。
田中
そのような体制が整うことで、コンサルタントの採用要件にも変化が出てくるのではないでしょうか?営業経験がなくても採用しやすくなるなど、柔軟性が広がるように思います。
武藤様
おっしゃる通りです。財務的な責任、つまり損益はデリバリーリソースを抱えるコンサル部門が担っています。一方で、事業開発本部は売上目標こそ持ちますが、利益責任は負いません。
このように「売上」と「利益」の責任を分けて管理することで、互いに競合するのではなく、コラボレーションしながら成果を最大化できる構造をとっています。
結果として、コンサルタントに過度な営業負荷がかからず、営業経験の有無にとらわれずに多様な人材を受け入れやすい柔軟な採用体制が整ってきています。

「金融機関の抜本的変革に立ち向かう」地域活性化から日本全体の活力創出へ
田中
最後に、お二人からメッセージをお願いいたします。
武藤様
今回の金融法人部の立ち上げは、会社として重要なテーマである「外販拡大」に真正面から取り組むための、戦略的な施策の1つです。このフェーズに参画いただければ、会社の成長に直接関わりながら、ご自身のキャリアやスキルも大きく飛躍させることができるはずです。そうした成長の機会に前向きに挑戦してくださる方と、ぜひ一緒に取り組んでいけたらうれしいです。
後藤様
私からは“金融”という軸でお話します。今、金融業界は大きな変革の時期にあります。例えばPBR1倍割れへの対応に象徴されるように、特に地域金融機関は今、企業価値の向上に本気で取り組まざるを得ない局面にあります。 それと同時に、地域経済への貢献という本来的な役割も求められており、両立のための抜本的な変革が必要とされています。
こうした中、金融機関自身のトップラインの強化や業務効率化の動き、また金融機関取引先における成長期待のある中堅企業の伴奏支援など様々なテーマが目白押しです。
そんな時代の変化にあって、私たちと共に地域を元気にし、そしてその先にある日本全体の活力につなげていく。そういった志を持ち、一緒に未来をつくっていける仲間と出会えることを楽しみにしています。


東京大学大学院理学系研究科博士課程修了後、三菱総合研究所、フロンティア・マネジメント、アビームコンサルティングなどを経て、当社創業時に取締役COOに就任。コンサルタントとして、事業会社や金融機関の戦略立案、業務改革、IT活用などの多数の支援実績を有することに加えて、コンサルティング会社の運営や実行主体として新規事業を複数立ち上げる等の豊富なビジネス経験を有する。スタンフォード大学でMBAを取得。

三菱銀行(現、三菱UFJ銀行)、KPMG FAS、フロンティア・マネジメントを経て、2025年より現職。 金融庁での地域金融機関の監督業務、大手銀行での常駐経験や金融機関に対するアドバイザリー/コンサルティング業務経験を有する他、金融機関の取引先に対して多様なソリューション機能の提供に豊富な経験と実績を有する。

会社名 ドルビックスコンサルティング株式会社
資本金(資本準備金含む) 740百万円
株主構成 丸紅株式会社100%
役員構成
代表取締役社長CEO 菅 隆之
取締役COO 武藤 覚
取締役 柴田 武之
取締役 瀧本 愼平
取締役(非常勤) 渡辺 剛史
監査役(非常勤) 滝井 登
会社設立日 2020年12月21日
事業開始日 2021年1月4日
所在地 東京都中央区日本橋室町2-3-1 コレド室町2 10階
事業内容 顧客のデジタルトランスフォーメーションを支援し全面的に推し進めるコンサルティングサービスの提供
参考:https://www.dolbix.com/

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
ドルビックスコンサルティング株式会社の求人情報
| 募集職種 | 【中途事業開発】金融法人営業/シニアマネージャー~マネージャー |
|---|---|
| 職務内容 | 大手金融機関、地域金融機関等、全国の金融法人を通じたリレーションの維持・強化を図ることで、案件の受注獲得の支援を行っていただきます。 ■業務詳細 |
| 応募要件 | ■必須条件 <必須スキル> ■歓迎条件 <資格> |