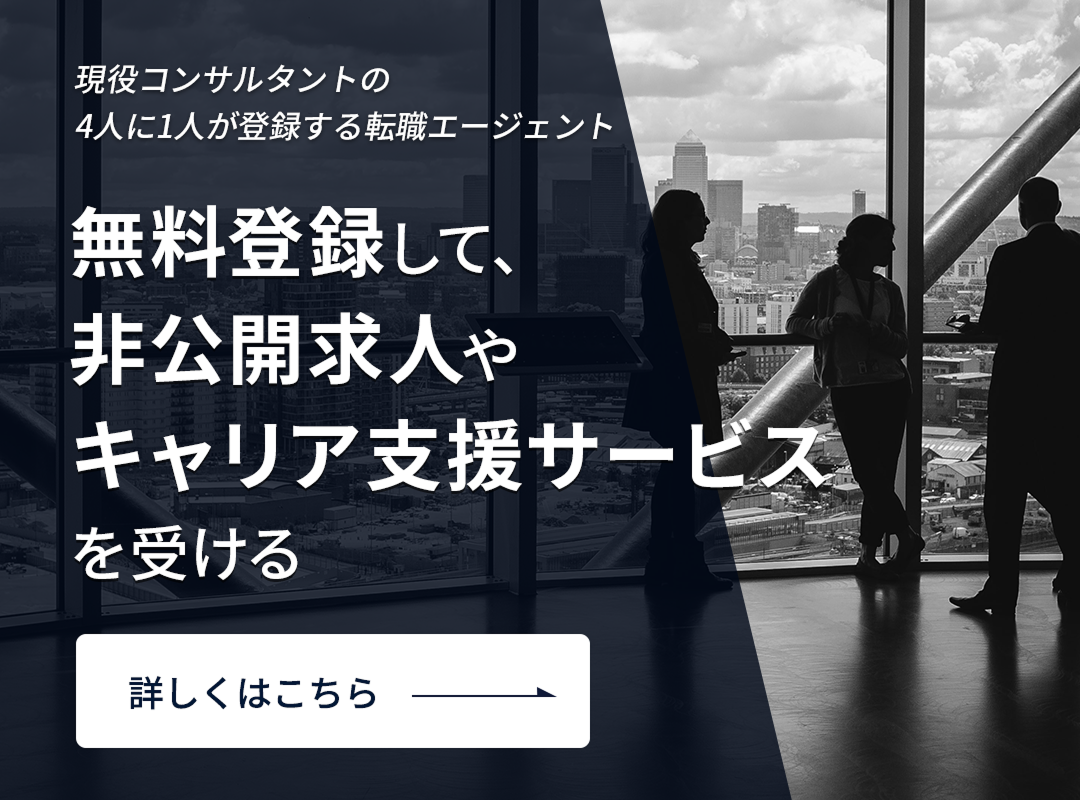日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 インタビュー/「強い個」が「傾聴と対話」を通じて日本の社会課題・経営課題に挑み、ありたい未来をつくる

日本企業の世界企業ランキングでの地位低下が続く中、これまでとは異なるアプローチでの課題解決が求められています。この状況に対し、日本発のコンサルティングファームとして独自の価値創造に挑んでいるのが、株式会社日本総合研究所(以下、日本総研)のリサーチ・コンサルティング部門です。
1989年の設立以来「強い個の集団」を標榜し、現在約350名のコンサルタントが主に3つのユニット体制で活動。同部門の特徴は、日本企業の文化や課題を深く理解したうえでの「傾聴と対話」によるアプローチです。AI時代だからこそ重要となる人間同士のコミュニケーションを重視し、経営層も気づかない真の課題を発見し、実効性のある変革を実現しています。
今回は、リサーチ・コンサルティング部門本部長の石田直美様、都市地域イノベーションユニット長の前田直之様、ストラテジー&オペレーションユニット長の斉藤岳様、ストラテジー&インダストリーユニット長の浅川秀之様より、2021年に策定したパーパスが組織に与えた影響、官民連携から企業変革まで各ユニットの専門性、そして350人から500人体制への成長戦略についてお話を伺いました。
※2025年6月時点での内容です
Index
国が抱える社会課題解決から、民間企業の経営課題解決まで、多様な領域におけるコンサルティング
アクシス
まず皆さまのご経歴について、お話しいただけますか。
石田様
私は1997年に新卒で日本総研に入社し、官民連携の領域に長く携わってきました。具体的には、ごみ処理、下水道を担当した後に上水道、バイオマス、エネルギーなどの分野に関わりました。これまでキャリアを重ねる中でインキュベーションを担う創発戦略センターからリサーチ・コンサルティング部門に異動しましたが、官民連携というテーマは一貫しています。2019年からの3年間は内閣府で、自治体による医療予防・介護予防事業を推進する仕事をしました。日本総研に戻ってきてからは本部長代行を経て、2025年4月より本部長を務めています。

前田様
私は大学と大学院で建築や都市計画、まちづくり分野を専攻してきました。研究室のメンバーと共に行っていた地域活性化に向けた活動を仕事にしたいと思い、新卒では日本総研とは別のコンサルティング会社に入りました。2007年に日本総研に転職しましたが、前職でも現職でも一貫してまちづくりや、PPP/PFIといった官民連携での事業化に携わってきました。

斉藤様
私は学生時代に電波天文学を専攻していましたが、当時読んだ書籍の影響でコンサルティングの仕事への憧れがあり、日本総研に2000年に新卒入社しました。入社後はずっと、いわゆる民間の経営コンサルティングをしてきました。当時はERPの基幹システムの導入がはやっていて、入社後約2年にわたって、ある会社での導入プロジェクトを担当しました。その後、製薬会社の経営再建をしたり、ビジネスデューデリジェンスの枠組みをゼロからつくったりと、面白い経験ができました。
現在は、ストラテジー&オペレーションというユニットの責任者を務めていますが、その前身となる組織を2017年に立ち上げました。日本総研では、組織やコンサルティングテーマの立ち上げも含めて個人の意向を最大限尊重してくれる風土があり、当時も自ら手を挙げて新しい組織の立ち上げを実現することができました。今は、戦略から実行まで一貫してフルパッケージでご支援できるようなユニットになってきたのではないかと思っています。
一方で、私たちの取り組みが十分に他のファームと肩を並べて伝わっているのか、課題も感じています。経営者や事業会社のコーポレート系のスタッフの方、そして戦略コンサルタントとしての転職を検討されている方々への認知度をさらに上げていきたいです。

浅川様
私は大学、大学院で物理学の中でも光に関する分野を研究していたこともあり、光通信の開発を行っていた電子機器メーカーに入社し、製品開発に取り組んでいました。ただ2000年代初頭に、会社がハードの開発を絞る方針を打ち出したこともあり、将来が不透明になりました。もともと学生時代からコンサルティング業界への興味もあったこと、製品開発よりもさらに上流で仕事をしたいという思いがあったことから、2003年に日本総研に移りました。
入社後は通信分野の知識を生かし、通信・メディア・ハイテク戦略グループに所属しました。グループ長としての経験も経て、今年4月にストラテジー&インダストリーユニットというより大きな組織が立ち上がり、そのユニット長を務めています。

「強い個の集団」として350名が結集、公共・民間・産業の各領域で経営課題・社会課題解決に挑む
アクシス
リサーチ・コンサルティング部門の概要について教えていただけますでしょうか。
石田様
リサーチ・コンサルティング部門は、設立以来「強い個の集団」を掲げてきました。それぞれの理想や思いを追求するプロフェッショナルとして仕事をする人たちが集まっている組織です。現在約350名のコンサルタントで構成され、都市地域イノベーションユニット、ストラテジー&オペレーションユニット、ストラテジー&インダストリーユニットの大きく3つのユニットを中心に構成されている体制となっています。
組織としては現在の350人から500人への規模拡大を進めている過程ですが、一人ひとりが働きやすく、パフォーマンスが上げられるよう組織設計を行っています。
100人弱程度の単位が1つの塊として目が届く適正範囲と考え、その塊を増やすことで組織全体を大きくしていくイメージを考えています。「強い個」同士が組み合わさることで、さらに価値を高めていける場をつくり、複雑化する社会課題に対応できる組織づくりを目指しています。

アクシス
それぞれのユニットの特徴について教えていただけますでしょうか。
前田様
都市地域イノベーションユニットは、複雑化する社会課題に対し、官民連携やまちづくりの専門性を生かしたコンサルティングを提供するユニットです。傾聴と対話を通じて、行政が思っていることと市民が望んでいるものが一致しないときには、第三者として「こうあるべきではないか」と提示し、対話を重ねながら解決策を導き出します。
6つのグループ構成:
・都市・モビリティデザイングループ
・都市戦略グループ
・社会・環境インフライノベーショングループ
・地域・共創デザイングループ
・サステナブル社会デザイングループ
・デジタル社会創成グループ
都市地域開発、交通、エネルギー、インフラ、デジタル、文化芸術、スポーツなどの分野での豊富な実績を持ち、地域や社会が抱えるさまざまな課題の解決に官民連携で長年取り組んできました。クライアントと長い時間をかけて1つのプロジェクトに向き合い、伴走することで、その地域や社会の未来をつくるような支援をしますので、クライアントとは戦友のような関係性を築くことができます。
斉藤様
ストラテジー&オペレーションユニットは、経営戦略の策定から実行まで一貫してフルパッケージで支援するユニットです。強い個同士が組み合わさってさらに価値を高めていける場として、現場のコンサルタントが最も活躍できる環境づくりを重視した運営を行っています。
7つのグループ構成:
・ストラテジー&マネジメントグループ
・ストラテジー&ソーシャルバリューグループ
・サステナビリティ戦略グループ
・人事組織・ダイバーシティ戦略グループ
・デジタル戦略グループ
・ストラテジー&組織・人材開発グループ
・マネジメント&インディビジュアルデザイングループ
経営者やCxOの参謀として、ありたい未来をつくりたいと強く思っている方々とタッグを組んで企業変革を支援しています。ビジョン・中計の策定やポートフォリオ経営、サステナ、新規事業開発、グループ経営、人材マネジメント、DXまで、幅広い経営課題に対応しています。
浅川様
ストラテジー&インダストリーユニットは、戦略に特化したユニットで、クライアントは民間産業系の企業が多いです。AI時代だからこそ、人と人とのコミュニケーションを重視しています。真の意味で経営層と対話して、その人も気づかないような困りごとを見いだし、結果につなげていくことを大切にしています。
5つのグループ構成:
・環境・エネルギー・資源戦略グループ
・高齢社会イノベーショングループ
・ヘルスケア・事業創造グループ
・事業開発・技術デザイン戦略グループ
・通信メディア・ハイテク戦略グループ
上流工程での価値創造に取り組んでいます。それ程大きくはないファームだからこその特長を生かし、どのようなお客さまであっても若手が直接コミュニケーションをとれる機会を意識的に多く設け、成長スピードの加速を図っています。ユニット内のいろいろなエキスパートから学べる環境で、自分のやりたいことを実現するための支援体制を整えています。
2021年のパーパス策定をきっかけに、ありたい未来について社内で対話するように
アクシス
2021年に貴社は“次世代起点でありたい未来をつくる。傾聴と対話で、多様な個をつなぎ、共にあらたな価値をつむいでいく。”というパーパスステートメントを打ち出しています。パーパスを策定した背景、思いを伺えますか。
石田様
当社は設立以来、「強い個の集団」を掲げてきました。それぞれの理想や思いを追求するプロフェッショナルとして仕事をする人たちが集まっているのがリサーチ・コンサルティング部門です。一方で、当社より規模の大きい競合他社の組織力に対して、一人ひとりのプロとしての力だけで戦うのは難しくなってくるという現実も感じていました。「強い個」は良さでもありながら、なんとなく全体としてバラバラなところもあったわけです。
そこで、「強い個」がそれぞれに強い思いを持ってコンサルティングに取り組んでいるという良さを生かしながら、同じ部門で働いている人たちの共通の価値観や、目指すものを打ち出すことができないかという思いがパーパス策定につながりました。
パーパスのポイントは2つあると思います。1つは、それぞれが自身の「ありたい未来」を掲げ、その姿を会社や経営陣が1つに決めないというところです。それぞれが「次世代のために私はこれをやる」という個人の思いを投影できるようにしました。
もう1つは「傾聴と対話」です。「強い個」の集団の中で、互いの異なる価値観や専門性を認め合い、対話を重ねながらコンサルティング活動に取り組むことで、自身もチームもレベルアップしていくと考えています。
私の個人的意見かもしれませんが、コンサルティングは、社内外問わずいろいろな関係者と話し合いながら未来をつくっていくものだと思っています。パーパスを通して、日本総研がそういった人間味のあるコンサルティングを提供している会社だと認知されればうれしいです。
前田様
コンサルティングは、お客さまのニーズのみを汲み取って、それだけを満たしていくという仕事ではありません。日本総研はコンサルタント自分自身がどうしたいのかという思いを大事にしている会社です。そういう意味では日本総研のコンサルタント一人ひとりがありたい未来をきちんと描きながら、お客さまと一緒にそれを実現していきます。その手法として傾聴と対話が必要なのだと、私は理解しています。

アクシス
2021年のパーパス策定以前と策定以後で、社内のメンバーとのコミュニケーションがしやすくなった、などの影響はありましたか。
石田様
2つに分けてお話ししたいと思います。まず1つは、そもそも当社はトップダウンで1つの価値観や仕事の方針を押し付けるような会社では全くありません。その意味で、あまり「パーパスを定めたからこれに従ってやれ」という雰囲気ではなく、「こういうものをつくったけれど、皆さんどう思う?」というスタンスで進めてきたので、この過程においても「傾聴と対話」を重ねてきたつもりです。
もう1つ、「ありたい未来」やパーパスについては、それぞれの組織に考えてほしいと思い、2023年度から社内にパーパス賞という賞を創設しました。それぞれが考えるパーパスを体現したプロジェクトや取り組みをノミネートしてもらい、社員相互で投票して、パーパスに沿ったプロジェクトを表彰しています。賞をきっかけに、それぞれが自分にとってのありたい未来や、プロジェクトの意義について話ができるようになったことは良かったと思っています。
AIの時代だからこそ、対話を通じて経営層も気づかなかった困りごとを見いだし、結果につなげていく
アクシス
リサーチ・コンサルティング部門としてパーパスの位置づけをどう捉えていますか。また、パーパスの達成に向けてどういった役割を担われているのでしょうか。
石田様
当社の社員は、自分の仕事をライフワークと重ねながら、思い描く未来に挑戦している人が多いです。会社がありたい未来を示すのではなく、皆がそれぞれ「ありたい未来」を持ち、それに向かって日本総研を通じてチャレンジできるということが当社の強みです。
ただ一方で、人としての情熱を仲間で共有することも大事にしていくような組織の成り立ち、あり方もそれぞれの社員に伝えていけたらと思っています。パーパスを掲げたからには、パーパスにかなったプロジェクトも実施し、社内外に「ザ・日本総研」のプロジェクトとして発信していきたいと考えています。
斉藤様
世の中には数千人規模のコンサルタントが在籍しているコンサルティングファームもあるのに対し、当社は350人程度の組織規模ですので、大規模な組織戦で戦うことに長けているわけではありません。そうなると、それぞれのコンサルタントが強くないといけません。そういう「強い個」同士が組み合わさって、さらに価値を高めていける場をつくるのが大事だと思っています。
お客さまからはよく「戦略系のコンサルティングファームよりも、日本総研さんと話している方が楽しい」といわれます。提案の一方的な押し付けではなく、自分たちの考えをしっかり伝えつつ、お客さまと傾聴と対話を重ねて共にありたい未来をつくっているというスタンスですので、その点をご評価いただいているのではないかと感じます。
アクシス
3つの部門のそれぞれのユニットがビジネスをどのようにパーパスと紐づけ、パーパス達成に向けて動いていますか。
前田様
そもそもユニットというよりも自分自身が大事にしてきたことは、まさに傾聴です。まずクライアント側の課題や悩み、お立場、背景をきちんと傾聴して把握するのは、私たちの業務の大前提だと思っています。自分たちがやりたいことだけを一方的に押し付けるのはコンサルティングではないと思うので、傾聴して相手の状況を把握したうえで、たとえば行政が思っていることと市民が望んでいるものが一致しないときには、第三者として「こうあるべきではないか」と提示し対話していきます。
これだけ複雑化する社会において、コンサルタント1人が提供できるサービスの量・質には限界があります。複雑化している課題や、問題意識、ニーズにお応えするためには、専門性のあるさまざまな人間を組み合わせて、複合的なコンサルティングを行っていく必要があります。当ユニットだけでも90名前後の人材を抱えていますので、それぞれの専門性の価値を相乗効果で最大化できるのではないかと思っています。
斉藤様
パーパスとの親和性は公共領域のコンサルティングが一番近いと思います。一方で経営コンサルティングは一番遠い位置にあります。決してパーパスと合わないわけではありませんが、パーパスだけでは世の中に対して当ユニットが扱うコンサルティングテーマの価値が響きにくいというのが実際のところです。そのため、私たちは経営コンサルティング そのもので日本総研の良さを伝えていかないといけないと思っています。

アクシス
以前、石田様から、経営コンサルティングを通じて日本企業を良くしていくことが、社員のエンゲージメントを上げることにつながり、それ自体が社会貢献になるのでは、というお話をいただきました。
斉藤様
ありたい未来をつくりたいと強く思っている経営者が世の中にはいます。私たちは経営者や、経営者を支える方々の参謀でありたいと思っています。そういう方々とタッグを組んで企業変革を支援することが私たちの価値観との親和性が高く、日本総研の強みを発揮しやすいと思っています。
「金太郎飴ではない、異能な仲間と楽しくやり抜く」ということが、私たちの共通の価値観だと思います。最近はリモート中心になって、そういった共通の価値観が共有化されづらくなってきていると感じ、価値観の共有のためにもオフィスデーを始めました。強制出社ではなく、「何曜日に来られる人は会社に来よう」という取り組みです。
浅川様
日々の業務の中でパーパスについて議論する機会が多くあるわけではないのですが、ただ私も、自分がいたチームのメンバーや若い人には、結局は人と人で仕事をしている側面が強いので、コミュニケーションが大事だということは伝えてきました。それを会社がパーパスとして言語化してくれているイメージです。
今はコンサルティング業でもAIに仕事を任せれば提案書をつくってくれますし、簡単な調査のアウトプットも出してくれますが、そうすると私たちの価値は、本当の意味で経営層との傾聴と対話を繰り返し、その人やその組織も気づかないような困りごとを見いだして結果につなげていくということです。人と話さないとできないことは、AIに侵食されにくい部分だと思うので、今の時代、より重要になってきています。
自分が成し遂げたいことを、日本総研でのコンサルティングを通じて実現していく
アクシス
貴社で働くことのメリット、やりがいについてお話しいただけますか。
前田様
コンサルティングを通じて自分で成し遂げたいこと、やりたいことを持っている人が、日本総研らしいコンサルタントです。そういう人が集まっている集団に身を置きたいと思うかどうか、に関わってきます。
コンサルタントは基本的に自分たちで事業をするわけではなく、クライアントに伴走し、サポートしていく立場です。そういう中で、クライアントがうまく事業やプロジェクトを達成できた瞬間は、自分のことのように達成感ややりがいを感じられます。
私は、PFIの事業のアドバイザリー業務に長く携わり、竣工式典などにも呼ばれます。設計するのも施工するのも事業者さんですが、自分なりに地図に残る仕事をしたという実感があります。お客さまと一緒に長い時間をかけて1つのプロジェクトに携わって、それが達成できたときには、戦友のような関係性ができます。そういうお客さまとはプロジェクトが終わった後も長くお付き合いが続いていくと思います。そのようなことも、日本総研に限りませんがコンサルタントという仕事の醍醐味です。
斉藤様
現場のコンサルタントが生き生き活動できるファームとしては、おそらく当社が1番だと思います。日本総研のリサーチ・コンサルティング部門は、マネジメントの意向で組織が動くのではなく、現場が中心です。マネジメント側は、現場のコンサルタントが一番活躍できる場をつくることを意識して運営しています。
浅川様
さまざまな分野において社内外から認知されるプロフェッショナルが在籍しておりますので、自分がやりたいことを実現するために、その知見や専門性をとことん生かすことができます。また、小規模のファームということもあり、どのようなお客さま相手でも若手がコミュニケーションをとりながらプレゼンテーションする機会が多いので、入社後早期から経験を積んで成長できる環境です。若手がプレゼンテーションをするときには、事前に周囲が資料や提案の内容などについてアドバイスするので、結果的にOJTになっている面もあります。
逆に、そういった良さを残しつつ組織をどう大きくしていくかは、今後の課題でもあります。

アクシス
組織を大きくしていく中で、どのように質を担保していきますか。
浅川様
研修など共通項でできることはありますが、それぞれがやりたいことをブレさせずに、自分の価値を出すためにどうすればいいかを考えていくと、提案資料の1ページにしても、お客さまとの対話にしても、一歩一歩足元を大切にしていくということ以上のことはありません。そういった文化はしっかり浸透させていきます。
斉藤様
お客さまは要求水準も高く、私たちは考えに考え抜いて、伝え方も含め追求し続けていますが、現場を離れたらわいわい楽しいという雰囲気が大事だと思っています。そのための一環として、私はユニットのメンバーと定期的に対面で会って雑談し、ユニットやリサーチ・コンサルティング部門の価値観を共有してきました。
前田様
今は10~20人超ぐらいのグループを5~6グループずつまとめて、3つのユニットをつくっています。たとえば1人のマネジメントが200人の個を1つの組織でつなぎ合わせようと思っても、それぞれの個性が分からないので現場任せになってしまいます。100人弱ぐらいの単位が、1つの塊として目が届く範囲だと思うので、私たちの組織は、その塊を増やしていくという考え方で大きくしていく必要があります。
アクシス
ユニットが大きくなっていくというよりは、ユニットを多くつくっていくようなイメージでしょうか。
前田様
そうですね。今100人弱ぐらいの塊をユニットとして3つつくったという状態です。まとまるための適正な規模を見極めながら、組織を大きくしていければと考えています。
石田様
個性豊かなコンサルタントがたくさんいる中、「それぞれが一国一城の主のように仕事をしているけれど、それで本当にやりたい挑戦ができているのか」「これからどういうことをしていきたいのか」といったことを話し合いながら、ストラテジー&インダストリーユニットもできました。350人から500人へと規模を大きくしていく過程でも、その狙いを経営層から共有し、現場のリーダー層と話し合いながら進めていこうと考えています。
グループやユニットのつくり方などは、一人ひとりが働きやすいように、そしてパフォーマンスが上げられるように設計していきたいと思っています。
世界企業ランキング低迷を打破する、日本発コンサルティングの挑戦
アクシス
最後に、候補者様へのメッセージをいただけますか。
石田様
当社では、自分のやりたいことや主体性がある方を求めています。その中でも、日本総研で社会課題を解決したいと思う方にジョインしていただきたいです。また、今後は経営コンサルティングや戦略コンサルティングも強化していきたいので、「経営コンサルティングをやりたいけれども、大きい会社に入ると指示を受けて動くことが中心となり面白くないのではいか」と感じている方にも来ていただけたらと思います。
コンサルティング経験者の採用も増やしていきたいと考えているので「今の会社だと自分が本当にやりたいことができなくなってきている」「もっとのびのびとコンサルティングをしたい」という方がいたら、ぜひジョインしていただけるとうれしいです。
前田様
私のユニットは公共系の案件が多いということもあり、霞ヶ関や自治体出身の方は仕事がしやすいと思います。とくに霞ヶ関や自治体にいた頃にコンサルタントと仕事をした経験がある方は歓迎しますし、入社された後も当社になじみやすいと思います。
また、建築やまちづくりのような分野では、設計事務所、ゼネコン、デベロッパーからの転職者も多いです。自分のやりたい分野の仕事や、上流の企画の仕事をしたいという思いの方が目立つ印象です。すでに公共側、民間側へのネットワークがある方は、パーパスにもある「対話」という面でも仕事がしやすいでしょう。
斉藤様
事業会社の経営企画、人事、IT戦略といった部署で勤務し、経営コンサルティング会社への転職を考えている方の選択肢として、日本総研の私のユニットを知っていただきたいと思っています。将来CEO、CFO、またはその参謀として活躍したいという展望がある方にとっては、私たちのような仕事をすることが一番の近道なのではないでしょうか。
浅川様
今でも日本の大企業で、外資系ファームなどに膨大なコンサルティングフィーを払っているところは多いですが、この失われた30年間において、払い続けて本当に結果が出ているかというと、たとえば世界企業ランキングでは日本企業は落ちる一方ではないでしょうか。日本のコンサルティングファームだからこその提供価値を戦略として日本企業にデリバリーすることで、日本のコンサルティングファームとしての価値を広げていくべきだと思っています。そういった志に共感できる人に来ていただきたいです。


東京工業大学大学院総合理工学研究科修了後、日本総研に入社。主にインフラの官民連携を担当し、自治体へのアドバイザー、民間企業向けの参入支援や新たなスキーム構築等のコンサルティングに従事。PFI推進委員会専門委員等の政府委員を歴任。2019年~2022年に内閣府で成果連動型事業推進室参事官。2025年よりリサーチ・コンサルティング部門 本部長としてコンサルティング部門をリード。

早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻修了。大手建設コンサルタント会社を経て日本総研に入社。主にPFI/PPPに関するアドバイザリーサービス・コンサルティング・都市開発、およびまちづくり・地域振興(スポーツ・文化芸術・観光)、スマートコミュニティ・低炭素都市づくりに関するコンサルティングに従事。2024年より都市地域イノベーションユニットのユニット長。主な著書に「コンヴィヴィアル・シティ 生き生きした自律協生の地域をつくる」(共著、2025年4月、学芸出版社)など。

東京大学大学院理学系研究科修了後、日本総研に入社。組織・機能・業務改革コンサルティングを軸に中計策定、BDD、BPR、要員最適化、本社改革、持株会社化、シェアードサービス、グループ経営管理などに従事。2024年よりストラテジー&オペレーションユニットのユニット長として、民間企業向けの経営コンサルティングをリード。2025年4月より神奈川県立病院機構理事(兼務)。

大阪大学大学院基礎工学研究科物理系修了後、大手電機メーカーに入社し情報通信分野(主に光通信分野)にて製品開発に従事後、日本総研に入社。情報通信やテクノロジー分野の経営戦略・事業戦略策定およびその実行支援などに従事。通信メディア・ハイテク戦略グループ長を経て現在、2025年よりストラテジー&インダストリーユニットのユニット長。総務省情報通信審議会総会委員などを兼務。

日本総合研究所は、SMBCグループの総合情報サービス企業として、企業や社会に対する新たな課題の提示・発信(イシュー・レイジング)から、課題に対する解決策の提示と解決への取り組み(ソリューション)、新たな市場や事業の創出(インキュベーション)などを通じ、それぞれの分野で企業や社会が求める創造的な付加価値を生み出しています。

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
株式会社日本総合研究所の求人情報
| 募集職種 | オープンポジション |
|---|---|
| 職務内容 | ~経営戦略コンサルティング~ 【想定選考分野・ポジション】 ~産業系戦略コンサルティング~ 下記に該当する方について、オープンポジションからのエントリーをお願い致します。 【想定選考分野・ポジション】 ~公共系コンサルティング~ 下記に該当する方について、オープンポジションからのエントリーをお願い致します。 【想定選考分野・ポジション】 ■アピールポイント■ 2.民間企業と官公庁を繋げる役割と仕組み 民と官の顧客別に分けない組織編制となっており、専門テーマごとに民と官の両者に関わることができます。 そのため、民と官を繋ぎ社会課題を解決するハブとしての役割を担うことができます。 3.活用価値の大きなSMBCグループ基盤 提案受注はコンサルタントが独自ルートで開拓している事例が多いです。 また、新規顧客開拓に向けてはSMBCグループの豊富な法人ネットワークを存分に活かすことが出来ます。 (なお当社システム部門は、SMBCグループ内の金融システムを一手に引き受けており、SMBCグループ外をお客様としていないため、コンサルティング部門との協業がほぼありません。) 4.やりたい仕事を続けやすい労働環境で離職率が低い 常駐型案件がほぼ無い事もあり、リモートワーク主体の裁量労働が定着しています。自宅をメインにしてオフィス/シェアオフィスを併用する事で、効率的に働ける環境を自ら選択できます。また、ライフイベントに応じた働き方の変化があっても、仕事を続けやすい環境があります。 |
| 応募要件 | ■求める人物像■ ■その他要件■ |