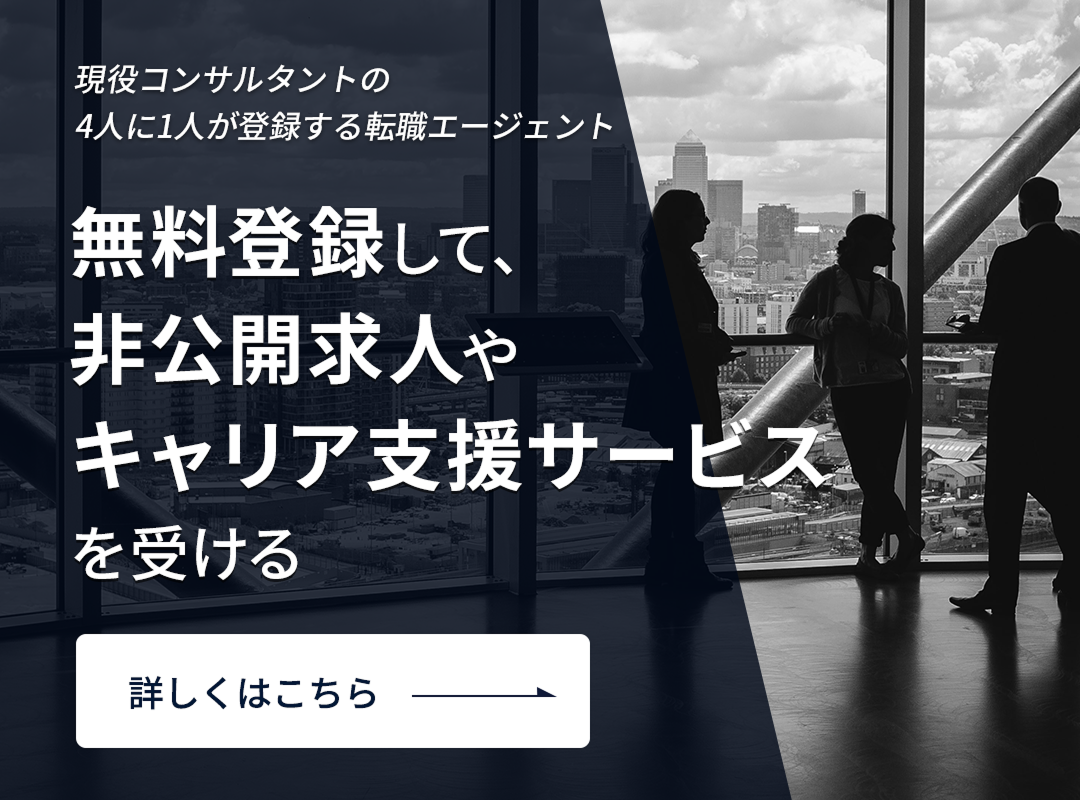株式会社三菱総合研究所 デジタルイノベーション部門 インタビュー/政府デジタル共通基盤構築からDXによる医療・介護分野のサービスの効率化や質の向上まで。国家級DXプロジェクトを動かす三位一体戦略

株式会社三菱総合研究所は、政策立案/制度設計・社会実装(DX推進)、政策評価が一体となって国家規模の社会課題に向き合う総合シンクタンクです。同社のデジタルイノベーション部門は、政策の構想段階からDXを前提とした制度設計を行い、実装後も蓄積された公的データをもとに効果検証し、政策の見直しを行う一連のプロセスを支援しています。公共コンサルティング本部と医療・介護DX本部は、マイナンバーカードのスマートフォン搭載から全国医療情報プラットフォーム創設支援を通じた医療・介護分野のサービスの効率化や質の向上まで国家プロジェクトの最前線で活躍。政策が社会に定着するまでの5〜30年という長期的な視点で継続的に伴走することを強みとしています。
今回は、公共コンサルティング本部を率いる清水充宏様と医療・介護DX本部を率いる松下知己様に、組織の役割や具体的なプロジェクト事例、求める人物像についてお話を伺いました。
※内容は2025年7月時点のものです。
Index
政策立案から制度設計、社会実装まで一連のプロセスに魅力を感じ入社
アクシス
まずは、お二方のご経歴を教えていただけますか。
清水様
2000年に新卒でSIerに入社し、7年間システムエンジニアとして社会実装に向けたシステム設計・開発・運用・保守までを幅広く経験しました。その実務経験を通じて、政策の立案段階から関与し、制度や業務を設計し社会に実装するという最上流からの一連のプロセスを経験したいと考え、2007年に三菱総合研究所に転職しました。
現在は、公共コンサルティング本部で主に中央省庁、地方自治体、独立行政法人などのお客さまに向けて、デジタル化やDXの推進を通じた社会・行政課題の解決に取り組んでいます。

松下様
1999年に新卒で三菱総合研究所に入社し、以来一貫して医療・介護分野の政策コンサルティングに従事しています。もともとは工学部出身で、学生時代に三菱総合研究所のインターンシップに参加したことがきっかけでした。社会保障分野でも工学的なスキルが活かせるということで入社を勧められ、今に至ります。
10年ほど前からは、医療・介護のリアルワールドデータの活用や、制度の運用を支える情報システム構築などの業務が増えてきました。近年は「医療・介護DX」として、制度そのものをデジタルで変革する取り組みも進んでおり、現在は公共イノベーション部門とデジタルイノベーション部門を兼務し、両方の領域を担当しています。

「政策立案/制度設計、社会実装(DX推進)、政策評価」三位一体で社会を変える。三菱総研の組織戦略
アクシス
続いて、三菱総合研究所やデジタルイノベーション部門が担われている役割やミッションについて教えてください。
松下様
三菱総合研究所は、「社会課題を解決し、豊かで持続可能な未来を共創する」というミッションのもと、政策立案/制度設計、社会実装(DX推進)、政策評価を一体ととらえて課題に向き合っています。
社内には、研究・提言機能を担うシンクタンク部門、政策の立案/評価・制度設計を担う公共イノベーション部門、そして私たちが所属するデジタルイノベーション部門があり、これらが密接に協業することで、政策の上流からDXを前提として、社会実装までを一貫して支援する体制を築いています。
政策を適切に機能させるためには、もはやデジタル技術抜きでは成立しません。政策や制度を構想する段階からDXを前提に設計し、実装後もデータをもとに客観的に効果を検証し、必要に応じて見直す。その一連のプロセスを支援することが、私たちデジタルイノベーション部門の役割です。
また、政策や制度が社会に定着するには、5〜10年、あるいは20〜30年と長期にわたるケースもあります。だからこそ、私たちは長期的な視点で継続的に伴走し、社会に定着するまで責任を持って支援し続けます。それが当社のコンサルティングの大きな強みだと考えています。
アクシス
昨今では政策の立案からDX実装まで一気通貫をうたっているコンサルティングファームも少なくありません。その中で御社が早期にその立ち位置を確立できた背景を教えてください。
清水様
当社が政策立案から社会実装まで一気通貫で支援できる体制を確立できた最大の要因は、ここ5年間、全社方針として「VCP経営(Value Creation Process)」を推進してきたことが挙げられます。
それ以前は、政策立案、制度設計、社会実装といったフェーズが社内の各組織においてそれぞれ分断されるケースが見られ、一気通貫の流れが十分に機能していませんでした。
しかし、「社会課題を解決する」というミッションを掲げる中で、当社が持つケイパビリティ、知見やアセットを最大限に活かし、構想から実装、さらには自社サービスを社会に定着させるところまで責任を持って取り組むべきだという意識が社内に浸透していきました。
また、当社は多種多様な分野の専門家集団であり、社会課題解決に資する政策立案や制度設計に長けた人材の宝庫です。そこにデジタル・DXという共通機能を横串で通しながら垂直展開していける土壌は従前より醸成されていたのだと思います。
VCP経営推進の結果として、他本部と連携して進める案件が年々増えており、現在では当本部だけで完結する案件は全体の7割程度で、残りの3割は他部門と協働して取り組んでいる状況です。こうした連携は、業績評価の指標であるKGIやKPIにも組み込まれており、部門を横断した協働が社内で推進され根付いています。
アクシス
政策の立案から実装、さらに効果検証までを見据えると、未来を見据えたバックキャスト的な思考が求められると思います。その難度の高さこそが、御社で取り組む面白さにもつながっているのではないでしょうか。
松下様
そうですね。まさにおっしゃる通りで、未来から逆算してサービスの構想を描いていくのは、非常に難度が高いです。そして各分野の専門家の知見と、DXという機能的なアプローチをどう融合させていくかは決して容易ではないため、常にチャレンジを伴います。
ただ、当社では以前から、政策・制度を構想するだけでなく、実装や運用にまで責任を持って関与する姿勢が現場に根付いていました。自然と部門をまたいで協力し合う文化もありましたので、全社的に一体で取り組む体制が整ってきた今、その文化がしっかりとした下支えになっていると思います。
アクシス
三菱総研グループという大きな枠組みの中で、ナレッジを共有できる点も魅力だと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
清水様
たとえば、三菱総研DCSは、もともと三菱銀行(現三菱UFJ銀行)のコンピューター部門を母体にしたユーザー系のシステム会社です。
私たちは自ら大規模なシステム開発を手掛けるわけではありません。そのため、私たちがシンクタンク・コンサルティングの役割で政策立案や制度設計を担い、三菱総研DCSなどがその実装を支えるITソリューションを担う、そうした役割分担をしながら、密に連携しています。
公共分野ならではの制度面や業務特性の知見も共有し合いながら、案件ごとにグループとして一体で取り組める体制があるのは、大きな強みだと感じています。

デジタルイノベーション部門を支える「公共コンサルティング本部」と「医療・介護DX本部」
アクシス
続いて、各本部についてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
清水様
公共コンサルティング本部のミッションは、国内外の公共分野を対象に、DXの推進を通じて社会課題や行政課題の解決を図ることです。デジタルはあくまで手段であり、私たちの目的は、デジタル技術やデータを最大限に利活用することで社会に良い変化をもたらすことにあります。
本部内には、以下の4つのグループがあります。
まず1つ目は「地域共創DX推進グループ」です。
都道府県や市区町村などの自治体を対象に、業務とシステムの最適化・DX推進を支援しています。例えば、株式会社アイネスと共同開発した『AI相談パートナー』は、自治体窓口の相談業務の質を平準化するためのサービスです。会話をリアルタイムで文字起こしし、過去事例や対応案を即時提示することで、住民サービスの向上および窓口業務の高度化を実現しています。
2つ目は「行政DX戦略グループ」です。
社会インフラ、レジリエンス、モビリティなどの政策立案を所管する他部門と連携し、政策の企画・立案段階からプロジェクトに参画。デジタル活用を前提とした制度設計や運用設計を支援しています。政策が実際に動き出すフェーズでは、このグループが主導し、各分野の専門知見を掛け合わせながら、実装段階まで伴走する体制を構築しています。
3つ目は「デジタルガバメント推進グループ」です。
当該分野では、従来、行政内部の業務高度化・効率化に焦点が置かれてきましたが、現在は行政サービスの受益者である国民・住民の利便性や体験価値向上が重視されています。例えば、2025年6月よりサービスが開始されたiPhoneへのマイナンバーカード搭載プロジェクトでは、制度・技術の両面で制度設計から実装までデジタル庁・ベンダーと連携しながら伴走しました。
4つ目は「海外・貿易物流DX戦略グループ」です
約30年にわたり財務省税関の業務システム最適化に取り組んでおり、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)の海外展開や、ミャンマー中央銀行の機能強化プロジェクトなどにも取り組んできました。日本の優れたシステムを制度と一体的にASEAN・グローバルサウスへ輸出する事業を強化しており、海外における社会インフラの整備にも貢献しています。
アクシス
続いて、「医療・介護DX本部」についてもご紹介いただけますか。
松下様
医療・介護DX本部は、もともとは公共コンサルティング本部の一部でしたが、2021年に医療・介護分野に特化したDX推進本部として新設されました。
背景にあるのは、日本の深刻な少子高齢化という社会課題です。社会保障制度の持続可能性が問われる中、医療・介護の分野はその主たる部分を占めています。この領域で、制度の持続性を高めるためにも保険者及び医療機関、介護サービス事業所の業務の効率化とサービスの質の向上の両立、国民の利便性を向上させながら適切に制度を利用してもらえるようにDXの力をどう活用するか。それが本部の中心的なテーマです。
政府も同時期に「医療DX推進本部」を立ち上げて、制度改革とデジタル基盤整備を重点政策として打ち出しました。当社もこうした政策と密接に連携し、制度の持続性向上に向けたさまざまなプロジェクトに伴走しています。

国家プロジェクトの最前線へ、社会を動かす実感を
アクシス
ここからは、具体的なプロジェクト事例についてお伺いできればと思います。「医療・介護DX本部」での代表的な取り組みを教えてください。
松下様
現在、マイナンバーカードの活用を起点とした医療・介護分野のサービスの効率化や質の向上、情報の利活用に向けたプロジェクトを進めています。マイナンバーカードの健康保険証としての運用は全国で始まっていますが、今後は介護保険や予防接種、母子保健などにも対象を広げ、制度横断で情報を共有・蓄積・活用できる仕組みを構築しています。介護保険、予防接種、母子保健では、すでに複数の自治体でデジタル化の実証が進んでおり、私たちは全体構想の策定から情報システムの要件定義、工程管理までを一貫して支援しています。
具体的な事例として予防接種事務のデジタル化を挙げると、従来は紙で管理されていた接種対象者への予診票や接種券の送付事務や接種記録などがデジタル化されることで、自治体や医療機関の事務負担の軽減が期待されています。また、接種記録がデジタル化されることで個人の接種履歴を確実に管理できるようになり、医師にも正しい情報を共有することが可能になります。また、接種記録を健康保険で受けている医療の情報と紐づけて分析できるようになれば、ワクチンの有効性や安全性の評価につながることも期待されています。
同様に、母子保健や介護保険でも紙を前提とした運用をデジタル化することで、行政、保険者、医療機関や介護事業所、国民が必要な情報を共有しながら制度を適切に運用できるようにデジタル基盤の整備を進めています。私たちは、こうした複数制度を俯瞰した視点から、持続可能な社会保障制度の実現に向けたトータルなDXの推進を支援しています。
医療・介護DX本部のプロジェクトの多くは、厚生労働省をお客様とした国のプロジェクトです。社会全体の仕組みを動かすダイナミズムを体感できるのも当本部の大きな魅力だと思います。
アクシス
とても壮大なプロジェクトですね。公共コンサルティング本部の具体的なプロジェクト事例も教えていただけますか。
清水様
私たちは「行政のデジタル化」を通じて、まず行政内部の制度や業務そのものを変えていくことに取り組んでいます。デジタル庁が掲げる「デジタルファースト」「コネクテッド・ワンストップ」「エンドツーエンド」といった原則に沿って、紙や対面で行われていた手続きを最初から最後まで一貫してデジタルで完結できる仕組みを構築することで、国民の利便性を向上させ、行政内部事務の高度化・効率化の実現を目指しています。
こうした取組は、国の制度設計に関わるところからスタートし、国や自治体の業務現場や国民に有効活用していただくにはどのような制度設計が最適か、オペレーション効果を最大化するためにデジタルをどのように利活用すべきかといった視点で進めているのが特徴です。単にデジタル化するのではなく、制度の目的を実現するために、実運用まで見据えた制度となるよう伴走支援しています。
例えば、マイナンバーカードのスマートフォン搭載により、モバイル端末1つで行政手続きが可能になりました。これにより、申請時に必要だった従来の認証プロセスが簡素化され、国民の利便性が大きく向上することが期待されます。
また、法務省が所管する戸籍制度のデジタル化にも貢献しています。従来は本籍地の自治体でしか取得できなかった戸籍証明書が、マイナンバー連携によって居住地の自治体でも取得可能になりました。
さらに、外務省所管のパスポート申請など他機関と連携する手続きもオンラインで一気通貫に行えるようになりました。従前は役所に赴き紙の戸籍証明書を取得する必要がありましたが、2025年3月からは、戸籍電子証明書を利活用することで、スマートフォンのみでパスポートのオンライン申請が可能となっています。
その他にも、東京都の都市空間を3Dで再現する「都市デジタルツイン」構築にも取り組んでいます。災害時のシミュレーションや都市計画立案などへの活用を想定したこのプロジェクトでは、当社がプライムとしてシステム開発・運用・保守を担っています。
(海外展開の取り組みについては前章をご参照ください)

アクシス
国の案件をメインにやられているコンサルティングファームはなかなかないと思いますが、案件を獲得する際、他のコンサルティングファームと競合することもあるかと思います。その点はいかがでしょうか。
清水様
医療・介護DX分野においては、当社は従前より強みを保有しており、他のコンサルティングファームと競合する場面でも圧倒的優位に立てる領域だと自負しています。
一方、公共コンサルティング本部では、外資系のコンサルティングファームと競合する場面も多々あります。そのような中で当社の強みとなるのが、総合シンクタンクとしてのケイパビリティを活かしたプロジェクト体制の構築力です。
工程管理やPMOといった機能だけでは競合他社との差別化が難しいですが、当社は、将来構想への提言力、制度への深い理解や、予算会計制度への精通、過去の実績、お客様やSIベンダー各社との良好な関係性を通じて、お客様の課題を深く理解し、社会課題の解決に向けて粘り強く伴走する姿勢を評価いただいています。
アクシス
地方公共団体向けと国向けのコンサルティングの割合はいかがでしょうか。
清水様
割合としては、地方が1割に対して国が9割程度になります。
アクシス
まさに国のルールメイキングから関わるダイナミックな仕事ができるということですね。
清水様
やはりまず国の事業にコミットします。戸籍を例にとりますと、戸籍法という法制度は法務省が所管していますが、実際の事務を行うのは自治体です。私たちはまず法務省が戸籍法をマイナンバー対応するための制度設計支援から参画させていただき、それを地方に展開する支援まで一貫して行っています。国で設計した制度を自治体にどのように有効活用していただくかという思考で進めています。
松下様
医療・介護DX本部は、ほぼ100%厚生労働省がお客様ですので、今のところ国向けのコンサルティングに注力しています。
若手に大きな裁量があり、実力次第で早期昇格も
アクシス
では最後に、それぞれの本部が求める人物像についてお聞かせください。
松下様
「医療・介護DX本部」においては、医療や介護の専門知識が必須というわけではありません。もちろん業界知識があれば活かせますが、それ以上に大切なのは、社会の変化や課題に対して好奇心を持ち、学びながら成長していける姿勢だと思います。実際に、医療や介護に携わっていなかった方でも、活躍されているメンバーが多数います。
加えて、私たちはコンサルタントという職業柄、常に「困っているお客様」に向き合います。お客様の悩みにしっかり耳を傾け、伴走する力、そして人を助けることにやりがいを感じられる方は、この仕事に向いていると思います。
スキル面では、比較的大規模な情報システムの構想や、工程管理などのプロジェクトマネジメント的な業務が多いため、SEとしてのバックグラウンドをお持ちの方は、ご自身の強みを活かせると思います。構造的な思考ができる方、ステークホルダーとの調整やコミュニケーションを楽しめる方は、現場で特に頼られる存在になっています。
また、医療・介護DX本部は社内でも新しい組織で、急速に成長しているという特徴があります。そのぶん、若手にも大きな裁量が与えられていて、実力次第では早期昇格も可能です。プロジェクトも長期的なものが多いため、自分が関わった仕事の成果が実社会でどのように活きたか、しっかり見届けられるというのも魅力ですね。
アクシス
裁量が大きいと、若手の方にとっては成長の機会になりそうですね。
松下様
そうですね。もちろんプレッシャーはありますが、それ以上に「社会の仕組みを自分が変えている」という実感を持てる仕事だと思います。医療や介護は、生活の中で誰もが関わるテーマですし、日本全体としても最も重要な社会課題の1つです。それに対して、自分の提案や仕事の成果が実装されていくプロセスに携われるというのは、コンサルタント冥利に尽きる瞬間だと思います。
アクシス
公共コンサルティング本部では、どのような人物像を求められていますか。
清水様
基本的には、医療・介護DX本部と共通する部分が多いですが、違いがあるとすれば、取り扱う分野の幅広さだと思います。前述の通り、私たちは社会インフラやモビリティ、レジリエンス、デジタルガバメント、さらには海外プロジェクトまで、多岐にわたる領域を所管しています。そのため、1人のメンバーが複数のプロジェクトに携わる「マルチアサイン」になるケースも少なくありません。複数分野において興味関心を持って柔軟に取り組み、変化を楽しめる方には非常に向いている環境です。
アクシス
ちなみに、若手の方や中途で入られた方に対するサポート制度には、どのようなものがありますか。
清水様
基本的には、プロジェクトリーダーとの関係性の中で育成を進めていくのですが、新入社員・キャリア入社社員向けに「エルダー制度」を導入しています。これは、比較的年齢の近い先輩社員が1対1でつき、日々のちょっとした悩みから、キャリアの方向性まで幅広く相談に乗る制度です。
また、入社後には「育成計画書」を作成し、その内容に基づいて1年間の育成を進めていきます。本人の希望・関心のあるプロジェクトに手を挙げていただくことも可能で、プロジェクトアサインの際にそうした希望を踏まえて調整しています。
また、全社的にはMRIアカデミーを立ち上げ、コンサルタントとしての基礎スキルから、実践までを体系的に学べる研修制度が準備されています。
松下様
そうですね。医療・介護の分野で頑張りたいという気持ちを持っていても、キャリアに迷うことは当然あると思います。実際に、私たちの本部にも医療・介護分野だけでなく「科学技術のイノベーションにも関心を持っている」という希望を持つメンバーもいます。
医療・介護とは異なる分野ですが、当社内には科学技術のイノベーションを扱う部署があるので、その部署と連携しながら「就業時間の何割を医療・介護に、何割を科学技術に」といった形でアサインを調整し、キャリア形成を支援しています。ですので、一度配属されたからといって、その部門に固定されるわけではなく、キャリアパスは非常に柔軟に設計できます。

アクシス
デジタルイノベーション部門には、どのようなバックグラウンドを持つ方が多く在籍されていますか?
松下様
医療・介護DX本部では、主にベンダー出身の方が多いです。特に、公共分野のシステム開発に関わってきた方や、医療・介護系のシステムに携わっていた方ですね。開発だけでなく、SE営業の経験を持つ方もいます。
清水様
公共コンサルティング本部も、似たような傾向があります。新卒よりもキャリア採用が多く、例えば、国内大手SIベンダー出身の方が目立ちます。前職でシステム開発に携わっていて、「もっと上流で提案や構想から関わりたい」「自分の視野を広げたい」といった動機で来られる方が多いですね。
また、最近は国・地方を問わず公務員の方が、公共分野に根を張りながら、デジタルの力で社会課題を解決したいという思いで転職されるケースも増えています。
松下様
加えて、他のコンサルティングファーム出身の方からもご応募いただいています。そのような方々の中には、シングルアサイン中心の環境に物足りなさを感じていたり、プロジェクトがサイロ化してしまっていることに課題を感じていたりして、「もっと全体を見ながら、目的から逆算してコンサルティングを行いたい」という希望を持って当社を志望される方もいますね。
清水様
「社会を動かすプロジェクトに本気で関わりたい」という強い思いを持った方が活躍している環境です。分野や経歴に関わらず、そういった志を持つ方にとっては、当社の環境は非常にフィットするのではないかと思います。

2000年に新卒で入社したSI企業を経て、2007年に当社入社。入社後は一貫して、公共分野のDX推進に資する戦略立案、基本構想・計画策定、PMO事業を担当。社会・行政課題解決のため、政策立案から制度設計、社会実装まで俯瞰的な視野をもって取り組んでいる。

1999年に新卒で当社入社。入社後は一貫して、医療・介護分野でレセプト情報等のデータ解析に基づく医療・介護分野の政策立案支援、医療・介護分野の大規模データベースの設計・工程管理に従事。近年は政府が推進する医療・介護DXの実現を支援している。
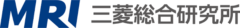
当社は1970年、本格化する情報社会を見据え、三菱創業100周年記念事業としてグループ27社の出資により設立されました。
社会課題解決企業の先駆者として、ミッションとして掲げた「社会課題を解決し、豊かで持続可能な未来を共創する」をステークホルダーの皆様とともに目指していきます。

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
株式会社三菱総合研究所の求人情報
| 募集職種 | 公共DXコンサルタント |
|---|---|
| 職務内容 | <官公庁・自治体> <医療・介護分野> |
| 応募要件 | <官公庁・自治体> ■スキル・資格 [望ましいスキル] [マインドセット] <医療・介護分野> ■スキル・資格 [望ましいスキル] [マインドセット] |