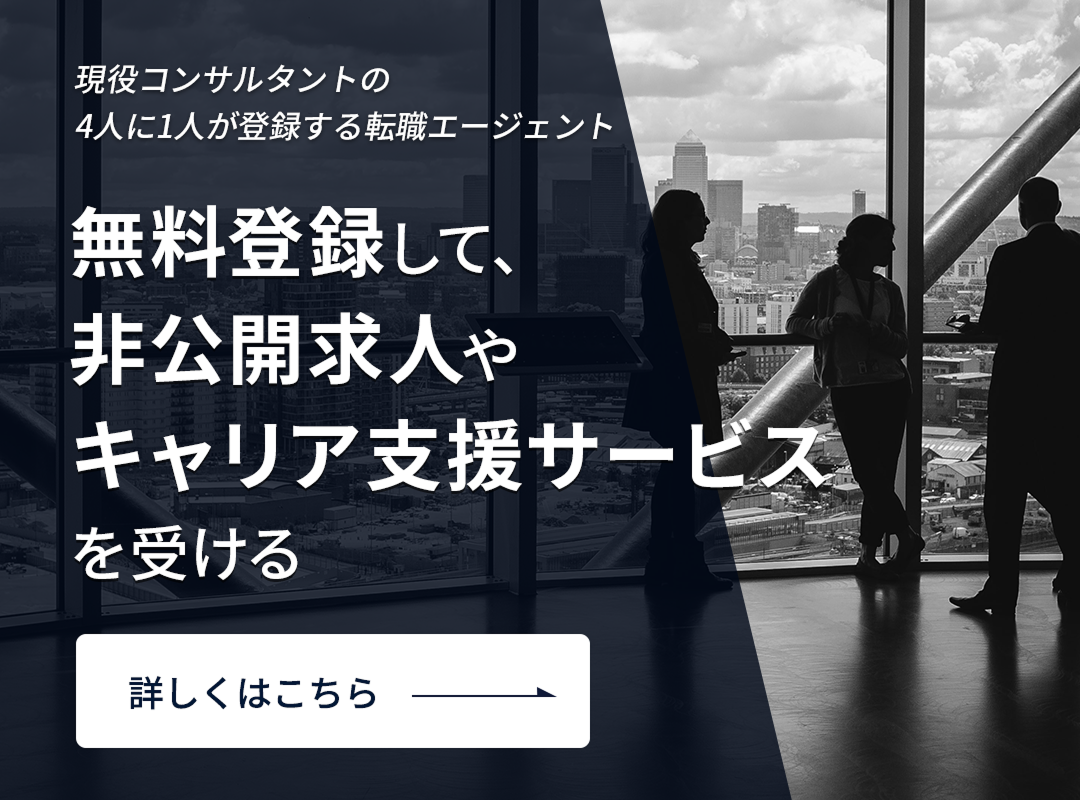株式会社三菱UFJ銀行 AI・データ推進グループ インタビュー/「4万人利用」の社内AI「AI-bow(アイボウ)」を生んだ司令塔の正体

生成AI技術の急速な進歩により、金融業界は新たな変革の波に直面しています。三菱UFJ銀行では、2024年にデジタル戦略統括部内に「AI・データ推進グループ」を立ち上げ、MUFGグループ全体のAI活用をリードする司令塔として機能しています。同グループは現在約50名体制で、約4万人の行員が利用する社内AI「AI-bow(アイボウ)」の運営から、グループ横断で60件を超えるAI導入プロジェクトまで、幅広い領域でAI実装を加速。さらに、世界各地のテック企業との直接対話を通じて最先端の知見を収集し、3カ月に1度、経営陣に直接報告する「AIインテリジェンスチーム」も設置しています。
今回は同グループの次長 島野浩平様、調査役 塚本七海様に、AI活用の現状と課題、そして「AIエージェント100体と協働する未来」に向けたMUFGグループの取り組みについてお話を伺いました。
Index
AI時代はデータが主役、膨大なデータを求めて金融業界へ
江頭
お二方のこれまでのご経歴について教えてください。
島野様
2005年に大学を卒業後、SIerに入社し、インフラからアプリケーション開発、フレームワーク設計、UXデザインやコンサルティングを経験しました。その後、社内公募を経てAI導入支援を中心とするコンサルティング部署に異動しました。
その経験から、AIには何よりデータが重要だと痛感したのです。ただ、SIerではお客様企業からいただく機密データの共有に承認や調整が多く、必要なデータを迅速に得にくい状況でした。そこで、豊富なデータを直接扱える事業会社で挑戦したいと考え、2018年に三菱UFJ銀行に転職しました。
江頭
なぜ御行を選ばれたのですか。
島野様
当時、メガバンクの業務削減のニュースを見て、金融業界が大きな変革期にあると感じました。業務削減にはデジタル化や効率化が不可欠で、裏を返せば、改善余地が大きい分野だと思ったのです。そこで、最も豊富なデータを扱える当行なら、自分の経験を生かして大きな挑戦ができると考えて選びました。

江頭
続いて、塚本様のご経歴を教えてください。
塚本様
2016年に大学卒業後、自動車メーカーで小型モビリティ向けの対話システムの研究開発を担当し、その後、2024年1月に当行へ入行しました。
転職活動を始めた当初、銀行には「堅い」イメージがあって候補には入れていませんでしたが、ご縁あって島野と面談する機会をいただきました。その際に伺った話や今後の取り組みが非常に面白く感じられたこと、そして働いている方々の雰囲気がとても良く、自分に合っていると直感できたことが決め手になりました。

江頭
島野様から見て、塚本様のどういったキャリアが魅力的だったのでしょうか。
島野様
当時、全社的に今後のAI活用を強化するため、リサーチ体制をしっかり整えていこうという動きがありました。塚本の過去の研究で培った知見があることに加え、推進力がある点を評価し、採用を決めました。
江頭
採用においては、金融の知見は必須条件ではないのですか。
島野様
はい、必須ではありません。各現場には金融業務に精通した方がたくさんいますし、私たちはAIの専門家として現場と協力し、知見を活用しながらプロジェクトを作り上げていくことの方が大事だと考えています。
MUFGグループのAI活用をリードする司令塔として2024年に立ち上げ
江頭
御行でAI・データ推進グループを設立された背景を教えていただけますか。
島野様
ここ数年、AIの進化が目覚ましく進む中で、当行ではAI活用を加速させるため、2024年にデジタル戦略統括部を設立し、さらにAI活用の司令塔として「AI・データ推進グループ」を立ち上げました。
江頭
AI活用の推進は、どのような指標で把握していますか。
島野様
大きく2つの指標があります。
1つは生成AIツールの利用率です。MAU(マンスリーアクティブユーザー)をモニタリングしており、最終的には全社員がAIを日常的に使いこなす“利用率100%”を目指しています。
もう1つは案件支援数や業務のリリース数です。AIは単にツールを使うだけでなく、システムに組み込み、業務プロセスとして定着してこそ意味があります。私たちは各部署に入り込み、AI導入のプロジェクトを立ち上げ、実際の業務にどう適用できたかという観点でも指標を設定しています。
江頭
実際に事業を推進するにあたって、課題はありますか。
島野様
現在の1番の課題はリソース不足です。AI・データ推進グループは現在、48名のメンバーが所属し、AIの活用を進めるチームと、BI(データ可視化・分析基盤/ダッシュボード整備)を担当するチームに分かれて活動しています。しかし、銀行内にはまだAIを導入できていない業務領域が多く残っています。今後、こうした領域にも広げていくためには、さらに人材を増やしていきたいと考えています。
江頭
ちなみに、AI・データ推進グループのメンバーは、どのようなバックグラウンドの方が多いのでしょうか。
島野様
コンサルティングファーム出身の方もいれば、事業会社出身の方もいて、業界はかなり多様です。中途入行のメンバーが年々増えており、2025年度の終わりにはおそらく7割程度を占める見込みです。
採用にあたっては、大きく2つのポイントを重視しています。1つは、AIに関する知見や実務経験を持ち、現場での課題感を理解しようとしていること。もう1つは、高いコミュニケーション能力を持ち合わせていること。私たちの目的は、MUFGグループにAIをしっかり適用していくこと。そのためには、各部署と一緒に課題を設定し、ワンチームでプロジェクトを進めていく力が欠かせません。
江頭
なるほど。AIの導入を進める上で各部署とのヒアリングが重要になってくると思いますが、デジタル戦略統括部の中にはDXコンサルティングの役割の方もいらっしゃいます。その方々も各部門にヒアリングをされると思うのですが、AI・データ推進グループとはどのように役割分担されているのでしょうか。
島野様
コンサルティンググループは、営業のように各部門や部署に密着し、幅広い課題をヒアリングしています。そこではAIに限らず、たとえばRPAなどのテーマが挙がることも多いです。その中で特にAIが関わる案件については、私たちAI・データ推進グループに引き継いでもらう形で連携しています。
江頭
実際にAIを業務に適用していくには、社員が持っている知見や暗黙知のようなナレッジを構造化することが重要になると思います。このあたりのデータ基盤の整備も、AI・データ推進グループの担当領域に含まれるのでしょうか。
島野様
データの基盤整備や管理は、デジタル戦略統括部の中のデータマネジメントグループが主に担っています。一方で、当行にはまだドキュメント化されていない属人的な知見やノウハウが多く残っています。今後AIエージェントを本格的に導入するにあたり、こうした暗黙知をどう構造化・明文化し、AIが活用できる形にしていくかが重要な課題であり、それに関してはグループをまたいで現在議論を進めているところです。
4万人が使う生成AI「AI-bow(アイボウ)」を社内に定着させる仕組みづくり
江頭
現在のプロジェクトの事例についてもお聞かせいただけますか。
島野様
現在、当グループの一大プロジェクトとなっているのが、Azure OpenAI Serviceをベースにした社内向けAIエージェントです。社内では「AI-bow(アイボウ)」と呼んでおり、仕事のパートナーのように活用できる存在として位置づけています。質問を入力するとAIが回答してくれる生成AIツールで、現在は当行の約4万人の行員が利用しています(2025年8月時点)。
このプロジェクトでは、システムのバージョンアップや保守、各部署・部門への展開まで、システム企画部と一緒にAI・データ推進グループが担っています。また、「この業務で使いたい」といった現場からのニーズに応えるため、グループ内にカスタマーサクセスの機能を持ったチームを設け、課題のヒアリングや改善提案も行っています。
さらに、単にシステムをつくるだけでなく、実際に使ってもらえるようにすることも重要です。そのため、ポータルサイトの構築や研修プログラムの企画・実施など、社員全体のAIスキル向上を目的としたマーケティング活動も私たちのプロジェクトの一環として進めています。
江頭
どのようなプログラムを進めているのでしょうか。
島野様
最近では、「Hello,AI@MUFG」というプロジェクトも立ち上げました。これは、AIにまだ触れたことがない人も含め、全員が気軽にAIを使えるようにすることを目的とした、いわば社内横断のお祭りのようなイベントです。銀行だけでなくグループ全体、海外拠点も含めて展開を計画しており、AIをより身近に感じてもらうきっかけづくりを進めています。
江頭
具体的にどのようなイベントなのですか。
島野様
まず第1弾が2025年7月から始まる「プロンプトチャレンジ」です。
参加者にお題を出して、それを生成AIに入力し、その結果をみんなで試してみるという企画です。さらに、「役員が実際にどんなプロンプトを出しているのか見てみよう」といった企画や、役員の1週間の仕事を入力して、それを短歌形式で生成AIに出力させるといったユニークな取り組みも計画しています。こうした企画を通じて、「AIってこんな面白いこともできるのだ」というきっかけになれたらと思います。
他にも、中級・上級者向けのイベントとして、実際の業務課題をベースに自分たちでAIエージェントを作ってみるという企画もあります。さらに、チームごとに作ったAIエージェントの精度を競わせるコンペのような取り組みも検討中です。イメージとしては、ポケモンを対戦させるような感覚で、自分の作ったエージェントが他のエージェントと勝敗を競えるようにできたらと考えています。
江頭
それは面白いです。社内にAIの活用を浸透させる上でもぴったりな取り組みですね。そうした活動はチーム内にエンジニアメンバーが多いからこそできるのですか。
島野様
そうですね。とはいえ、最近では自然言語処理の進化もあって、日本語で入力するだけでそれなりのアプリを作れるようになったので、こうした企画も実現しやすくなっています。

最先端テック事情を集めるため海外出張を行い、3カ月に1度社長・頭取とディスカッション
江頭
AI・データ推進グループでは、海外出張もあると伺っています。具体的にはどのような活動をされているのでしょうか。
島野様
MUFGではAIの最前線の動きを常にキャッチアップするため、「AIインテリジェンスチーム」を立ち上げました。塚本がリーダーとなり、国内外のテック企業に直接アポイントを取り、現地を訪問してCxOクラスの方々と対話し、最前線の知見を収集しています。
これまでにも、シアトルやサンフランシスコといった大手テック企業が集まる地域を訪れ、最新トレンドや今後のロードマップを直接ヒアリングしてきました。今後は中国などアジアの先進的なAI企業にも足を運び、世界各地の情報をさらに幅広く取り入れていく予定です。
収集した情報はリポートとしてまとめ、3カ月に1度、経営層に直接報告します。MUFGグループ全体としてトップダウンでAI導入を推進しているため、経営陣はこれらのリポートをしっかり読み込み、毎回鋭い質問や新たな提案が飛び交います。こうした会議にはMUFGの亀澤社長や三菱UFJ銀行の半沢頭取、各役員が参加し、塚本がメインスピーカーとしてディスカッションをリードしています。
江頭
それはすごくプレッシャーがありそうです。
島野様
はい(笑)。毎回緊張しますが、やりがいがあります。1時間ほどの会議で、まず30分調査内容を説明し、その後は経営陣とディスカッションを行っています。
江頭
実際に海外のAI最前線の企業の方たちと話す中で、印象に残ったことや新たな気づきはありますか。
塚本様
普段の会議や公開情報だけでは得られないような、リアルな話が聞けるのが大きいですね。特に現場のエンジニアや技術サイドの専門家から、今のAIの実情や将来の展望について率直な意見を伺えるのはとても貴重です。
こうした情報はリポート化するだけでなく、経営層とのディスカッションを通じて会社全体で理解を深めるようにしています。その上で、どの情報をどのプロジェクトや施策に生かせるかをチーム内で連携しながら素早く検討し、次のアクションにつなげています。

全社で60件超のAIプロジェクト、会社からは多額の投資もあり挑戦の機会は拡大中
江頭
プロジェクトはどのように組成されるのでしょうか。
島野様
まずプロジェクト全体の取り組みについてですが、2024年に全社横断のAI導入プロジェクト「AI-PT」を立ち上げました。これは各部門の戦略に直結するAI導入プロジェクトを推進するもので、銀行内だけでも20件以上、グループ全体を含めると60件を超える規模になっています。これらのプロジェクトは、各本部と連携しながら進めています。
AI・データ推進グループとしては、スタートアップが持つAI関連ソリューションを活用し、必要に応じて改善点をフィードバックしながらプロジェクトを進め、最終的に業務への実装までつなげていくケースが多いです。
江頭
アサインはどのように行われるのでしょうか。
島野様
基本的には、メンバーの特性やこれまでのバックグラウンドを踏まえてアサインしています。たとえば、コンサルティングファーム出身の方であれば、PMOスキルや企画力に長けている方が多いので、そうした強みを生かせる案件に入ってもらいます。
また、システム開発の知見を持つ方であれば、プロダクトマネジャー的な立場で機能改善などを担当してもらうこともあります。 1人あたりが関わるプロジェクトは平均で1〜2件ほどですが、マネジメントの立場になると5件前後を同時に見ることもあります。
江頭
さまざまなプロジェクトがあるということは、それだけ活躍のフィールドも広いということですね。
島野様
はい。ステップアップできる場は本当に多くあります。たとえば、最初は開発フェーズから入って経験を積み、その後は上流工程を希望すれば、他社との連携を構想したり、ゼロからシステムを企画したりする段階から挑戦することも可能です。会社からも多額の投資をいただいているからこそ、挑戦する機会を広げ、しっかり成果につなげていきます。

AI導入の実行力×推進力、現場を動かす力がある方を求めている
江頭
今後の採用を拡大していきたいということですが、今1番求めているのは?
島野様
そうですね。特に、AIの導入プロジェクトを実際に動かしてきた経験を持つ方を求めています。情報収集だけでなく、プロジェクトの企画、予算の見積もり、体制づくりやスケジュール設計、さらに関係部署やステークホルダーを巻き込んで推進できる方が理想です。
加えて、大企業でのご経験がある方は、決裁や稟議の流れ、部署間のパワーバランスを理解されている分、スムーズに動けるケースが多いと思います。逆に、スタートアップのようなスピード感を前提にしていると、銀行ならではの慎重な意思決定プロセスとの間にギャップを感じる場面もあるかもしれません。
江頭
具体的にどのような働き方になるのでしょうか。
島野様
働き方にはどうしても波がありますが、その分、裁量も大きいです。たとえば塚本の場合、3カ月に1回リポートを提出するため、直前は執筆作業に追われて忙しくなります。
また、プロジェクトの立ち上げ時には稟議書を書いたり、承認を得たりするための書類作成などが重なるので、一気に忙しくなる時期もあります。
とはいえ、皆それぞれが長期的なスケジュールを見ながらメリハリをつけて働いていますし、自分の判断で動ける裁量はかなり大きいと感じています。出社に関しては、現在週2日を目安に設定し、顔を合わせてコミュニケーションを取る時間も大切にしています。
江頭
オンボーディングはどのように行っているのでしょうか。
島野様
基本的にはメンター役の担当者をアサインしています。たとえば、日々の就業管理の入力方法や発注、決裁を行う際の手続きなど、実務の細かい部分を担当者から逐一レクチャーしてもらう形です。

能力拡張こそAIの真価、1人で100人分の生産性を実現
江頭
今後の未来についてもお伺いします。島野様が2018年に入社されてから、データ活用を起点に金融・銀行業界はどのように変化してきたと感じられますか。そして、これから先の未来については、どのような姿を思い描いていらっしゃいますか。
島野様
私が入行した当時は、まだAIに特化したチームは存在せず、BaaS(Banking as a Service)やAPIを担当するチームの中に、AIを担当している人が数人いる程度でした。データも十分に整備されておらず、「AIで何かやりたい」という声はあっても、理解や環境が追いついていないのが実情でした。
そこから少しずつAIツールが導入され、活用の土台が整っていくうちに、この7年間で現場の理解度が大きく向上しました。今では、むしろ自らAIを使いこなし、AIネーティブな組織に進化させていこうという強い意欲を持った方々が銀行内にたくさんいます。
未来についてですが、これからはAIエージェントの導入がさらに進んでいくでしょう。ただし、人を減らすことが目的ではありません。AIを生かして、人の能力や判断を拡張し、より良いアウトプットを出せるようにしていくことが重要です。
つまり、AIを道具としてではなく共に働くというイメージです。AIエージェントが相棒や頼りになる上司のような存在となり、人と作業を分担しながらアウトプットを磨いていく。そんな未来が訪れるのではないかと思います。
江頭
世の中が紙文化からデジタルにシフトしていく中で、さらにAIエージェントを活用した提案がどのような形になるのか、これからの可能性にとても興味があります。一方で、具体的なイメージをつかむのが難しい部分もあります。未来像において、どのようにお考えですか。
島野様
AIエージェントの利用には大きく分けて2つの方向があります。1つはお客さまと直接やり取りするエージェント、もう1つは行内業務をサポートしてくれるエージェントです。
前者については、万が一間違いがあればお客さまにご迷惑をかけるリスクが大きいため、実用化はもう少し先になると見ています。ただし、将来に向けてどうすれば精度を高められるか、間違いを減らせるかという研究は継続的に進めています。
後者については、すでに活用の可能性が高いと考えています。たとえば提案書の作成や提案ストーリーの構築といった場面です。行内には「こういうお客さまにこういう話をしたら盛り上がった」といった過去の事例が豊富に蓄積されています。これらの知見をもとに、AIが壁打ち相手となって提案内容を考えるサポートをしてくれる。そうすれば、1から手探りで考えるのではなく、AIと一緒に検討を進められるので、より質の高い提案を短期間でつくれる未来が見えてきます。
江頭
先ほど、AIの導入は人を減らすことが目的ではないとおっしゃっていましたが、もう少し詳しく教えていただけますか。
島野様
AI導入は単純に業務を削減するというよりも、むしろ新しい業務や付加価値の創出につながると考えています。AIを使うことで1人が担える作業量や質が格段に向上すれば、結果として会社全体の売上やサービスの幅を広げることができます。
将来的にAIネーティブな組織が実現すると、AIの活用度は2倍、3倍、4倍と拡大していく可能性があります。先ほど「AIと働く」と申し上げましたが、AIは人と違って必要に応じて増やせる存在です。たとえば、私が同時に5人、10人、さらには100人のAIエージェントと協働できるようになれば、生産性は何十倍、何百倍というレベルまで高められるでしょう。最終的には、そうした世界を目指すことが私たちのゴールの1つです。
最先端な技術力とセキュリティー技術が体得できる金融業界の魅力
江頭
採用において、先ほど金融業界の経験は必須ではないとのことでしたが、非常に高い水準が求められる金融業界での経験は、候補者の市場価値をさらに高めるのではないかと感じています。その点について、どのようにお考えでしょうか。
島野様
そうですね。多くのお客さまにサービスを提供しているからこそ、求められる成果の水準は非常に高いです。課題を深く理解し、確実な解決策を導き出すことが求められる。そのチャレンジが大きな成長や経験につながると感じています。
さらに、情報セキュリティーやコンプライアンスといった厳しい制約の中でAI導入を進める経験は、他業界では得がたいものです。AIプロジェクトを推進しながらも、セキュリティーエンジニアのような専門知識を自然と身につけることができる。こうした環境は金融業界ならではの魅力だと思います。
江頭
塚本様は、御行にご入行されてどのように感じられていますか。
塚本様
大きく2つあります。1つ目は、想像以上に最先端の技術に触れられることです。AI領域でキャリアを築く上で、こうした環境に身を置けることは非常に貴重だと感じています。
2つ目は、技術力が確実に磨かれることです。銀行が扱うデータは非常に複雑で非構造化データも多く、長年蓄積された膨大なデータを活用しなければなりません。単にAIを導入するだけでは成果につながらず、課題を多角的に捉え、深く考え抜く力が求められます。こうした経験を積めるのは当行だからこそ、自分のキャリアに確実に生かせると実感しています。


2005年に新卒で大手SIer入社。高度なミッションクリティカルシステムの開発経験を積んだのち、コンサルティング部署に異動して主に電力業界、物流業界のAI導入・開発のコンサルティングに関わる。事業会社で直接データに触れる場を求め、2018年に三菱UFJ銀行に入行。2024年にデジタル戦略統括部が発足し、AI・データ推進GrのヘッドとしてAI戦略、導入、オペレーションまで全般を手掛ける。

2016年に新卒で自動車メーカーへ入社。遠隔操縦ロボットのソフトウェア開発や、小型モビリティに搭載する対話システムの研究開発に従事。その後、キャリアアップを目指して転職活動を行い、2024年に三菱UFJ銀行へ入行。現在はデジタル戦略統括部 AI・データ推進Grにて、最新AI技術の調査と行内への導入推進を担当している。

1919年(大正8年)8月15日設立、従業員数は銀行単体で31,756名、国内421・海外104の拠点を有する(従業員数と拠点数はいずれも2024年3月末時点)
三菱UFJフィナンシャルグループの中核企業として、「預金」「融資」「決済」の主要業務を中心に、あらゆる金融サービスを国内に限らずグローバルに事業を展開。

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
株式会社三菱UFJ銀行の求人情報
| 募集職種 | AIを活用したDX施策の企画・推進 |
|---|---|
| 職務内容 | 【業務内容】 [共通] ① ② ③ |
| 応募要件 | 【必須スキル】 【歓迎スキル】 |