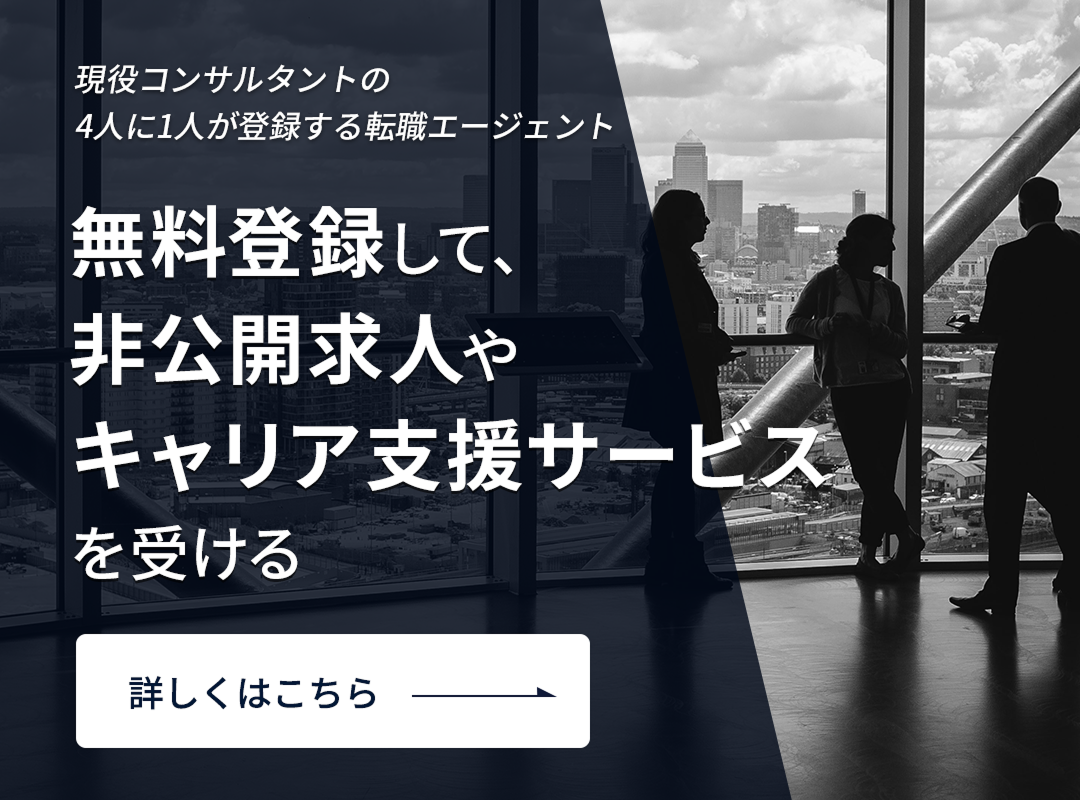株式会社三菱UFJ銀行 カスタマーサービス推進部×デジタル戦略統括部 インタビュー/「AIと共に進化する顧客体験」──コンタクトセンターDXから描く未来の形

デジタル技術の急速な進歩により、金融業界は顧客体験の根本的な見直しを迫られています。三菱UFJ銀行では、2024年4月にカスタマーサービス推進部を新設し、リアル・デジタル・リモートという3つのチャネルを横断的に統括する体制を構築。さらに、デジタル戦略統括部と連携し、AIエージェントの導入やVOC(顧客の声)の高度活用など、次世代のカスタマーサポートを目指した大規模なDXプロジェクトを推進しています。
年間数百万件規模の顧客接点を持つコールセンターを起点に、「カスタマーサポート」から「カスタマーサクセス」への転換を図る同行の取り組みは、金融機関の顧客体験設計における新たなベンチマークとなりつつあります。組織再編により実現したチャネル間連携の強化、多様なバックグラウンドを持つ人材の積極登用、そして数十億円規模のシステム刷新プロジェクトまで、変革期ならではのダイナミズムが随所に見受けられます。
今回は、カスタマーサービス推進部から小島健之様、天川貴志様、デジタル戦略統括部から山本浩太様、渡邉直人様にご参加いただき、組織横断型のDX推進体制や具体的なプロジェクト内容、そして銀行業界における働き方の変化について詳しくお話を伺いました。
Index
異なる経歴の4人が語る「銀行キャリアの幅広さの魅力」
江頭
今回は、三菱UFJ銀行のデジタル戦略統括部とカスタマーサービス推進部から4名の方々にお越しいただきました。まずは、皆さまのご経歴を教えていただけますか。
小島様
現在、カスタマーサービス推進部リモートチャネルGrでコンタクトセンターDXを推進している小島です。2010年に総合職として新卒入行し法人営業を経験した後、研修を通じて興味を持ったマスリテール企画に携わりたいという思いから、住宅ローン企画部署への公募にエントリーし、配属となりました。
その後、組合専従や、デジタルマーケティング等、各種マスリテール向け商品の非対面推進に従事し、2020年からはデジタル企画部(現・デジタル戦略統括部)にてMUFGのAI活用推進や、コンタクトセンターシステムのクラウド化等を検討、2023年にはコールセンター(現・カスタマーサポートオフィス)へ異動し1年間現場からDX推進・CX向上を牽引しました。
2024年4月には、組織再編でカスタマーサービス推進部が新設され、最初は企画Grにて全体チャネル戦略を策定した後、2025年1月からはリモートチャネルGrへ部内異動し、現在に至ります。

天川様
同じくカスタマーサービス推進部のリモートチャネルGrに所属している天川です。新卒で人材派遣会社に入社し、営業をはじめ、求人作成や面接、配属後の管理、契約・請求対応など、一連の業務を幅広く経験しました。
その後、コールセンターベンダーで営業職に転職。主に銀行や生命保険などの金融業界のクライアントを担当し、複数のコールセンター運営に携わりました。そうした知識や経験を生かしながら営業以外の立場から顧客体験の設計に関われる道を探していたところ、タイミングよくお声がけいただき、2025年3月に入行しました。
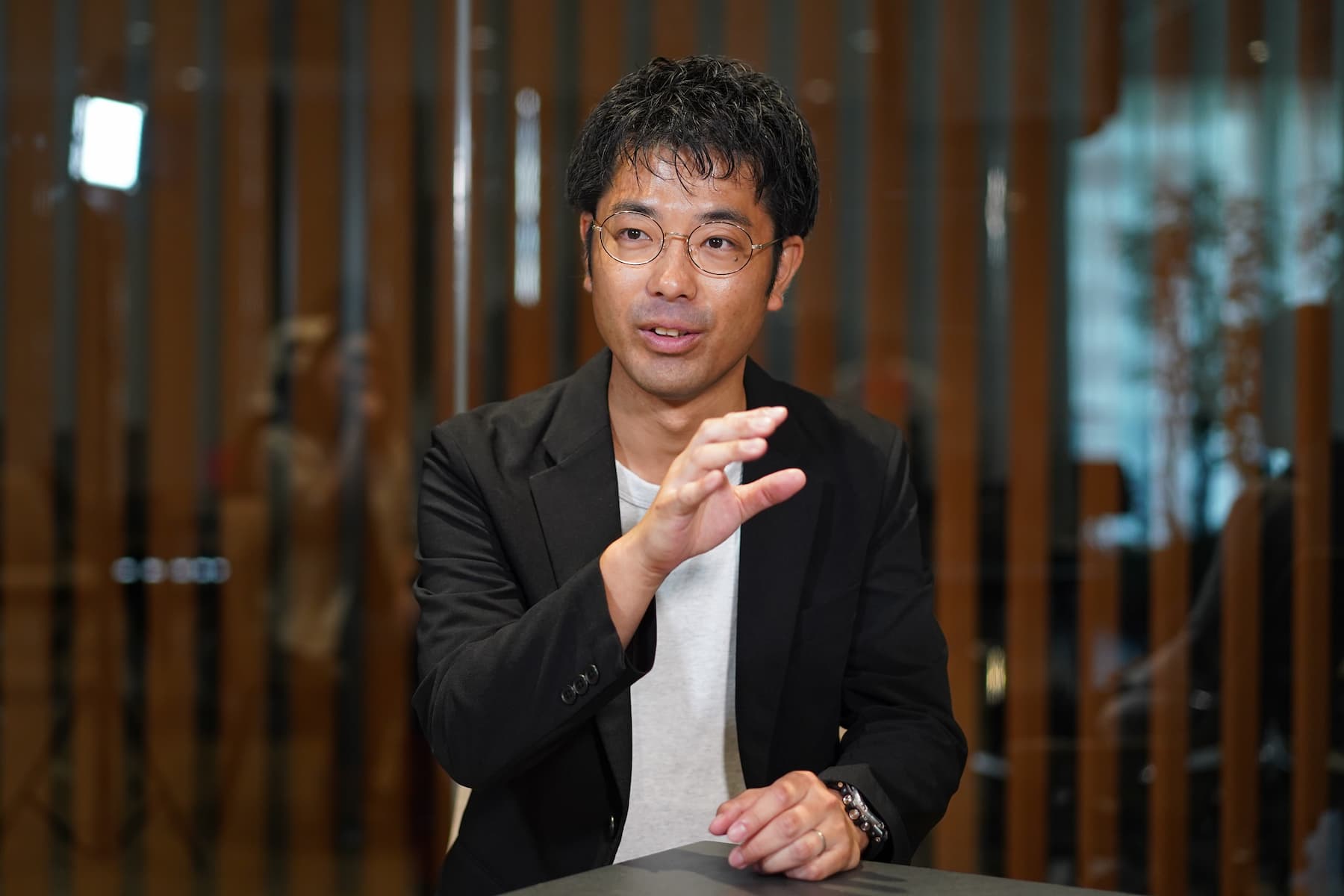
江頭
続いて、デジタル戦略統括部のお二人にも伺えますか。
山本様
デジタル戦略統括部の山本です。2011年に当行へ入行しました。大学では理系を専攻しており、就職活動では、当時のリーマンショック後の厳しい経済状況の中で、「日本経済を支える仕事がしたい」と考えたことが銀行を選んだ理由です。
入行後は法人営業を経験し、その後は大企業担当の営業や営業企画を担当。営業企画では、現場の声をもとにデジタルを活用した業務改善にも取り組みました。現在はデジタル戦略統括部の立ち上げに伴い、コールセンターや法人領域のデジタル化を支援するチームに所属し、約1年半になります。

渡邉様
同じくデジタル戦略統括部の渡邉です。2018年に新卒で共済に入社し、業務部で火災・建物保険など損保系の支払い業務に従事していました。災害時には現地で災害対策本部を立ち上げ、査定対応を行うなど、実務から全国的な企画推進まで幅広く経験しました。
その後、大手日系グループの生命保険会社へ転職し、企画部門でベンダーのBPR(業務改革)やSNS施策などを担当。業務プロセス全体を見直し、より効率的な運用へと導く業務に携わりました。
30代になるタイミングで、今後はより大きな事業基盤で企画領域を深めたいと考えるようになり、銀行の中でも変革期にある三菱UFJ銀行の環境に魅力を感じて2025年5月に入行し今に至ります。

チャネル横断の再編、カスタマーサービス推進部の誕生
江頭
続いて、2024年4月にカスタマーサービス推進部の概要や再編が行われた背景について教えていただけますか。
小島様
カスタマーサービス推進部は、銀行におけるすべての顧客接点として①リアルチャネル(店舗・ATM)、②デジタルチャネル(インターネットバンキング・各種アプリ)、③リモートチャネル(コールセンターや事務オペレーションバックオフィス等)を横断的に統括する組織です。
これまで各チャネルは別々の部署で企画・運営されていましたが、実際のお客さまはチャネルをまたいで銀行サービスを利用されるため、お客さまにストレスない快適・便利な銀行体験を提供するべく、2024年にカスタマーサービス推進部として再編・新設されました。現在は、3チャネルの特性を生かしながら、最適な組み合わせ=ベストミックスでのサービス提供に取り組んでいます。
江頭
再編後、率直に現状はどう感じていますか?
小島様
チャネル間の連携を意識して顧客体験を設計する機会が明らかに増えましたね。ただ、まだまだ改善の余地はあると感じています。
なかでもリモートチャネルGrはコールセンターを所管しており、年間数百万件規模でお客さまよりお電話・お声をいただいています。そこには顧客体験をより良くするためのヒントがたくさん眠っていると感じており、そうした声を生かしながら顧客体験の改善を加速させていきたいと考えています。
江頭
具体的にどうやって改善していくのでしょうか?
小島様
私たちが目指しているのは、「お客さまが電話をしなくても済む世界」です。多くのお客さまはまずWebで調べて、それでも解決できなかった場合に電話をかけてこられる。デジタルチャネルで完結できず、リモートチャネル(コールセンター)に移ってきているわけです。
そこで重要なのがお客さまの声=VOC(Voice of Customer)。コールセンターに寄せられる膨大なご意見・ご要望をしっかり拾い上げ、WebサイトやFAQ、アプリ等のデジタルチャネルや、営業店・ATM等のリアルチャネルの改善につなげていくことが不可欠です。
また、実際にお客さまと日々向き合っている従業員の声=VOE(Voice of Employee)にも多くのヒントがあります。オペレーターからの気づきや提案も積極的に取り入れ、VOC・VOEを起点とした改善サイクルを回していくことが、今後ますます重要になると考えています。
江頭
こうした再編の動きに伴い、最近では組織内部の多様化も進んでいると伺っています。
小島様
実際に、カスタマーサービス推進部内ではキャリア採用の方が増えてきていますね。以前は銀行出身者が中心で、行内の常識に縛られがちな側面も一定あったかと思いますが、天川のように外部のフラットな視点を持つ人材が加わることは、組織にとって非常に大きな意味があります。
さらに、カスタマーサービス推進部には、他部署と兼務する形ですが2つの「部内室」(専門性の高いチーム)が存在します。1つはカスタマーエクスペリエンス・デザイン室で、ここにはデザイナー等、顧客体験設計を専門とするキャリア採用の方々が多く在籍しています。
もう1つはデータ・マーケティング室で、マーケティングやデータサイエンスの知見を持つ人材が集まっており、こちらもキャリア採用を積極的に行っています。
このように、専門性を持った多様なバックグラウンドのメンバーが共に働く環境が整いつつあるのも、再編後の大きな変化の1つだと感じています。

デジタル戦略統括部が担う“横ぐし”の役割、各部門と共創
江頭
続きまして、デジタル戦略統括部の概要と、現在の役割について教えていただけますか。
山本様
デジタル戦略統括部は、三菱UFJ銀行全体のデジタル化・DXを推進し、業務の高度化・生産性向上や新たな金融サービスの創出を担う組織です。
その中で私たちが所属しているのは「コンサルティンググループ」で、各ビジネスを所管する部署と密にコミュニケーションを取りながら、意図を理解し、先回りしてサービスをお届けするという、まさに接点として機能する役割を担っています。いわば、横ぐしの立場から「どのような選択が最適か」といった観点で、アドバイスや支援を行うのが私たちのミッションです。
江頭
カスタマーサービス推進部とはどのような形で関わっていますか?
山本様
現在、カスタマーサービス推進部には私たちのチームから4名が参画しています。生成AIの活用の可能性や、「5年後のコンタクトセンターはどうあるべきか」といった未来志向のテーマについても、現場に入り込んでプロジェクトを一緒に推進しています。
江頭
プロジェクトはどのように進めているのでしょうか?
山本様
プロジェクトはアジャイル体制で進行していますが、ビジネス面での意思決定はカスタマーサービス推進部が担います。私たちは、デジタル領域での知見提供が主な役割ですが、型にはめずに、プロジェクトごとにどのような役割を担うかを小島たちと相談しながら、適切な体制を構築して進めています。
江頭
ちなみに、アサインメントはどのように決めているのでしょうか?
山本様
基本的には、本人の希望や関心を聞いたうえで、それぞれの経歴や強みに応じてアサインしています。たとえば、テクノロジーに詳しいメンバーであれば、生成AIエージェントのようなテーマに関わり、「今後、AIがどうやってお客さまの発話に対応していくべきか」「そのためにどういった商品設計が必要か」といったプロジェクトに参画してもらいます。また、プロジェクト推進力が高い方には、スクラムマスターとして、アジャイルの現場を采配してもらうケースもあります。

VOCデータ整備、AIエージェント、コンタクトセンター刷新など大規模プロジェクトが進行中
江頭
続いて、カスタマーサービス推進部とデジタル戦略統括部が現在協働で進めているプロジェクトについて教えていただけますか?
山本様
まず、足元の取り組みとしては、コールセンターに寄せられるVOC(Voice of Customer=お客さまの声)の利活用に注力しています。お客さまの発話内容を正確にテキストデータとして蓄積し、それを要約したり、検索性を高めるためにタグ付けを行ったりと、分析に適した形に整えていく必要があります。
また、そのテキスト化されたデータを分析するための基盤整備や、そこから得られた示唆をもとにホームページやFAQの改善につなげる仕組みづくりも進めています。
さらに中長期的には、「AIエージェントが応対を担う世界」に向けた取り組みも始まっています。たとえば、コールセンターでよくある「1番は口座開設、2番は資産運用…」といったIVR(自動音声応答)の煩わしさを解消するため、AIが最初にお客さまの要件を聞き取り、適切なオペレーターへスムーズに振り分ける仕組みを、ファーストステップとしてスモールスタートで導入予定です。
小島様
加えて、私たちが現在最も注力しているプロジェクトの1つが、次期コンタクトセンターシステムの刷新です。音声基盤やCRM基盤を、3~5年後をめどに新しいシステムに乗り換えることを想定しており、これは中長期で取り組む大規模プロジェクトになります。
このプロジェクトはリテールインバウンド領域に限らず、アウトバウンド業務や法人部門も含めた全社的なもので、システム部門とも連携しながら進めているところです。
また、顧客体験をさらに向上させるために、コンタクトセンターDXの一環として、たとえばコブラウズ機能(オペレーターが顧客と同じWeb画面を共有して案内・操作補助を行う機能)の導入や、チャットシステムの高度化といった領域にも着手しようとしています。
江頭
AIエージェントについて「今年が本格始動の年」と捉えている企業も多いと思いますが、御行ではどのような位置づけでプロジェクトを進めているのでしょうか?
小島様
MUFG全体としてもAIの活用を前提とした業務設計への意識が高まっておりますが、コンタクトセンター領域においては、まさにこれから本格的に取り組みを進めていく段階です。AI技術の進化により、カスタマーサポート領域との親和性が非常に高くなってきており、銀行としても積極的に導入していくべき領域だと考えています。
顧客体験の向上という観点はもちろん、コールセンターの採用や育成が年々難しくなっている背景もあり、人とAIが共存する仕組みを構築していくことは、持続可能な組織運営のためにも不可欠です。こうした状況を踏まえると、「AIをどう使うか」ではなく、「AIとどう共に働くか」を考えていくフェーズに入っていると感じています。
一方で、コンタクトセンターでのAI活用は他の金融機関や民間企業と比べると、私たちは “後発”の立場です。その自覚を持ちながら、いかにスピード感を持ってキャッチアップし、独自の価値を出していけるかが、今後の大きなチャレンジだと捉えています。
変革期の今だからこそ味わえる、数十億円規模プロジェクトの意思決定
江頭
ここまで、さまざまなプロジェクトやチャレンジについて伺ってきましたが、改めてカスタマーサービス推進部で働く中で感じている魅力や面白さについて教えていただけますか?
小島様
現在取り組んでいるプロジェクトの中には、数十億円規模の非常に大きなものもあります。そうしたプロジェクトの最終的な意思決定を自分たちが担っていくという責任は大きいですが、その分、非常にやりがいもあります。もちろん、チャレンジングな側面も少なくありませんが、「大きな仕組みを自分たちで動かしている」という実感は、この仕事ならではの醍醐味だと感じています。
天川様
まさにそうですね。私も前職との比較になりますが、コールセンターを含めてここまでのスケールで展開している組織はそう多くないと思います。その大規模な現場で使われるシステムを設計・導入していくわけなので、1つ1つの判断が非常に重要になりますし、経営層からの注目度も高いです。
さらに、関わる部署が多岐にわたるため、「誰がどのようにこのシステムを使うのか」を整理しながら進めていく必要がある点も大きな特徴です。簡単なことではありませんが、その分、長期的に向き合っていく面白さや、プロジェクトが形になっていくワクワク感を日々感じながら取り組んでいます。

江頭
デジタル戦略統括部で働くうえでの魅力や面白さについて教えていただけますか?
山本様
私たちの部署では、ビジネスサイドと一緒に課題を考え、多様な選択肢の中から最適なものを提案し、共に意思決定していけるという点に、大きなやりがいを感じています。
また、経営サイドからも「積極的にチャレンジしてほしい」というスタンスで背中を押してもらえるので、新しい取り組みに対して前向きに動ける環境があります。もちろん、金融という領域上、慎重さが求められる場面もありますが、アジャイルで素早くプロトタイプを作り、実際の反応を見ながら改善していく。そういった“動きながら考える”ような取り組みが許容されているのは、非常にチャレンジしやすいと感じています。
江頭
渡邉さんは、入行されてまだ3〜4カ月とのことですが、入ってみてのギャップなどはありましたか?
渡邉様
いい意味でのギャップはすごく感じています。まず、取り組めるフィールドが本当に幅広いので、「これから長く腰を据えてキャリアを築いていきたい」と思えるだけの魅力があると実感しています。
それに、スキル面で優秀な方が各領域にいらっしゃるのはもちろんですが、何より「人が柔らかい」という印象が強いですね。もっと堅い文化なのかなと思っていたのですが、実際はとても話しやすく、相談もしやすい雰囲気です。変革期ということもあり、組織の雰囲気や働き方も大きく変わってきていると感じています。

江頭
そのあたりの「組織としての変化」は、プロパー社員のお二人も実感されているのではないでしょうか?
山本様
はい、実感しています。特に最近は、現場の担当者の意見や判断が非常に重視されるようになりました。「自分はこうしたい」という考えをしっかり持ち、その理由を丁寧に説明すれば、上司も基本的にはそれを尊重し、背中を押してくれる。そうした“現場発”の意思決定を支える文化が、徐々に根付いてきたと感じます。
小島様
昔は、「経験のある上司の判断に従っていれば間違いない」といった空気がありました。でも、今は確実に変わってきています。世の中の変化のスピードは非常に早くなっていますし、価値観や物事の捉え方も、世代や立場によってどんどん多様化している。そうした時代においては、「1つの正解」に頼るのは難しいと感じます。
だからこそ、さまざまな意見を聞きながら、「どこに向かうべきか」を皆で考えていく。そんな柔軟性や対話を重視する方向へ、銀行の組織も確実に変わってきていると、私は捉えています。
現場と並走し、合意形成を楽しめる人にチャンス
江頭
変革が進む中で、カスタマーサービス推進部とデジタル戦略統括部、それぞれが今後一緒に働く人材にどのような人物像を求めているのか、教えていただけますか?
小島様
カスタマーサービス推進部・カスタマーサポートオフィスとしては、大きく2つのタイプの人材を求めています。
1つは、カスタマーサポートのDXをリードしていける方。戦略全体を俯瞰しながら、「今後どのように顧客接点を再構築していくべきか」といった構想を描ける方に来ていただきたいです。業界の知見やDXの経験など、何かしらの強みがある方はもちろん歓迎です。
私たちが目指すのは「カスタマーサポート」から「カスタマーサクセス」への転換です。そうした世界観に共感し、一緒に描いていける方を求めています。
もう1つは、現場オペレーションを変革しつつ、安定運営に貢献してくださる方です。これからDXを推進する中で、業務の進め方や役割も大きく変わっていきます。そうした変化を現場に定着させていくには、マインドセットから変えていける人材が必要です。地道な作業もいとわず、常にユーザーの立場に立って、より良い体験のために価値や喜びを見いだせる方。そういった方と一緒に働きたいですね。
江頭
デジタル戦略統括部では、どのような人物像を求めていらっしゃいますか?
山本様
コンサルティンググループ全体として、キャリア採用を強化し、DXをさらに推進していきたいと考えています。もちろん、金融ビジネスや特定ドメインの知識はあると嬉しいですが、拘りはありません。「これまでコンサルティングファームや各種ベンダーなどで培った経験を、事業会社側の立場で生かしてみたい」、「特定ドメインで培ったデジタル・DX関連のスキル・経験を幅広いフィールドで試してみたい」と思っている方です。
私たちの関わるプロジェクトは、ファームが担当するような支援範囲が定義されたものだけでなく、もっと“ふわっとした”課題感から入っていくケースが多くあります。そうした「壁打ち」的な役割からスタートし、ビジネス側の業務と並走しながら、「こういったアプローチがあるのでは?」と提案していけるのが、この仕事の面白さでもあります。
特に、コールセンター領域においては、現場で何が起きているかという解像度を高く持ち、現実をきちんと把握したうえで、資料に落とし込みながら関係者と合意形成を図っていける方が活躍できると思いますね。
また、マインドセットとしては、テーマの幅広さを楽しめる方が向いていると思います。さまざまなリクエストや要望が飛んでくる環境なので、それをネガティブに捉えるのではなく、「新しいチャレンジができる機会」として前向きに取り組める方とぜひ一緒に働きたいです。
個々の強みを生かせるキャリア形成が可能に
江頭
御行では柔軟な働き方ができると伺いましたが、実際の勤務スタイルは?
小島様
カスタマーサービス推進部では、週2~3日の出社と在宅勤務を組み合わせた柔軟な働き方を推奨しています。プロジェクトのミッションや個人の事情に応じて調整しており、出社頻度が高い人もいれば、在宅を中心にしている人もおり、家庭やプライベートとの両立がしやすい環境だと実感しますね。カスタマーサポートオフィスは現場運営ということもあり出社が基本ではありますが、ご事情等に応じて調整可能です。
江頭
デジタル戦略統括部ではいかがでしょうか?
山本様
私たちも週3日程度の出社が基本で、プロジェクトによってはシステム開発拠点やコールセンターの現場に出向くこともあります。オフィスが複数あるため、働く場所もチームで柔軟に選べるようにしています。
天川様
私自身、入行して半年ですが、育児休暇や時間休の制度も充実しており、とても取りやすい雰囲気があります。入社間もないタイミングでも、家庭の事情にしっかり配慮してもらえることに驚きました。
江頭
ワークライフバランスは取りやすいですか?
山本様
休みは非常に柔軟に取れますが、自分の業務の進捗や責任を意識しながら動いている人が多いですね。たとえば、夕方に一度仕事を中断して家のことを済ませた後、夜に再開する人もいます。そうした自律と信頼をベースにした働き方が根付いてきていると思います。
江頭
以前は“銀行=ジョブローテーション文化”という印象がありましたが、今もその風土は残っていますか?
小島様
だいぶ変わってきています。かつては“いろいろな部署を経験して一人前”という考え方が主流でしたが、今は専門性を深めながらキャリアを築く人も増えています。
山本様
実際にキャリアの希望・専門性が尊重される風土に変化してきていて、「人事がキャリアを考えてくれる」という時代ではなくなってきたと感じます。業務との適合性や本人の志向が重視されるようになっていますね。
小島様
キャリア採用の方についても同様で、専門性を生かして長期的に活躍できるフィールドを前提としています。全く違う部署へのローテーションはゼロではありませんが、原則として“その人の強みを伸ばす”方向に配置されるケースが中心かと思います。今、銀行は大きく変わろうとしています。この変革期だからこそ味わえるダイナミズムを、ぜひ一緒に体感してほしいですね。

2010年、旧三菱東京UFJ銀行に入行。法人取引推進を担当した後、住宅ローン、外貨預金等のマスリテール向け商品・キャンペーン企画、WEBマーケティングや、組合専従業務等に従事。2020年よりデジタル企画部(現・デジタル戦略統括部)にてカスタマーサポート領域のDX推進を担当後、2023年4月より旧コールセンター(現・カスタマーサポートオフィス)にてDX推進・CX向上PJを現場から牽引。 2024年4月より、カスタマーサービス推進部企画Grでチャネル全体の戦略企画従事後、現在は同部リモートチャネルGrにてカスタマーサポート領域全体のDX推進・CX向上PJをリード。

2010年、人材派遣会社へ入社。要員を必要としている企業を自身で発掘する営業活動から、その企業に合わせた人材の募集・面接、配属後の管理、契約・請求処理等、一連の業務を対応。その後、2014年にコールセンターベンダーへ転職し、通信・ゲーム業界を担当した後、銀経・保険会社等の金融業界を担当。既存の企業様を担当する営業職として、既存コールセンターの運用・品質改善、新規コールセンターの立ち上げ、ノンボイス導入等の提案活動に従事。それらの経験を活かし、2025年3月に当行入行。現在は、当行の次期コンタクトセンターシステムの検討を推進。

2011年、旧三菱東京UFJ銀行に入行。営業店および営業本部にて中堅・大企業向けの法人営業を担当。その後、大企業営業部門の企画業務に従事し、複数のデジタル・DX案件の立ち上げを経験。2020年には、デジタル企画部(現・デジタル戦略統括部)に異動し、スタートアップとのオープンイノベーションや新規事業開発を担当。2024年4月のデジタル戦略統括部の立ち上げに伴い、現職へアサイメントを変更し、大企業法人向けビジネス領域や、コールセンター・事務センター領域のDX・AI推進を支援するコンサルティングチームのチームリーダーとして、各プロジェクトをマネジメント。

2018年に新卒で共済連合会へ入会。火災共済金の支払業務や企画立案系業務を中心に行う。大規模災害発生時には災害対策本部事務局として損害査定計画の策定、遂行に従事。2021年に大手日系グループの生命保険会社へ転職し、保険事務委託先のベンダー管理、事務コスト削減に向けた業務改革、データ集計及び分析業務等に従事。その後、より大きな事業基盤を持つ会社でキャリアアップをしたいという想いから当行へ入行し、現在はデジタル戦略部コンサルティングGrにてコンタクトセンター案件をはじめカスタマーサポート領域のDX推進を中心に担当。

1919年(大正8年)8月15日設立、従業員数は銀行単体で31,756名、国内421・海外104の拠点を有する(従業員数と拠点数はいずれも2024年3月末時点)
三菱UFJフィナンシャルグループの中核企業として、「預金」「融資」「決済」の主要業務を中心に、あらゆる金融サービスを国内に限らずグローバルに事業を展開。

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
株式会社三菱UFJ銀行の求人情報
| 募集職種 | DXコンサルティング(コンタクトセンターのデジタル改革) |
|---|---|
| 職務内容 | ■業務内容 ※想定される内容 ■主な役割: ■魅力とキャリアパス: |
| 応募要件 | 【必須】 【歓迎】 |