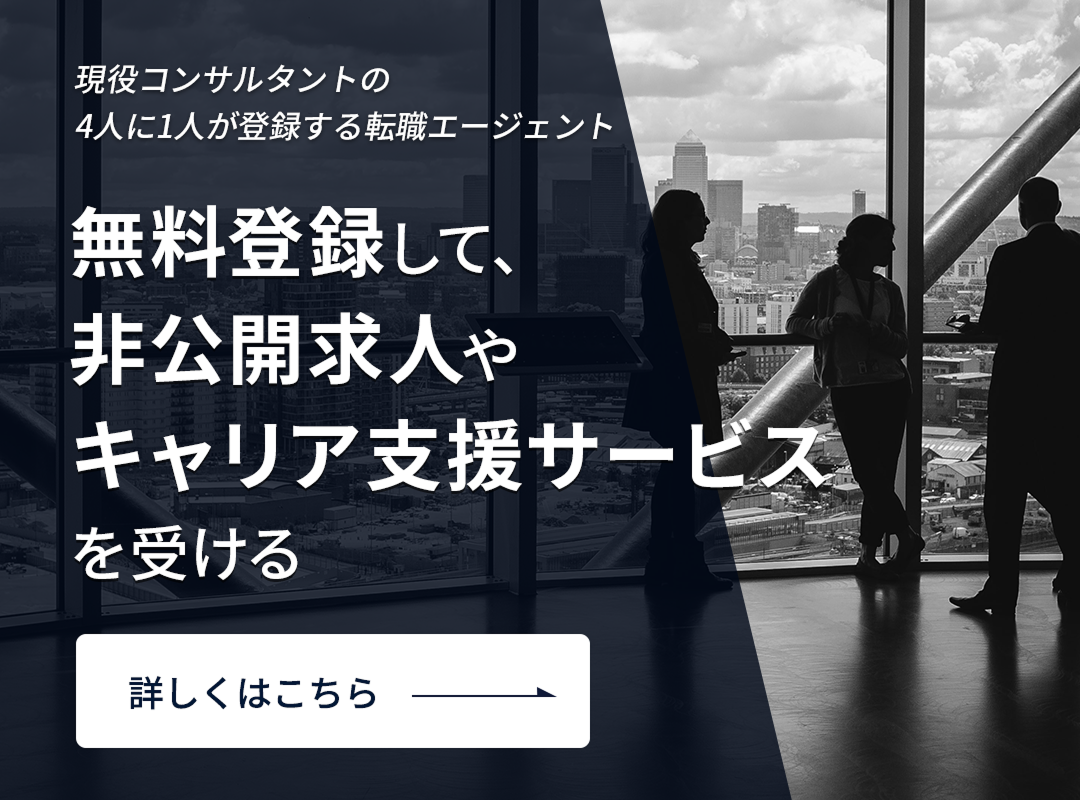Mujin Japanインタビュー/総合オートメーションテクノロジー企業が製造・物流業界コンサル参入、「根性文化」から「データ駆動自動化」への転換

統合自動化プラットフォーム「MujinOS」の開発で世界市場に挑むMujin。「過酷な労働から人々を解放し、人類が創造性、技術革新、そして世界をより良くする活動に集中できる世界を実現する」というミッションを掲げる同社が、2024年4月に自動化コンサルティング~インテグレーション~アフターサポートまで一気通貫でスピーディーにご提供すべく株式会社Mujin Japanが事業を開始しました。また、2023年より始動した製造業・物流業界に向けた本格的なコンサルティング事業も並行して、より規模を拡大してきました。
その最大の特徴は、経営層への戦略提案で終わらず「現場の自動化実装まで最後までやりきる」点にあります。製造現場出身のエンジニアとコンサル経験者からなる「ハイブリッド人材」が、課題の可視化から自動化プラン設計、導入支援まで一気通貫で伴走します。
今回は、Mujin Japanの取締役でありコンサルティング事業を統括する、オートメーションストラテジー本部長 嶋田岳史様、コンサルティング部の松山孟司様、池庄司まり子様に、日本の製造業が抱える構造的課題と、それを打破する技術×コンサルの新しいアプローチについてお話を伺いました。
Index
3人の入社ストーリー、世界と戦える「普遍的技術」を求めて
江頭
まずは、皆さんのキャリアとMujinに入社された経緯を教えてください。
嶋田様
工学系の大学院を修了後、新卒で戦略コンサルティングファームに入社し、主に製造業界や金融機関のDX案件に携わりました。入社から1年半ほどたった頃、大学院時代の友人から「日本にはスタートアップは数多くあるけれど、“世界と殴り合える”ようなポテンシャルを持つところはMujinしかないと思う」と聞かされ、強く興味を持ちました。
当時のMujinは社員数がまだ70名ほどで、ビジネス部門も小規模でした。そんな中で偶然「営業・企画職」の募集を見つけ、「コンサル経験を活かせそうだし、何より面白そうだ」と思って応募したのが入社のきっかけです。
江頭
具体的にどのような点に魅力を感じられたのでしょうか。
嶋田様
1つはMujinの技術は普遍的であること。もう1つは、事業領域がどの国でも必ず存在する社会インフラに近いことです。日本だけで戦うと、どれだけ成功しても人口1億2000万人の市場に限られてしまいます。一方、インフラ領域なら、世界82億人を対象に戦える。そのスケール感に大きな魅力を感じ、2019年1月に入社しました。

江頭
松山様はいかがでしょうか。
松山様
前職は自動車系部品メーカーで、生産技術のソフトウエア開発を担当していました。プログラムを書いてロボットやAGVを動かしたり、工程全体のシステムを構築したりと、研究開発から実装まで幅広く手がけていました。その中で多くのベンチャー企業と協業し、新しい技術づくりに取り組んでおり、Mujinとも某自動化案件で関わったのが最初の接点です。
当時のMujinはまだ規模も小さく、技術も発展途上でしたが、わずか2年後には工場の量産ラインに導入できるレベルにまで成長し、非常に驚きを覚えた。そこから生産工程全体の自動化といった大きなプロジェクトを、ユーザー側として一緒に進めるようになりました。ただ、大企業で生産ラインが数十もある環境では、導入を繰り返すうちに業務が単調になり、次第にマンネリを感じるようになりました。もっと世界のものづくりを見てみたいと思ったのが転職のきっかけです。
Mujinはソフトウエアを強みに、世界中から優秀なエンジニアが集まっています。前職でもソフトウエアを開発・実装する立場にいましたが、世界を見れば優秀な人材は無数にいる。むしろ、自分が研究を続けるより、そうした人たちと一緒に最先端の自動化技術を多くのお客さまに導入し、世の中に広げていく方が、日本の製造業や社会全体により大きなインパクトを残せると思いました。研究者から導入・普及の側に立場を移すことで、新しい挑戦ができると感じ入社を決めました。

江頭
池庄司様はいかがでしょうか。
池庄司様
新卒では大手自動車メーカーに入社し、OEMの生産技術として新モデルの立ち上げや、量産に耐えうる技術の導入を担当しました。8年ほどたつと自分の仕事の幅も広がり、会社の仕組みも理解できて、業務をスムーズにこなせるようになっていました。一方で、自分の能力をさらに試し、より幅広い環境で通用する人材になりたいと考えるようになり、経営コンサルティング会社に転職したのです。
コンサルではモビリティ領域の戦略セクターに所属し、地域の公共交通に関する政策立案の支援などを行いました。しかし1年を通して、「やはり自分はものづくりに携わりたい」という思いが強くなりました。そこで、ものづくりとコンサルティングの両方を実現できる会社を探していたところ、エージェントの紹介でMujinと出会い、入社を決めました。

「お客さまが何に困っているか」を肌で感じた営業経験が、コンサル事業の出発点に
江頭
嶋田様は2019年1月に「営業・企画職」として入社され、現在はコンサルティング事業を統括されています。当初からその流れが見えていたのでしょうか?
嶋田様
「営業・企画職」と聞いて戦略立案や事業企画系の業務だと思っていたのですが、実際には営業そのものまで任されて、当初は「だまされたな!」と思いました(笑)。ただ、振り返ってみると、今の私を形作っている非常に貴重な経験となりました。
というのも、営業を経験することで「お客さまが今、何に困っていて、どうすれば解決できるのか」を肌で感じられたからです。CEO 兼 共同創業者の滝野からも「現場や実務を知らない人間が、本当に意味のある戦略や企画立案をできるわけがない」といわれていて、その通りだと実感しました。
そのため、営業をしながら得た情報を新規事業の企画にフィードバックし、企画で考えたことを営業で試すという形で二足のわらじを履いて取り組みました。その試行錯誤が、結果的にコンサルティング事業の基盤にもつながっていきました。
江頭
その後、社内で正式にコンサルティング事業を立ち上げたのが2023年ですね。
嶋田様
そうですね。実はその前から、お客さまのニーズがあれば「裏メニュー」としてコンサル的な支援を3〜4年ほど断続的に行っていました。本来であれば「こういうことをしたい」という構想はお客さま自身から出てくるべきものですが、待っていてもなかなか出てこない。なぜなら、多くのお客さまは「現状を変えたい」と思っていても、日々の業務に追われたり、推進できる能力・経験を持った人材が不足していたりして、なかなか前に進めない状況にあったからです。
私たちのミッションは「人々を過酷な労働から解放し、創造・イノベーション・世界をより良くすることに注力できる世界を実現する」ことです。その理念に照らせば、ただ待つのではなく、私たち自身が主体的に時計の針を進める役割を担うべきだと考えました。そして、それまでのコンサルティング事業で得た経験とコンサルを担える人材が社内にいたこともあり、正式に事業として立ち上げようと踏み切れましたね。

Mujin流コンサルの特徴はマルチベンダーを前提とした最適解の追求と経営・現場の橋渡し
江頭
2024年4月には日本法人「Mujin Japan」が事業を開始し、コンサルティング事業が本格的にスタートされています。改めて、コンサルティング事業について教えていただけますか。
嶋田様
Mujinコンサルの事業は大きく3つの領域から成り立っています。1つ目は経営層とともに描く上流の戦略策定、2つ目は製造業(Factory Automation)の現場自動化、そして3つ目は物流領域の自動化です。
この3本柱を貫く共通点は、「現場をどう変革するか?」に最後まで伴走することです。単に戦略を描くだけでなく、データ化からプラン設計、導入プロジェクトまで一気通貫で関わる点が大きな特徴です。しかも、Mujin Japanはソフトウエアに強みを持つエンジニアリング企業であるため「自社製品ありき」ではなく、可能な限りフラットな視点で最適解を提案できる強みがあります。
具体的には、4つのステップで進めていきます。
1.戦略の明確化
お客さまが「どこを目指すのか」「どのような戦略で取り組むのか」を整理します。すでに方向性が決まっている場合は、その考えを受け取り支援につなげます。
2.現状の可視化(定量化)
倉庫や工場の現場では、ノウハウがベテラン社員の頭の中にしかなく、数字化されていないケースが多く見られます。判断も長年の勘や経験に頼っていることが多いため、属人的で再現性がない。結果、その方が退職やリタイヤされると組織としてのノウハウが失われてしまい、非常にもったいない状況です。そこで、たとえば作業スピードや在庫の動きといった要素を数値化し、「どんな条件でどう判断したのか」という基準を明確にします。
3.最適な自動化プランの検討
各社の特性を踏まえ、最適な自動化構想を策定します。弊社はソフトウエアに強みを持つ企業であり、自社でハードウェアを製造しているわけではありません。よって、通常のメーカーにありがちな、「自社製造品だけを押していく」スタイルではなく、ハードウェアについてはマルチベンダーを組み合わせて最適なソリューションを設計します。コンサルティングでも同じ発想を貫き、フラットな立場から最適解を導き出すことを重視しています。
4.実行支援(PMOとして伴走)
プロジェクトが具体化していくと、お客さま側の人材やリソースがより不足していきます。その際にはMujinがPMOとして参画し、導入プロジェクトを最後まで支援します。
江頭
ありがとうございます。前職でコンサル経験もある池庄司様から見て、Mujinコンサルが、一般的なコンサルティングファームと比べてどのような点に違いを感じますか。
池庄司様
いろいろな違いは感じますが、たとえばMujinでは必ず「現場をどう改善するか」に直結させるために、データや技術といった確かな根拠をもとに提案するケースが多いです。
また、一般的なコンサルティングファームの方は製造現場の経験がない場合も多く、現場から「あなたたちにはわからないだろう」と受け止められがちです。一方、私たちは現場を経験しているメンバーが多いため、「実際にこういうことが起きますよね」と実感を持ってお客さまと話ができる。そこがMujinコンサルの大きな違いであり、強みだと感じています。
見えない間接費と過酷な現場、課題の本質に迫る
江頭
現在、お客さまから寄せられる課題にはどのようなものがありますか?
嶋田様
一番多いのは「自動化を進めたいけれど、具体的にどう進めればいいかわからない」という声です。経営陣から「物流を強化せよ」と号令があっても、現場では進め方が見えず時間だけが過ぎてしまうケースも少なくありません。
また、多くの現場で共通しているのは、数字の表面上は健全に見えても、その裏側に大きなギャップが潜んでいるという点です。たとえば日本のメーカーでは、粗利までは確保できても、営業利益になると急に数字が落ちることがよくあります。その原因の1つが、サプライチェーンにかかる間接費のブラックボックス化です。直接費をどれだけ削っても、間接費が重くのしかかり、利益を圧迫する。結果として従業員に還元できず、経営者が頭を悩ませる状況が増えています。
江頭
物流業界でDXが進みにくい理由は何でしょうか?
嶋田様
これは個人的な見解ですが、日本の製造業では長年「ものづくり」が花形とされ、物流やサプライチェーンは後回しにされがちでした。さらに日本人は現場力が高く、多少無理があっても「根性でやりきる」文化があったため、仕組みを見直さなくても現場がなんとかしてきてしまった。その結果、裏方であるロジスティクスや間接領域の改善が後手に回り、今もブラックボックスが多く残っているのでしょう。
その結果、多くのお客さまが「どうにか改善したい」と強く望むようになり、ニーズは非常に大きなものになっています。 しかし一方で、それに応えきれていないのが現状です。私たちは専門性のある人材が一社一社に伴走する形を取っているため、“金太郎飴”的に大量に対応することはできません。品質を担保するために1人あたりの案件数を意図的に制限しているので、どうしてもお客さまをお待たせしたり、場合によってはお断りせざるを得ないこともあったりします。そこが、私たちにとって今、最も大きな課題ですね。だからこそ、お客さまからの旺盛なニーズにタイムリーにお応えしていくために、仲間を大募集中です。
製造と物流の両方を経験することで得られた成長実感
江頭
現在、松山様が関わられているプロジェクトについて教えていただけますか。
松山様
今、私が担当しているのは製造業の案件です。対象となるのは、生産ラインを持つ企業で、特に自動車関連や部品メーカーが多いですね。製造業チームの役割は、ラインに必要なものを滞りなく届けるために、供給の仕組みをいかに効率化し、自動化するかという点にあります。
その中で強く感じるのは、どの企業にも独自の習慣や文化があるということです。それぞれの会社が長年大切にしてきた考え方が根底にあって、「ここは変えられない部分なのだ」と理解できる場面が多い。効率化や自動化の観点だけでは語れない、企業ごとの“違い”があることを実感しています。
池庄司様
そうですね。一方で、お客さま自身が時代の変化の中で自分たちの在り方に疑問を感じているケースも少なくありません。本当は考え方を変えるべきなのではないか、と。 ただ、それを内側から変えていくのは難しいのが実情です。だからこそ私たちコンサルが入り、「これまでのやり方もありますが、こうした考え方もあります」「将来を見据えるなら、こう変えていくのも1つの選択肢ではないでしょうか」と示すことで、お客さま自身が動き出せるよう支援する。そうしたプロジェクトも多いです。
江頭
プロジェクトを通じて「鍛えられたな、成長したな」と感じるエピソードはありますか?
池庄司様
私は製造業の生産技術出身なので、Mujinに入る前は物流にはあまり関わったことがありませんでした。工場内の物流に関わる程度でした。ところが今は、製造業だけでなく物流や上流の戦略案件にも携わるようになっています。
そこで気づいたのは、物流は製造と違って「一つひとつの品質」よりも「全体の流れや傾向」を見ることが重要だということです。小売業のお客さまの倉庫では、扱う商品が膨大なので細かく見すぎると対応しきれません。むしろ平均化して全体感をつかむことが成果につながるのです。この視点は製造業にも応用できる部分があって、「最初は全体を見てから、細かい改善に入った方が良いのでは」と思う場面もあります。製造と物流、両方を経験したことで得られた視点は、自分の大きな強みになっていると感じます。

現場経験×コンサルのハイブリッド組織
江頭
ここからはチームについて伺います。現在コンサルチームは何人体制でどのようなバックグラウンドの方が多いのでしょうか。
池庄司様
現在は20名ほどの体制です。メンバーのバックグラウンドは大きく2つに分かれます。1つは工場で生産技術や生産管理、IE(インダストリアルエンジニアリング)、ベンダーとして設備導入などに携わってきた人材。もう1つは物流系、たとえば3PL(サードパーティー・ロジスティクス)出身者です。いずれも「ピュアにコンサルティングだけ」というより、現場経験を持ち合わせているメンバーが多いです。
江頭
プロジェクトのアサインはどのように行っているのでしょうか。
松山様
プロジェクトのアサインは、基本的にお客さまからの要望やメンバーのバックグラウンドに合わせています。いわゆる普通の経営コンサルティングと比べると少人数で案件を回すことが多く、1人あたり3件を同時並行で担当するケースもあります。まだ小さいチームなので、全員の間でのコミュニケーションが多く、チームが違ってもお互いのことは把握できています。
江頭
入社した方はどのようなキャリアステップを描けるのでしょうか。
松山様
Mujinでは、多様な業界や役職層を相手にした案件経験を重ねることが、そのままキャリアアップにつながります。製造業といっても扱うテーマは幅広く、現場で担当者と膝詰めで議論することもあれば、経営層に方針を示すこともあります。1つの案件の中でも異なる立場の人たちと向き合うため、自然と視野が広がり、視座も自在に切り替えられるようになります。そうした経験を積み重ねて、最終的に「1人で案件をリードできるようになる」ことが、キャリアの次のステップ、つまり昇格のタイミングになるのだと思います。Mujinの昇格時期は人事評価と同時期で、年に2回実施しています。チーム内ですでに数名が1回目の評価で、コンサルタントからシニアコンサルタントに昇格しました。昇進昇格のペースも早く、社員の納得感も高いと思います。

江頭
キャッチアップはどうされていますか。
池庄司様
新しく入ったメンバーには、まずコンサル系のオンボーディングプログラムを用意しています。技術や製造業のバックグラウンドが強い人が多いため、最初の2週間でデータ分析の方法やプレゼンテーション資料の作り方を集中的に学びます。その間は、半分を座学や演習、もう半分を実際のプロジェクトでのOJTにあて、「勉強しながら実践する」形で進めています。技術的な知識は座学でも学びますが、多くはプロジェクトを通じて実務的に身につけていただいています。
江頭
海外案件は多いのでしょうか。
松山様
はい、海外案件も少なくありません。東南アジアからアメリカ、ヨーロッパまで幅広くありますが、基本的には日本企業のお客さまの海外拠点をご支援するケースが中心です。国ごとに物流の文化や特性が異なるため、それを反映させつつ工場をどう自動化するかが非常に面白い点ですね。
働き方としては在宅も可能で個人に任されていますが、実際にはお客さま先への出張が多いです。海外を含め全国への出張があり、多い人では週の半分ほど出張していることもあります。
池庄司様
海外案件に関わることもありますが、コンサルとして最も大事なのはお客さまとのコミュニケーションです。お客さまが日本の方であれば必ずしも英語は必要ありません。ただ、英語ができれば活躍の幅はさらに広がります。
産業ロボットの浸透と、ハイブリッド人材の育成へ
江頭
Mujin Japanに新しく加わるメンバーには、どのような“思い”や“スタンス”を期待されていますか?
嶋田様
今求めているのは、まず何よりも「日本のものづくりを良くしたい」「自動化を通じて社会に貢献したい」という思いを持っている方です。ここはメンバー全員に共通している根幹の部分で、最も大切にしています。
その上で、バックグラウンドとしては幅広く歓迎しています。改めてお伝えすると、実際に多いのは生産技術や生産管理の経験者、また私のようにコンサル出身で工学系の素養を持っている人、さらにはメーカーからセカンドキャリアとしてチャレンジしている人などです。そうした方々には大きな活躍の機会があると思います。また、チームも会社も引き続き成長途上で良い意味で「整っていない」部分がまだある状態ですので、それに対して「なんでないのだ」ではなく、「ないなら新しくつくろう」と、能動的に発信・行動できるマインドセットを持っている方をお待ちしております。
江頭
改めて御社で働く魅力を教えてください。
嶋田様
まず前提として、コンサルティングファームには大きく2つのタイプがあります。1つは経営層に対してビッグピクチャーを描く経営コンサルです。これは非常に意義のある取り組みですが、現場まで踏み込まないため、どうしても理想論にとどまりがちです。もう1つは現場改善型のアプローチです。現場の改善を積み重ねる一方で、部分最適に陥りやすい。「ある工程を効率化したが、結果的に隣の工程では逆に非効率が生じてしまった」といったケースは典型的です。
つまり、経営と現場は「将来の理想」と「日々のオペレーション」という異なる視点を持ち、その間には大きなギャップが存在しています。Mujinコンサルの最大の強みは、この両者をつなぐ“真ん中の役割”を果たせる点にあります。その理由は、私たちが現場で自動化を推進してきた経験を持ち、現場の課題や苦労を深く理解している一方で、経営層とともに構想を描いてきた経験から企画・戦略の視点も備えているからです。両方の立場を理解しているからこそ、経営層からも現場からも「自分たちの言葉が通じる存在」として信頼を得ており、実際に強いニーズにつながっています。
江頭
お二方は今後どのようなことに挑戦していきたいとお考えでしょうか。
松山様
私は、産業ロボットをもっと世の中に浸透させたいと考えています。ただ、その実現は簡単ではありません。Mujinが持つモーションプランニングという唯一無二のロボティクス技術は非常に高いレベルにありますが、製造業の多くのお客さまがまだその技術レベルの高さに追いついていない場合があります。つまり、技術が先行し、世の中が追いついていない部分があるのです。
だからこそ、お客さまの技術レベルを引き上げていければ、産業用ロボティクスはより大きな価値を発揮できるはずです。実際には「もっと手前の自動化で十分だ」という生産現場もありますが、そうではなく、世の中のレベルを上げていくことでMujinのテクノロジーが真価を発揮できる領域は確実に広がっていき、日本のものづくり業界に新しい息を吹くことはできると考えています。
池庄司様
コンサルタントとしての今後の挑戦としては、コンサル力と現場力の両方を身につけた人材を育成していくことです。製造の知識が強い人には論理的思考力やコンサル力を、コンサルバックグラウンドが強い人には現場を知っている「実務に強いコンサル力」を身につけていただく。その経験は将来、企画職などにもつながるはずです。普通のコンサルティングファームでは経験できない、このハイブリッドな成長環境をさらに強化していきたいですね。


工学系大学院修了後、戦略コンサルティングファームに入社し、中長期戦略、組織変革、デジタル戦略構築 等のPJに従事。2019年にMujin参画後は、営業部長・営業本部長を歴任し、2024年1月にアクセンチュア社との合同出資ベンチャーのAccenture Alpha Automation(株)の副社長に就任し、同年4月に(株)Mujin Japan取締役に就任。

新卒で愛知県の大手自動車部品メーカーに入社。約10年間、生産技術として工場内の様々な自動化に従事。キャリア後半では、構内物流の自動化を主導。ロボットソリューションやAGVソリューションの内製化に携わり、特にソフトウエアの領域に深く関わる。2023年Mujinコンサルティングの社員第1号としてジョインし、2024年1月にマネージャーに昇進。

新卒で大手自動車メーカーに入社し、生産技術を担当。その後、経営コンサルファームでシニアコンサルタントを経験後、2023年にMujinに入社。2024年4月設立の日本法人、株式会社Mujin Japanで製造・物流・小売向けの生産・SCM戦略および構内物流自動化に関するコンサルティングを担当。2025年7月にコンサルティング部マネージャーに昇進。

ロボティクス分野の世界的権威の1人であるCTO、Rosen Diankov博士の研究のもと、50年間不可能だったモーションプランニング技術を、ロボットに世界で初めて実用化することを成功しました。
その成果をもとに独自のロボット制御技術(MujinMI) によって産業用オートメーションの常識を覆し、世界中のサプライチェーンに革新をもたらしているMujin。
労働人口減少や重労働、2024年物流問題など、深刻化する社会課題に対応すべく、物流・製造・小売・流通等の各業界で、Mujinは世界初の自動化DXを次々と実現しています。
物流・製造現場での入出荷・仕分け・荷下ろし・積み付けなどの工程を自動化できる知能ロボットシステムに加え、工程間搬送を担うAGV(無人搬送車)も提供しています。単一作業の自動化や部分最適にとどまらず、ありとあらゆるロボットや自動機器を統合制御する統合自動化プラットフォーム「MujinOS」を強みに持つからこそ、複数ラインや全体最適化まで自動化DX支援できる点がMujin Japanの大きな強みです。
こうした技術と実績が評価され、国内外の企業から高い支持を獲得。2023年には、サプライチェーン戦略や中長期経営戦略を支援するコンサルティング事業を開始し、ハードウェアとソフトウエアを融合させた“完全自動化トータルソリューション”の実装も本格化しました。

アクシスコンサルティングは、コンサル業界に精通した転職エージェント。戦略コンサルやITコンサル。コンサルタントになりたい人や卒業したい人。多数サポートしてきました。信念は、”生涯のキャリアパートナー”。転職のその次まで見据えたキャリアプランをご提案します。
株式会社Mujin Japanの求人情報
| 募集職種 | 戦略コンサルタント |
|---|---|
| 職務内容 | ■どんな仕事か? ■オートメーションストラテジー本部ミッション ■会社概要 自動化産業は約1000兆円規模とも言われる巨大な市場でありながら、今なお明確な“プライムベンダー”と呼べる企業は存在していません。私たちは、この分野におけるプライムベンダーとなることを目指し、さらなる成長を続けています。 ■職務内容 |
| 応募要件 | ■必須要件 ■歓迎要件 |