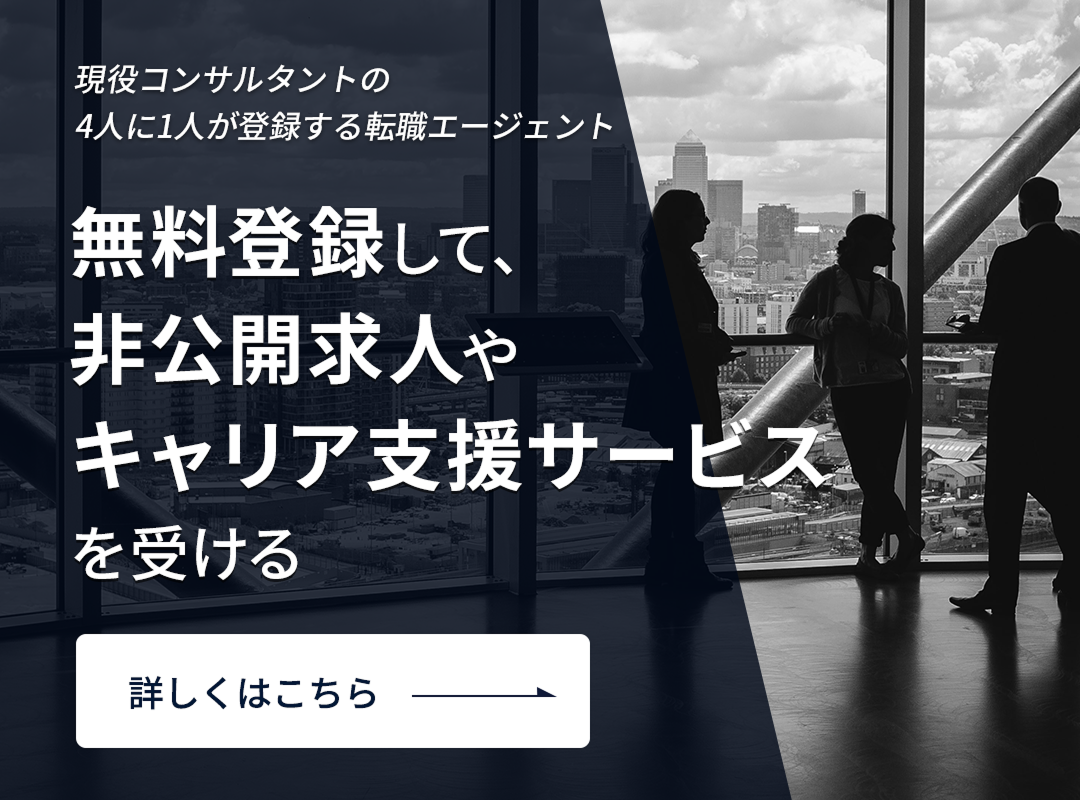「AI時代に生き残るコンサルタントとは?」元会計士・コンサル・CFO【宮地俊充社長】が語る進化するキャリアの軌跡
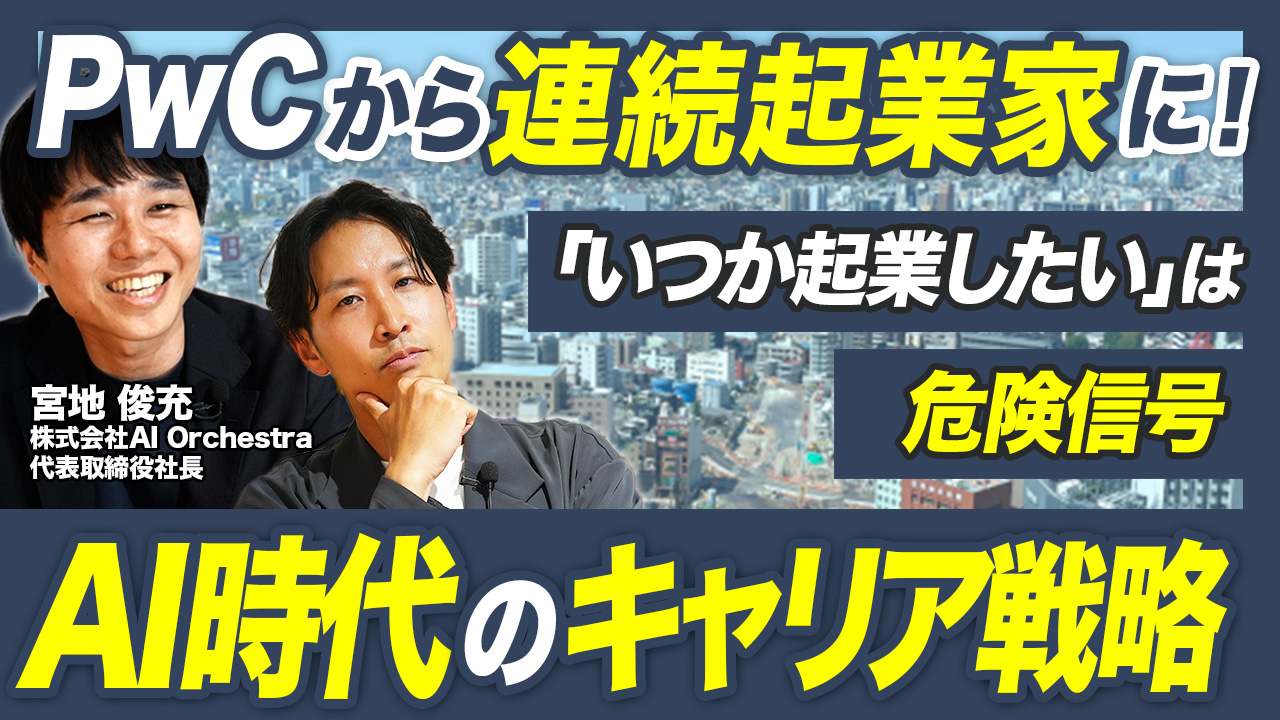
大手監査法人PwCからキャリアをスタートし、M&AファームGCAを経て20代でCFOに就任。その後、オンライン英会話「ベストティーチャー」を創業し、代々木ゼミナールに売却──そして現在は、生成AIの最前線で株式会社AI Orchestra代表取締役社長を務める宮地俊充さん。
「覚悟を決めた日」から始まった挑戦の日々。AIの進化が加速する今、情報収集以上に問われる“問いを立てる力”と“クロージングの力”。キャリアを「選ぶ」のではなく、「切り拓く」ための考え方とは?
これからの時代をどう生きるかを模索するすべてのビジネスパーソンに向けて、宮地さんにお話を伺いました。
ゲスト:宮地 俊充 株式会社AI Orchestra 創業 代表取締役社長
青山学院大学法学部卒業。大学時代は放送作家・脚本家として活動。卒業後より公認会計士を目指し、2007年に公認会計士試験合格。PwC(あらた監査法人)、独立系M&Aアドバイザリーファーム、EコマースベンチャーのCFO兼CMO(Chief Marketing Officer)を経て、2011年11月、株式会社ベストティーチャーを創業。2020年5月株式会社AI Orchestra創業。
モデレーター :藤澤専之介
RPA業務を自動化するテクノロジーの会社を2018年に立ち上げ、2022年にクラウドワークスにM&Aでイグジット。その後、子会社の社長やスタートアップの支援などを行い、現在はM&A支援に従事。
Index
自己紹介とこれまでのキャリア
藤澤(モデレーター): まずは簡単にご自身のご紹介と、これまでのキャリアについてお話しいただけますでしょうか。
宮地さん:現在は株式会社AI Orchestraという、生成AIを活用した事業を展開する会社を経営しています。大学を卒業した後、会計士試験に合格しまして、最初のキャリアとしてはPwC(当時はあらた監査法人)に入所いたしました。
藤澤:会計士からキャリアをスタートされたのですね。
宮地さん:会計士試験に合格すると、通常は3年程度実務経験を積んで修了試験に合格し、それから転職するというのが一般的です。ただ、私は少し変わっていまして、そこに“愛余って”とでも言いますか(笑)、1年半ほどで次のステップに進むことにしました。
その後、GCAサヴィアンというM&Aアドバイザリーファームに転職し、そこから本格的にコンサルティングのキャリアをスタートしました。そちらを約1年半で退職して、その後はIT企業の経営にシフトし、結果的に約14年間、さまざまな形で経営に関わっています。
英会話教育の革新:最初の起業「ベストティーチャー」
藤澤: 宮地さんが最初に起業されたのは、どのような事業だったのでしょうか?
宮地さん:最初に立ち上げたのは「ベストティーチャー」というオンライン英会話のサービスです。当時は、ZoomやGoogle Meetがまだ普及しておらず、主にSkypeを使って世界中の講師と会話できる仕組みでした。
ちょうど「英語の4技能(読む・書く・聞く・話す)」が重要視され始めたタイミングで。ライティングとスピーキングの両方を重視したプログラムは珍しく、その先進性もあって、多くの方に支持いただきました。約5年間この会社を経営し、最終的には代々木ゼミナール様に売却しています。
藤澤:ベストティーチャーの売却後は、どのような活動をされていたのでしょうか?
宮地さん:いくつかスタートアップに投資をしたりもしましたが、もう1つ、学生時代からずっと抱えていた「音楽への未練」のようなものがあって。大学時代に音楽をやっていたのですが、「やりきれなかった」という気持ちがどこかに残っていました。
それで、「このお金で音楽を本気でやったらどうなるだろう?」という気持ちで、一時期は音楽関連の会社も経営していました。
藤澤:音楽の会社も経験されたとのことですが、現在はAIやITの分野に戻ってこられていますね。
宮地さん:結局、自分が本当に得意で、熱中できるのはITやプロダクト開発、SNSの活用など、テクノロジーを活かした事業だと再認識しました。そうした流れで、今のAI Orchestraという生成AIの会社につながっています。
会計士としてのキャリアスタート
藤澤:宮地さんが最初に社会人として所属されたのはPwCだったそうですが、どのような経緯で入社されたのでしょうか?
宮地さん:僕がPwCに入所したのは2007年です。会計士試験に初めて合格して、最初に就職する先として監査法人を選びました。通常、合格者は監査業務をするのですが、僕は少しひねくれているというか、人とは違うキャリアを歩んでみたいなと。
藤澤:具体的には、どのような業務を担当されたのでしょうか?
宮地さん:当時はちょうどUS-GAAP(米国会計基準)とIFRS(国際会計基準)の両方が注目されていた時期で、僕は「これからはIFRSの時代だ」と思い、J-GAAP(日本基準)からIFRSへの会計基準の転換、いわゆる“IFRSコンバージョン”のコンサルティングを希望しました。
同期が250人くらいいた中で、そのIFRSコンバージョンの部門にいたのはたった2人でした。監査法人に入ったのに、監査を一切やらずにコンサルをしていたわけです。周囲には日本の会計士だけでなく、USの方もいて、かなり刺激的な環境でした。
藤澤:通常であれば数年間監査業務に携わってから転職される方が多い中で、宮地さんは1年半で退職されていますよね。その背景にはどのような考えがあったのでしょうか?
宮地さん:当時は、会計士試験に受かっている人が多くて、皆さんキャリアパスを模索していました。「将来CFOになりたい」、「FAS(Financial Advisory Services)の仕事がしたい」といった話があって、「そのためにはまず3年間監査をやるべきだ」というロジックが常識のように語られていたのです。
ただ、僕自身はそのロジックにしっくりこなくて。自分が本当にやりたいことに対して、監査の経験が直結しているようには思えなかった。だったら、早いうちに財務系やM&Aの仕事を経験したいと思い、転職活動を始めました。
GCAサヴィアンでの業務とキャリアの葛藤
藤澤:宮地さんはPwCから転職して、GCAサヴィアンへ入社されましたが、そちらではどのようなお仕事をされていたのでしょうか?
宮地さん:GCAサヴィアンでは、基本的にはM&Aのアドバイザリー業務を担当していました。ただ、僕のように会計士出身の人間は、どうしても「DD(デューデリジェンス)」、つまり財務調査の担当になることが多くて。
藤澤:それは、監査業務の延長線上ということでしょうか?
宮地さん:そうですね、失礼な言い方かもしれませんが、資料作成がメインになってしまいがちでした。一方で、僕自身はもっと大きな会社同士を「つなぐ」仕事がしたかったのです。
ただ実際は、大企業の社長たちとコネクションを持っている上司たちが案件を進めていて、若手の自分は直接関与できない状況が続いていました。それが非常にもどかしかったです。
藤澤:そうした経験が、後の起業にどう活かされていったのでしょうか?
宮地さん:まず、会計の基礎や会社法、経営学などは受験科目としても触れていたので、しっかりとした土台ができていました。
さらに、GCAやPwCでは「みんな基準値が高い」環境だったので、ロジカルシンキングや構造化された思考、情報整理能力など、基礎的なスキルが身に付いたと感じています。
藤澤:当時、転職について「もったいない」と言われることはありましたか?
宮地さん:ありましたね。上司の中には「まだ残って経験を積んだ方がいい」とアドバイスしてくださる方もいました。でも僕自身は、「残って経験を積んで役職が上がってから見えるもの」と、「転職して新しい環境で見えるもの」、そのどちらが良いかは“誰にも分からない”と思いました。
藤澤:確かに、それは比較のしようがないですね。
宮地さん:時代によっても違いますし、転職先がどうかによっても変わります。だからこそ、自分で「その選択を正解にしていく」しかないと思いました。若かったこともあり、行動力と突破力で前に進むことができたのだと思います。
『ソーシャル・ネットワーク』の映画に触れて芽生えた転機
藤澤:宮地さんがCFOを志すようになったきっかけについて教えてください。
宮地さん:『ソーシャル・ネットワーク』というFacebookがモデルになった映画を観たのですが、ハーバード大学の学生たちが楽しそうに働いていて、その光景がとても印象的でした。
IT業界は若い人でも大きなチャンスがあって、年功序列のような文化が薄い。とくに当時は、まだ“ガラケー時代”だったのですが、GREEやDeNAといった企業が急成長している時期でした。
20代でCFOを務める若い方たちが上場企業の役員として活躍していたので、「自分もその世界で挑戦してみたい」と強く思い、IT企業を中心にリサーチを始めました。
藤澤:今のようにSNSが発達していた時代ではなかったかと思いますが、リサーチはどのように行われたのでしょうか?
宮地さん:当時は今のようにTwitterやYouTubeなどの発信手段も限られていて、リアルな情報にアクセスするのが難しい状況でした。そんな中で頼りにしたのが「ベストベンチャー100」というスタートアップ企業を集めた媒体です。
藤澤:今の若い方はあまり聞きなじみがないかもしれませんね。
宮地さん:おそらくそうでしょうね。でも、僕はそこに掲載されていた100社すべてに電話をかけて話を聞きました。とにかく現場の空気を知りたくて、自分の目で確かめたかったのです。
藤澤:そこで出会った方々の中で、印象的な人物はいらっしゃいましたか?
宮地さん:たとえば、当時株式会社メタップスを創業していた佐藤航陽さんです。彼は「宇宙の真理を知りたい」と本気で語るような人物で、まったくぶれずに自分のビジョンを追い続けていました。のちにメタップスを上場させ、今もまたさまざまな事業に取り組まれています。
藤澤:コンサル出身の方とはまた異なるタイプのリーダーですね。
宮地さん:そうですね。当時のスタートアップは、今ほど洗練された人たちの集まりというよりも、むしろ“かなり異質”で個性的な人の集まりでした。でも、そこにものすごいエネルギーを感じて。コンサルとはまったく違う世界でした。
大手コンサルとスタートアップの「距離感」の違い
藤澤:宮地さんはコンサルティングファーム出身ですが、スタートアップ企業に入社された際にまずどんな違いを感じられましたか?
宮地さん:一番感じたのは、「役員や経営陣との距離」です。コンサルにいた頃は、どうしても役員クラスの方との距離が遠いと感じていました。一方でスタートアップに入ったら、社長の横の机で働くことになって。
藤澤:まさに“現場の最前線”という感じですね。
宮地さん:そうですね。しかも、どのスタートアップでも社長が最後まで働いていることが多くて。だから僕も自然と残るようになり、気づいたら「毎晩、社長と自分だけが残っている」という状況になっていました。そういう日々を通じて、社長が何を考えてどう意思決定をしているのかを、直に見て学べたと感じています。
藤澤:スタートアップ企業では、入社時からCFOという肩書きだったのでしょうか?
宮地さん:僕も勢いがあったので、最初から取締役、CFOでないと入らないということを伝えて入社しました。ただ、実績が伴っていない状態で肩書きだけ大きくしても意味がないですし、周囲との上下関係もつくれないのであまりおすすめはしないです(笑)。
藤澤:ちょうど社会人3年くらいを終えたタイミングで、そういう交渉をされていたのですね。
宮地さん:そうですね。当時は、情報源も限られていて、「ベストベンチャー100」の掲載情報しかなく、今ほど会社の内情や役割を深く知れる環境ではなかったので、役割のイメージが湧いていなかったのが正直なところです。
「勘違いのしようがない時代」──SNSがもたらす現実
藤澤:時代の変化についても言及されていましたが、今の若い方たちのキャリア環境はどう見えていますか?
宮地さん:本質的な話をすると、当時から15年くらい経った今は、SNSがあることで“勘違いできない時代”になったと思います。たとえば、「自分は歌がうまいかもしれない」と地方に住んでいて思ったとしても、YouTubeやTikTokに投稿すれば、すぐにフィードバックが返ってくる。つまり、結果が出るかどうかが明確になります。
藤澤:自分の実力がそのまま“見える化”される時代ということですね。
宮地さん:そうです。だから、「夢が叶わないのは、自分の実力不足以外に理由はない」という現実を突きつけられる。もはや言い訳ができないし、厳しい時代になったとも言えると思います。
「何をやるか」が見えないまま、スタートアップに“修行入社”
藤澤:「ベストティーチャー」を立ち上げるまでの期間、どのような過程があったのでしょうか?
宮地さん:ずっと「どんな事業をすべきか」と考えてはいたのですが、なかなかアイデアが浮かびませんでした。そこで、「まずは修行のつもりで経験を積もう」と思い、ある会社に入社したのです。
当時はまだ若く、あるとき社長から「上場した後も一緒にやってくれるよね?」と聞かれた際に、「実は起業を考えているので、正直まだ分かりません」と答えました。
すると社長から、「本気で起業したいなら、そのことしか考えられないはず。今すぐ辞めた方がいいよ」と言われて――まさに“売り言葉に買い言葉”のようなやりとりでしたが、その言葉で自分が甘えていたことに気づかされました。
藤澤:その一言が、宮地さんの中でどのような変化を生んだのでしょうか?
宮地さん:コンサル出身で「いつか起業したい」と考えている人は多いと思いますが、実際には何年も動けずにいることも珍しくありません。でも、“いつか”というタイミングは、待っていても自然に訪れるものではないです。
だからこそ、自分で“期限”を決めてセルフスターターとして動き出すことが大切だと感じています。あのときの社長の言葉は、まさに僕の背中を押してくれる一言になりました。
「会社を辞めよう」と思ったときに、ようやくハッとして道が定まったというか――「じゃあ、一度起業してみよう」と思えたことが、自分にとって一番大きかったです。
リサーチはもうAIがやる時代へ
藤澤:宮地さんご自身、コンサル出身としてさまざまな業務を経験されてきたと思いますが、AIの進化によりコンサルの仕事はどう変わってきているとお考えですか?
宮地さん:「Deep Research」の経験は、自分にとって非常に重要な起点になったと感じています。もし自分が事業会社の立場だったら、「今の時代、AIで調べられるのに、なぜそれをコンサルに依頼するのだろう?」と思ってしまうほどです。
藤澤:では、AIで代替できない部分はどこにあるのでしょうか?
宮地さん:AIは、インターネット上の情報であればリサーチすることができます。でも最終的には、現場に足を運んで情報を得たり、そこから仮説を立てて考えたりするのは人間の役割です。
だからこそ、これからはそういった「人にしかできない部分」に重きを置いていくべきだと思っています。
ネット上だけで完結するスタイルで仕事をしているコンサルタントは、今後は厳しくなっていくのではないでしょうか。
藤澤:ネットに載っていない情報をどう手に入れるかという点も重要ですが、それ以上に、「どんな問いを立てるか」というスキルこそが問われるということでしょうか。
宮地さん:「この人なら会ってみたい」と思わせるような信頼関係は、AIには代替できない非常に重要な要素です。「何かあればすぐに駆けつける」といった、泥臭くても誠実な営業スタイルを大切にしている会社もありますが、そうした姿勢も立派な強みになると思います。
また、「今の会社に残るか、それとも転職するか」のように、何が正解か分からない判断も多くあります。材料をいくら集めても、それをどう調理し、結果としてお客様に満足いただけるかは予測が難しく、最終的には“クロージング”の力が問われる場面が多いのです。
AIの時代は、最終的な意思決定ができる人が少なくなってきている印象があります。権限や性格的な面もあるかもしれませんが、だからこそ「決められる人」であること、クロージング力がより重要なポイントになっていくと思います。
藤澤:お話を伺いながら、「これで行こう」と意思決定のきっかけをつくることこそが、コンサルタントとしての価値なのだと感じました。
宮地さん: 「問い」を立てる作業自体も、今ではAIが担える時代です。だからこそ、最終的にはクロージングの力が問われるのだと思います。
たとえばAIに10個ほど案を出してもらったとしても、どれが相手に響くのかを見極めるのは、やはりセンスや経験に左右される部分。そこが勝負所になると感じています。