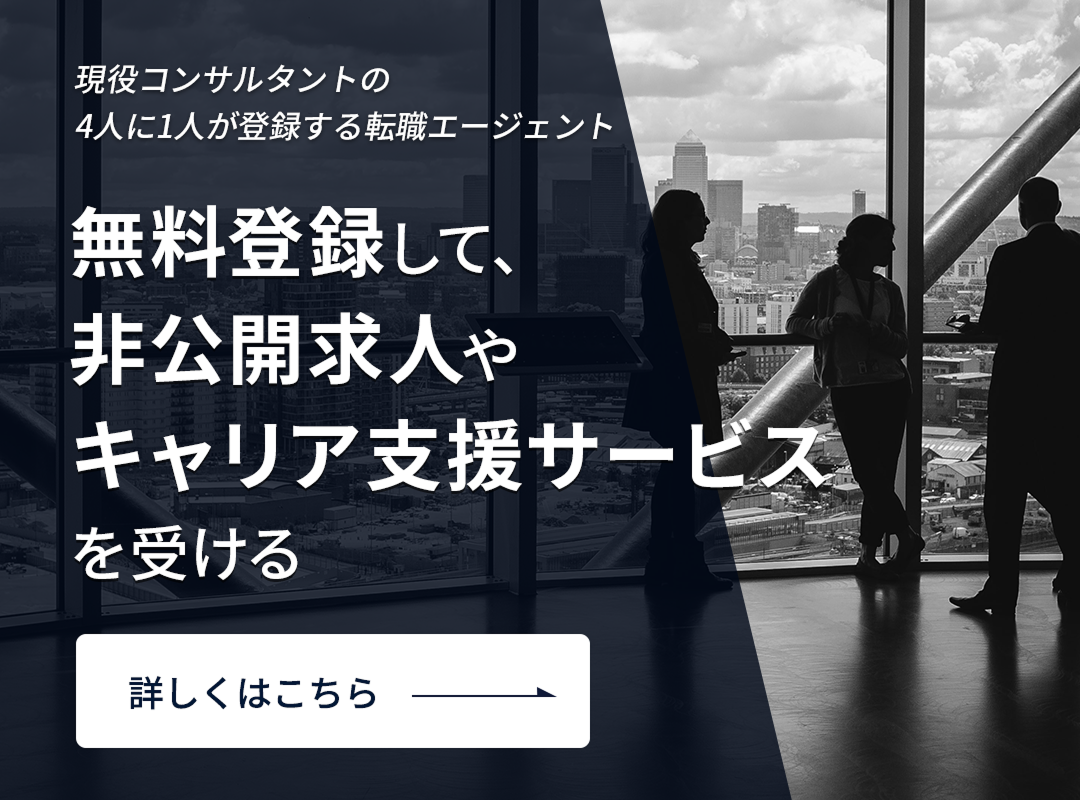「“想い・お金・人材”をどう動かすか」──連続起業家【宮地俊充社長】 が語る、英会話事業M&AとAI時代の本質
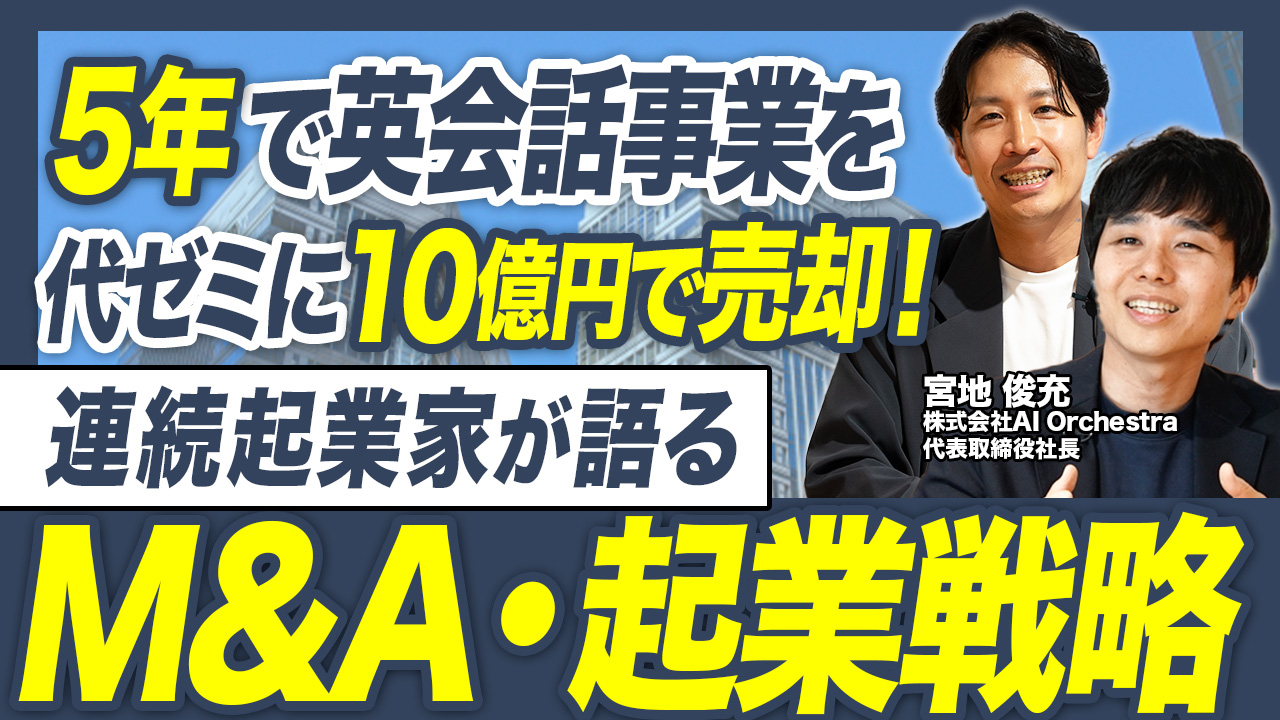
大手監査法人PwCからキャリアをスタートし、M&AファームGCAを経て20代でCFOに就任。その後、オンライン英会話「ベストティーチャー」を創業し、代々木ゼミナールに売却──そして現在は、生成AIの最前線で株式会社AI Orchestra代表取締役社長を務める宮地俊充さん。
後編では、「想い・お金・人材」という起業の3要素のリアルから、SNSでCTOを見つけた起業当初の奮闘、M&Aの裏側、そしてコンサル出身者としての強みと“弊害”の両面を語っていただきました。
また、ChatGPTとの出会いが導いたAIへの確信、個人がプロダクトを持てる時代におけるキャリア観、そして「正解がない時代」の生き方について、実体験をもとに鋭く紐解いていきます。
ゲスト:宮地 俊充 株式会社AI Orchestra 創業 代表取締役社長
青山学院大学法学部卒業。大学時代は放送作家・脚本家として活動。卒業後より公認会計士を目指し、2007年に公認会計士試験合格。PwC(あらた監査法人)、独立系M&Aアドバイザリーファーム、EコマースベンチャーのCFO兼CMO(Chief Marketing Officer)を経て、2011年11月、株式会社ベストティーチャーを創業。2020年5月株式会社AI Orchestra創業。
モデレーター :藤澤専之介
RPA業務を自動化するテクノロジーの会社を2018年に立ち上げ、2022年にクラウドワークスにM&Aでイグジット。その後、子会社の社長やスタートアップの支援などを行い、現在はM&A支援に従事。 
Index
英語学習への原体験と“仮説”から生まれた起業動機
藤澤(モデレーター):ベストティーチャーを通じて解決したかった課題について教えてください。
宮地さん:起業を考えたとき、自分にとって「大切なものって何だろう?」とあらためて立ち止まって考えました。そのときに思い浮かんだのが、英語学習でした。
ずっと取り組んできて、英語は本当に習得が難しいと感じていたので。それで、「もっと効率的に学べる方法があるのではないか?」という仮説があり、それを製品にして、社会に届けたいと思ったのが出発点でした。
藤澤:起業を実行するにあたって、最初に何を考えたのでしょうか?
宮地さん:事業をやる上で大事なのは、大きく3つだと思っています。やりたいこと(想い)・お金・人です。特にプロダクトをつくるならエンジニアが必要不可欠なので、この3点をどう揃えるかが最初の課題でした。
藤澤:起業当初、資金調達はどのように進められたのでしょうか?
宮地さん:実は、正式な起業前の2011年10月ごろに「僕はこういう経歴で、こういう事業をやろうと思っています」とX(旧Twitter)に投稿したのです。すると、当時のサイバーエージェント・ベンチャーズの担当者の方から連絡が来て、出資の話をいただきました。
今と比べて起業家が圧倒的に少なかったので。今では信じられないかもしれませんが、「Xで起業宣言して出資が決まる」みたいなこともありました。
エンジニア探しは“SNS DM作戦”
藤澤:技術的なパートナー、つまりCTO候補はどう探されたのでしょうか?
宮地さん:それが本当に苦労しました。2011年の9月〜10月ごろから、さまざまなスタートアップイベントを回ったりしていたのですが、最終的にはFacebookやXで“エンジニア”とプロフィールに書いてある人全員にメッセージを送るという、かなり泥臭いアプローチをしました。
藤澤:それで見つかった方がいらっしゃったのですね?
宮地さん:はい。ある方と出会って、まずはプロトタイプだけをつくってもらうことになりました。当時、MOVIDA JAPAN(孫泰蔵さん主宰のスタートアップ支援プログラム)とサムライインキュベートのどちらかに応募するというタイミングだったので、それに間に合わせる必要があったので。
藤澤:無事にプロトタイプも完成し、いざ本格的に共同創業へ……という段階だったわけですね。
宮地さん:ところがその方が、当時大手SIerに勤めていたこともあってか、起業目前の10月に「お金も調達してきたし、フルタイムでジョインしてくれますか?」と聞いたら逃げられてしまって。
藤澤:それは大変でしたね……。
宮地さん:でももう退路はないと思い、2011年11月1日に起業して、その日に「起業しました」とFacebookで投稿しつつ、「CTO募集」と同時投稿したのです。すると、その日のうちに連絡をくれた方がいて、代々木のルノアールで会いました。
藤澤:そしてその日に?
宮地さん:その日のうちに、取締役就任と株式譲渡を決めました。
藤澤:起業後、事業はどのように立ち上げられたのでしょうか?
宮地さん:2011年11月1日に起業して、2012年5月10日に正式リリースしました。約半年間です。その間は、サービス全体のディレクション、ワイヤーフレーム作成、投資家対応、プロモーション設計などを自分で手がけていました。
藤澤:特にプロモーション面ではどのような工夫を?
宮地さん:当時は「事前登録」が流行していたので、リリース前からユーザーを集める施策を行っていました。最終的に3,000人以上の事前登録者を集めることができ、かなり手応えがありました。
藤澤:初期段階から市場に受け入れられている感覚はありましたか?
宮地さん:はい。英語は常に学びたいと思う人が多いジャンルなので。
ベストティーチャーのM&A。成長とともに生まれた出口戦略
藤澤:ベストティーチャーは最終的にM&Aでイグジットされました。その意思決定の背景を教えてください。
宮地さん:どんなサービスも、リリース直後は注目が集まり盛り上がるものです。ただ本当に重要なのはそこからで、日々現場の問題を解決しながら、プロダクトを少しずつ改善し、自然成長を積み重ねていくというステージがやってきます。
藤澤:徐々に事業が熟していく段階ですね。
宮地さん:そうです。そんな中で、あるエンジニアのイベントで「ベストティーチャーのユーザー」だと話しかけてくれた方がいて。
藤澤:まさにその偶然の出会いが、転機になったわけですね。
宮地さん:はい。その方のスキルを見て「この人だ」と思い、CTOを交代しました。その結果、プロダクトの成長スピードが一気に上がりました。
藤澤:ベストティーチャーは立ち上げから順調に成長されたようですが、いつ頃からM&Aを意識し始めたのでしょうか?
宮地さん:創業から約3年で黒字化し、月商も100万円、200万円、500万円と順調に伸びていました。ちょうど「このままスケールするか」「上場を目指すか」と考え始めていたタイミングです。
その時期に、オンライン英会話の先駆者である株式会社レアジョブが上場したのですが、評価額は50億円規模だったのです。それを見て、「この市場で上場しても、思ったほど評価されないかもしれない」と感じました。
藤澤:そこで方向性の見直しがあったのですね。
宮地さん:加えて、当時のVC(ベンチャーキャピタル)との関係も厳しい状況でした。組織崩壊のような状態も経験し、「宮地はもうダメだ」という空気も出てきて……。コミュニケーション能力が低い、トラクションを出せない、次の資金調達も見込めない、といったネガティブ評価が並び、定例会議にすら来なくなる状況でした。
英語“4技能”で教育界を動かす
藤澤:そんな中でも、教育業界全体にインパクトを与えるような動きがあったと伺っています。
宮地さん:僕たちが一貫して訴えてきたのが、読む・聞く・話す・書くの「4技能」の重要性でした。これは当時、楽天の三木谷浩史さんや東進ハイスクールの安河内哲也先生らと連携して、大学入試に4技能を導入しようという社会的ムーブメントをつくっていたのです。
藤澤:英語試験の構造自体を変えにいく、大きな挑戦ですね。
宮地さん:TOEFLやIELTS、TOEIC S&Wといったアウトプット型試験の導入が進めば、高校生の英語学習も一変する。英語が受験科目になれば、1学年100万人の高校生が勉強する。それに伴って市場規模が爆発的に広がると考えていました。
藤澤:その構想を実現するために、具体的にどのような行動を?
宮地さん:北海道から九州まで、全国の塾・予備校を1件1件回りました。VCや銀行のつても活用しながら、とにかく「4技能型英語教育」の価値を伝える営業活動を徹底しました。
藤澤:その中で、代々木ゼミナールとの出会いがあったのですね。
宮地さん:はい。アプローチした中の1社が代々木ゼミナール様(以下、代ゼミ)で、最初の打ち合わせから「良いね」と言っていただきました。特に4技能の考え方に共感してくださったことが大きかったです。
藤澤:代ゼミとの関係は、どのようにM&Aに発展していったのですか?
宮地さん:通常、事業提携から始まり、マイノリティ出資を経て100%買収というステップを踏むケースも多いですが、教育系の会社の少額出資を受けて苦労するスタートアップの会社も多く、それが怖かったので、僕たちは最初から「100%出資しか検討しない」と明言していました。
藤澤:M&A交渉はスムーズに進んだのでしょうか?
宮地さん:最初にお会いしてから、しばらく時間は空いたのですが、ある日、代ゼミのトップの方から再度連絡がありました。「新聞に“4技能”の話が載っていた。やっぱりこれは来る」と。
藤澤:そのひと言が決め手になった?
宮地さん:大きかったです。そこからは、業務提携→出資→M&Aという流れが一気に進みました。
弁護士と渡り合える、“実戦的スキル”としてのコンサル経験
藤澤:ベストティーチャーのM&Aを進める中で、コンサルタントとしてのご経験はどのように役立ちましたか?
宮地さん:非常に大きかったですね。たとえばデューデリジェンス(DD)などは、もう「余裕で対応できる」といった感覚でした。相手方の弁護士と直接やり取りする中でも、必要な会計・法務・税務の知識が自分の中にあるので、不安なく進められました。
藤澤:M&Aにおいて、コンサル出身の強みが発揮されたのですね。
宮地さん:はい、M&Aの局面においては確実にコンサル経験が生きたと思います。
藤澤:全体を通して、コンサル経験がある起業家とそうでない起業家との違いを感じることはありますか?
宮地さん:あります。一番大きな違いは組織づくりです。コンサルティングファームはプロフェッショナルファームですから、社員一人ひとりの意識がとても高い。それが当たり前の環境で育っているので、初めて事業会社の現場に入ったときは、ある種のカルチャーショックがありました。
藤澤:具体的には、どのような違いがあるのでしょうか?
宮地さん:たとえば、業務時間外に勉強するのが当たり前というのがコンサルの文化です。でも事業会社では、それを押しつけると「非常識」と思われるケースもある。それくらい常識の基準が違います。
藤澤:コンサル出身の起業家は、組織づくりの初期に“詰めすぎる”傾向があるとも言われますが、いかがですか?
宮地さん:本当に皆、最初は詰め込みすぎます。求める基準が高すぎて、組織が一度崩壊してしまうのです。そしてまた新たに組み直して、少しずつ“丸く”なっていく。これは多くのコンサル出身社長が通る道だと思います。
藤澤:その厳しさは「強み」でもある一方で、調整が必要ということですね。
宮地さん:そうですね。対外的にはむしろその厳密さが武器になると思います。たとえば投資家対応や金融機関とのコミュニケーションでは、論理的な事業計画や数字での説明力が求められるので。
“想い”だけでは資金は動かない、コンサル出身者のファイナンス強み
藤澤:宮地さんご自身、投資家とのやり取りの中で感じた“違い”はありましたか?
宮地さん:はい。やはり、コンサル未経験の起業家の中には、情熱が先行してしまい、数字やロジックで語れない方も少なくないので。でも、投資家や銀行員にとっては、そこが一番重要だと思います。
藤澤:宮地さんはコンサル出身でありながらも、スタートアップを立ち上げ、事業をグロースさせてこられました。その中で、コンサル経験がむしろ“弊害”になったと感じたことはありましたか?
宮地さん:ありました。特に、「思っていたよりも論理的に物事が進まない」という現実にはかなり驚かされました。
藤澤:具体的にはどのようなシーンで?
宮地さん:事業は、フレームワークや理論だけで進むものではありません。たとえば、「今は“4P”のうちこれを強化すべきだ」と言っても、目の前には課題が山積みで、それどころではないことも多くて。結局、「とにかくやるしかない」というフェーズに突入するのです。
藤澤:コンサル時代はロジックを駆使して大企業に提案してこられたと思いますが、起業現場ではそれが通じないと?
宮地さん:そうですね。当時は「なぜこんなに良い提案が相手に響かないのだろう?」と思っていたのですが、実際に自分が事業を動かす側になって、ようやく分かりました。
藤澤:理想や戦略ではなく、“現場の都合”が優先されることも多いと。
宮地さん:ええ。起業の現場は、理想だけでは回らない。人的なリソース不足、法務的な制約、予算の制限など、実務上の障壁が想像以上に多い。それが実際のビジネスの9割を占めているように感じます。
藤澤:起業当初、そのギャップに戸惑うことはありませんでしたか?
宮地さん:もちろんありましたが、幸いにも最初から「崩して使う」という感覚を持っていたのは大きかったです。スタートアップのノリが、教科書的なファイナンスや戦略コンサルのようなものではなく、全部分かった上で崩していくようなやり方をするので。
たとえば、プレゼン資料に“フレームワークのような4P”を書いた瞬間に、ダサく感じるかどうかの感覚も大事です。最初からそこを乗り越えたレベルにいるような印象です。
ChatGPTとの出会いがもたらした“確信”
藤澤: 現在は生成AIを軸とした事業を展開されていますが、そのきっかけは何だったのでしょうか?
宮地さん:ちょうど「次は何をやろうか」と考えていた時、2023年にChatGPTが話題になったのです。それを見て、「これだ」と直感的に思いました。
藤澤:それは、どのような意味での「これだ」だったのですか?
宮地さん:僕が以前やっていた「ベストティーチャー」では、英語ライティングを外国人講師に添削してもらう仕組みを提供していました。実は当時から、「これをAIで置き換えられたらいいのに」と思っていたのです。
藤澤:かなり先見的な視点ですね。
宮地さん:はい。2016〜2017年ごろに大学の研究室と共同開発もしたのですが、AIが出力する内容に納得できず、結局リリースできませんでした。だからこそ、ChatGPTを見たときに、「自分たちがやりたかったことが、ついに技術的に実現できる時代が来た」と感じました。
藤澤:そこから一気にAI領域へ注力されたのですね。
宮地さん:はい。まずは情報発信に力を入れて、インフルエンサー的な立ち位置で認知を広げました。そこでリードをつくり、法人研修や顧問業務、プロダクト開発といった事業へと展開しています。
藤澤:現在のAI Orchestraについても、将来的なイグジットを考えていらっしゃるのでしょうか?
宮地さん:正直に言うと、イグジットは選択肢の1つとして考えています。ただ、以前のように「大きな会社をつくってIPOを目指す」というスタイルがベストだとは思っていません。
藤澤:それは、AI業界の変化を受けての判断ですか?
宮地さん:そうです。今のトレンドは、スモールチームで機動的に動ける組織や、“1人ユニコーン”のような個人に紐づいた事業体が評価される時代です。だから、今後どういう形でイグジットするのか、あるいは一部のみ切り出すのか、僕自身も含めてどうなるか──現時点では未定ですが、意識して動いているのは確かです。
藤澤:資金調達については、どのように考えていらっしゃいますか?
宮地さん:現在は、エンジェル投資家を中心に、1社の事業会社とも連携しながら、すでに7,000〜8,000万円ほど調達済みです。
起業の話は“過去の教科書”になりつつある
藤澤:宮地さんはこれまでいくつものスタートアップを手がけてこられましたが、今の若い方たちに伝えたいことは何でしょうか?
宮地さん:まず大前提として、「僕の起業したときの話はもう参考にならない」ということです。時代があまりにも変化しているので。特にこの2年間のAIの進化によって、前提条件がガラッと変わってしまいました。
藤澤:たとえば、どのような変化を感じておられますか?
宮地さん:たとえば2020年〜2021年のSaaSバブルの話をしたところで、今の状況ではあまり意味を成しません。特にプロダクト開発の難易度やアプローチ方法は、まったく違うものになっています。
藤澤:現在、起業や開発を考える人にとって、最もチャンスがある領域はどこだと思われますか?
宮地さん:今の技術水準では、非エンジニアでもプロダクトをつくることがかなり容易になっています。開発経験がゼロでも、学習環境やツールが充実しているので、本気で学べば誰でもつくれる時代です。
藤澤:たとえば、どんな人が対象になりそうでしょうか?
宮地さん:コンサル会社に入れるような地頭の良さを持っている人であれば、平日の夜や週末を使って数カ月学ぶだけで、十分プロダクトがつくれるようになると思います。
今はもう、「起業します!」という大きな宣言よりも、AIを使ってどんどん個人でプロジェクトを仕掛けていく方が圧倒的に面白いと思っています。
藤澤:スモールスタートでも、成果につながる可能性があると。
宮地さん:はい。実際にソフトウェアやプロダクトを小さくつくって公開する。その流れを繰り返していくうちに、自然と事業になっていく。キャリアのステップとしての“起業”ではなく、動いた結果としての“事業化”が主流になる時代です。
藤澤:最後に、読者の皆様へメッセージをお願いします。
宮地さん:僕自身も、AIを使ってプロダクトをつくっている方々と、もっとつながっていきたいと思っています。1人で黙々と取り組むのではなく、同じ興味・価値観を持つ人と一緒にプロジェクトを育てていくことに、これからの起業やキャリアの面白さが詰まっていると思います。