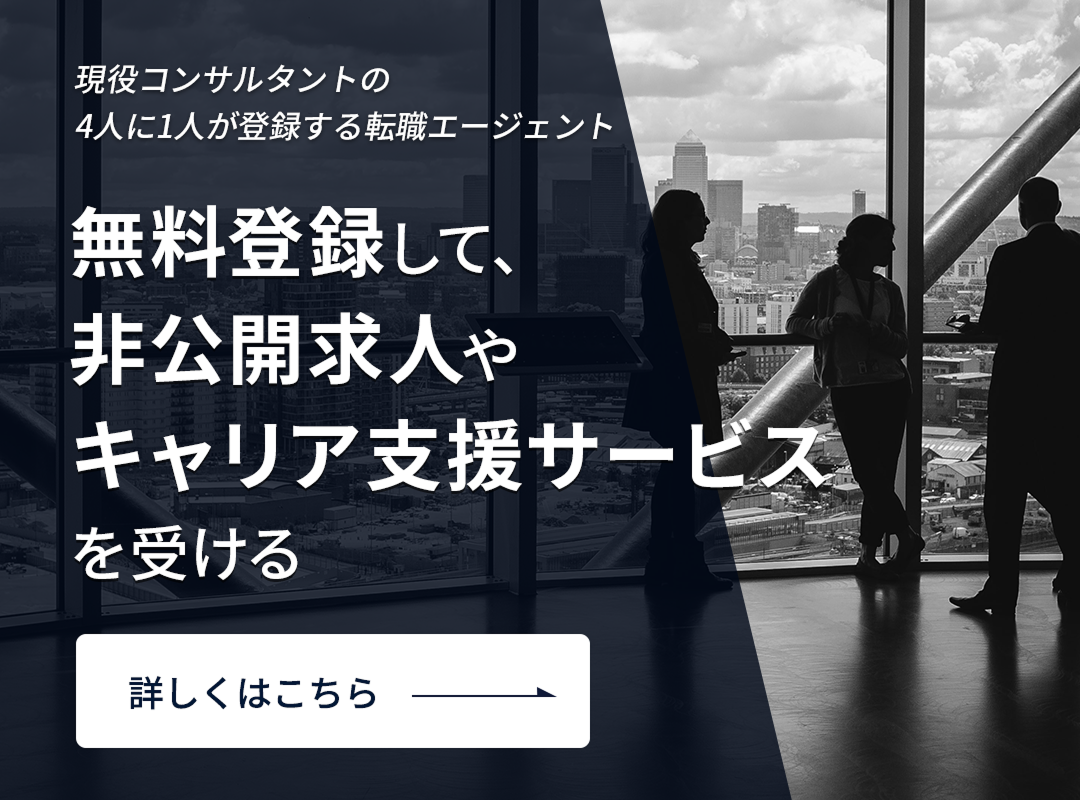行動力だけでは生き残れない時代へ──【元デロイト起業家・権藤 悠氏】が明かす「具体⇄抽象」スキルと自己成長の仕組み
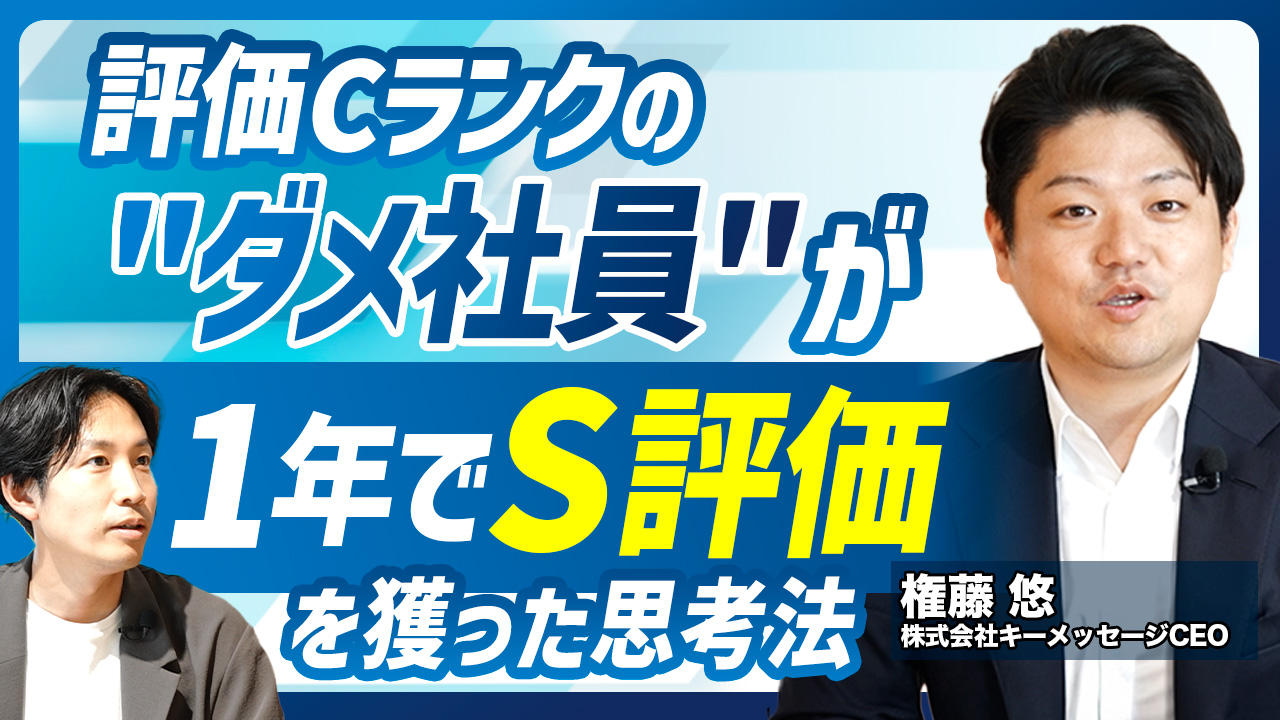
学生時代に体感した「チームで成果を出す喜び」と、ITを通じた人と人のつながりの力を軸に、組織制度設計やタレントマネジメント、組織間マッチングを支援してきました。
本インタビューでは、キャリア形成の選択理由やデロイト時代の挑戦、S評価を得るまでの転機、そして強みを活かすための思考法や習慣までを余すことなく語っていただきました。
ゲスト:権藤 悠(株式会社キーメッセージ 代表取締役CEO)
慶應義塾大学理工学部情報工学科卒業。ベンチャー三田会幹事。
ITベンチャー企業にて人事、IT新規事業開発をした後、株式会社ZUUに人事企画マネージャーとして参画し、東証マザーズ(現・東証グロース)市場上場前の採用・組織開発に従事。
その後、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社に経営コンサルタントとして入社。大手企業へのDX・組織人事高度化コンサルティング業務に従事し、合計社員数20万人以上の各業界企業を支援。デロイト トーマツ コンサルティングの中でも上位1%の人材しか認定されない「Sランク人材」の評価を受ける。
2022年、株式会社キーメッセージを創業。大手企業からスタートアップへ経営コンサルティング、AIやデータ分析を活用した新規事業開発や人的資本経営コンサルティングを提供する。
モデレーター :藤澤専之介
RPA業務を自動化するテクノロジーの会社を2018年に立ち上げ、2022年にクラウドワークスにM&Aでイグジット。その後、子会社の社長やスタートアップの支援などを行い、現在はM&A支援に従事。

Index
ITと人事の融合──組織を強くするためのキャリア軌跡
藤澤
まずは自己紹介とこれまでのご経歴を教えてください。
権藤さん
株式会社キーメッセージ代表取締役の権藤 悠です。生まれも育ちも広島で学生時代は野球に打ち込み、チームや組織で力を合わせて成果を出す喜びを原体験としてきました。社会人になってからは法人向けの組織・人事に興味を持ち、1社目・2社目のベンチャー企業では人事部門で活動。その後、デロイト トーマツ コンサルティングに入り、大手企業向けに人事関連の支援を担当しました。
組織・人事が自分の軸である一方、もう1つのアイデンティティはITです。きっかけは父がもともと日立のエンジニアだったのですが、小学生の時にホームページの作り方の本をくれて。当時はWindows95・98が主流の時代で、カープ関連のHPを作ったら、選手名検索でGoogle1位を取ることができました。そこから「ITで人と人がつながる力」に魅了されました。
大学は慶應義塾大学理工学部情報工学科に進学。以降、エンジニアリングの素養を生かしつつ、人事や広報、事業開発など幅広く経験。デロイトでは人事とデータ・AIを活用したプロジェクトにも関わりました。そして2020年代に入り、自らの経験をもとに、強みを活かす組織づくりを支援する株式会社キーメッセージを立ち上げました。
藤澤
キーメッセージではどのような事業を展開されているのですか?
権藤さん
大きく3つです。
1つ目は人事・組織制度設計の支援。2つ目はシステムやデータを活用したタレントマネジメント。3つ目は組織同士のマッチングと統合支援(PMI)です。
M&A仲介ではなく、お互いの強みや相性を見極めた上での「適切な結婚」と、その後の統合を重視しています。
「具体」と「抽象」を行き来し、課題解決力を鍛える──著書に込めた思い
藤澤
権藤さんは書籍も出版されていますが、どのような内容なのでしょうか?
権藤さん
大前提として、私の本は個人間のコミュニケーションや自身のスキルを高める領域に焦点を当てています。これまで累計で3万部ほど売れており、本を通じてビジネスパーソンの方々に向けて、ノウハウを提供しています。
特にこだわったのは、「抽象的な事柄と具体的な事柄を、いかに切り分けて考えるか」という点です。実務にどう生かすのかを、実際にトレーニングしながら学べる本が当時は存在していませんでした。そこで、51問のドリル形式にし、さまざまなビジネス課題を解像度高くブレイクダウンしていく方法を提示しました。
藤澤
読者は、どのようなスキルを身につけられるのでしょうか?
権藤さん
本の中では、ピラミッドツリーを作って課題を整理し、ソリューションに落とし込む方法を紹介しています。成功法則の抽出や、課題解決プロセスのステップ化など、実務で即活用できるノウハウを盛り込みました。
また、「具体と抽象」の行き来を体感してもらえるように、ドリルはカラーにしました。「ダサい彼氏をいかにオシャレにするか」「家事が回らない」といった日常的なテーマを例にしながら、イラスト付きで楽しく学べる構成です。こうしたシナリオを通じて、どう頭を使い、課題を解決するかをトレーニングできるようにしています。
「勝ち筋は大手の外にある」──ベンチャーからコンサルファームへの道
藤澤
権藤さんは最初のキャリアとして、なぜベンチャー企業を選ばれたのですか?
権藤さん
私は少し天邪鬼なタイプで、みんなが選ばないところにこそ勝ち筋があると考えていました。慶應義塾大学の理工学部出身なのですが、周囲は大手メーカー志望が多く、大手人気企業に就職するのが当たり前という雰囲気でした。そんな中で就職合同説明会に参加し、「この中で同じことをするより、別の道を探した方がいいのではないか」と感じたのです。
ちょうど私の学生時代は、DeNAやGREEといったITアプリサービスが最盛期を迎えていた時期。小さな組織で裁量権を多く持てるベンチャー企業の方が、自分の中長期的なキャリアを考えた時にプラスになると判断しました。加えて、大学まで取り組んできたチームや組織活動の経験、そして広報力を生かせる会社との相性も重視しました。
藤澤
その後、さらに挑戦されたと伺っています。
権藤さん
はい。自分をさらに鍛えるため、次の挑戦としてスタートアップに飛び込みました。2社目は金融メディアの上場企業である株式会社ZUUで、組織・人事を担当しました。ここは戦闘力が非常に高い方々が集まる会社で、学びが非常に多かったです。
その経験の中で、「もっと修行が必要だ」と感じました。特に、戦略を立てて中長期の課題を定義し、それを推進していくスキルを磨く必要があると。そこで行き着いたのが経営コンサルティングの世界でした。転職活動を経て、幸運にもコンサルファームに入社することができたのです。
「強みを可視化し、適材適所を実現する」──デロイト時代の挑戦
藤澤
権藤さんは、デロイト トーマツ コンサルティングではどのようなお仕事をされていたのでしょうか?
権藤さん
私が所属していたのは、組織・人事のテクノロジー活用を専門とするデジタルHRチームです。配属当初から、「新しいITやAIを活用してデジタル人材を輩出しなければ、これからの事業成長は難しい」という前提があって。そのため、人材育成や人材配置を支える人事制度を設計する業務に携わっていました。
藤澤
大手企業がクライアントだったそうですね。
権藤さん
はい。クライアントは従業員数が数万人から多い場合は20万人に及ぶ、大規模なコングロマリット企業でした。まるで1つの街のような規模感です。
たとえば、不動産営業をしている方が、実は社内の別部門で、研修会社の講師の仕事と非常に相性が良い、というようなケースもあります。そういった適材適所の配置を可能にするため、社員一人ひとりの強みやスキルを可視化し、それをもとに最適な人材配置を行えるシステムを構築しました。
藤澤
なるほど。システム面での支援が中心だったわけですね。
権藤さん
そうです。単なる制度設計だけでなく、その制度を支える仕組みをITで実装すること、そして運用を定着させるための支援までを担当していました。このような業務を通じて、「人と組織の可能性を最大化する」ための基盤づくりを行っていました。
「具体化と抽象化で課題を解きほぐす」──コンサルファームで得たスキル
藤澤
コンサルファームに入社してから得られたスキルについて教えてください。
権藤さん
コンサルファームに入る前、私は2社のベンチャー企業で働いていました。そこではとにかく行動力が求められ、「やれることはどんどんやる」という姿勢が基本で。今でもその傾向はありますが、コンサルでは「もっとショートカットできる部分がある」「事前設計でもっと上手くいく」という考え方を学びました。構造的に物事を組み立てることで、より効率的に成果を出せるようになったのです。
藤澤
具体的にはどのようなスキルでしょうか?
権藤さん
戦略構築力や課題解決力といった抽象的な言葉で表されるスキルです。私の価値観として重要なのは「具体化」と「抽象化」です。自分が持っている課題や問いに対して、まずは具体的にどうすれば解決できるかを考え、そこから成功の条件や本質を抽象化していきます。このプロセスを繰り返すことで、個人の課題解決だけでなく、チームに細分化して渡すことや、お客様への提案にも応用できます。
藤澤
大手企業のお客様とのやり取りにも役立ったのですね。
権藤さん
そうですね。大手企業では全員と合意形成を取りながら進めるのが難しい場合もあります。その時に役立つのが具体化・抽象化です。「今、この人たちは何を見ているのか?」を把握し、認識を共通化した上で、「こういう方向で進めましょう」とメッセージを出し、合意を得る。この積み重ねで課題解決・推進のイロハを自然とOJTで学ぶことができました。
藤澤
本で学べることとの違いはありますか?
権藤さん
課題解決の方法は本にもたくさん書かれています。頭では分かったような気になれる本も多いですが、やはり実務の現場で、実際のプロジェクトを通じて体得した経験は何物にも代えがたい。これは私にとって非常に大きな財産です。
「底辺社員」からの逆転──転職後の試練と順応
藤澤
デロイトに転職された後、順応はスムーズにいきましたか?
権藤さん
いや、全くです。正直、解雇寸前でした。仕事の出来が悪くて、「権藤、大丈夫?」と頻繁に呼び出される日々でした。最初の1年間は、マネージャーやディレクターと一緒にお客様の打ち合わせに参加して議事録を取っていたのですが、内容が全く理解できず、提出した議事録はすべて訂正されました。
藤澤
当時はかなり厳しかったのですね。
権藤さん
ええ。議事録を全部赤字で直されて、「分かっていない」と詰められる。正直に「はい、分かっていません」と答えるしかありませんでした。「なぜ分かっていないままにしていたのですか?」とさらに追及される始末です。
藤澤
プレゼンの場でも苦労があったとか。
権藤さん
お客様向けのプレゼンで、1ページだけ話を振られたことがあったのですが、話が長くなってしまい、お客様が寝てしまいました(笑)。
藤澤
そのような状態はどのくらい続いたのですか?
権藤さん
およそ1年ですね。その間、コンサルタントとして独り立ちしている感覚は全くありませんでした。正直、デロイトにはクビはないと思いますが、「別のポジションにした方がいいのでは?」とか「コンサル職は向いていないのでは?」という議論はありました。
藤澤
かなり厳しい評価だったのですね。
権藤さん
はい。当時は“底辺社員”と自分で呼んでいました。評価は最低ランクの1つ上、Cランク。退職勧告はDランクですが、その一歩手前で、年収も少し下がるような状態でした。そこからどうにかして逆転できたのは、本当に大きな転機でした。
評価が逆転した瞬間──権藤さんのターニングポイントとは
藤澤
評価が大きく逆転したきっかけは何だったのでしょうか?
権藤さん
当時、「権藤はまずい」という状況で、役員との面談がありました。その時に言われたのが、「君、ちょっとプライド高くない?」という一言です。コンサルティングファームやエンタープライズのお客様に対して成果を出すという点で、歯車が噛み合っていなかった。謙虚さが足りなかったのです。
藤澤
それはご自身でも納得されたのでしょうか?
権藤さん
はい。謙虚になれていなかったという指摘は腑に落ちましたし、「皆から学び取る姿勢を持ちなさい」という言葉は、今でも財産になっています。
藤澤
そこから何を始めたのですか?
権藤さん
まず、上手くいっている人はどんな共通パターンがあるのかを徹底的に研究しました。お客様とのコミュニケーションのポイントや、仕事で価値を出せている人の一挙手一投足まで観察し、真似をしました。そして先輩に「なぜあの場面でその発言をしたのですか?」と必ず理由を聞き、全部吸収するようにしました。
藤澤
吸収と改善の繰り返しだったのですね。
権藤さん
そうです。半期ごとに目標と行動を設定し、実際どうだったかを振り返る。上司からも評価をもらい、改善を重ねていきました。そのPDCAを回し続けて、ようやく1年かけてS評価をいただけたのです。
藤澤
S評価というのは、具体的にはどのような評価なのでしょうか?
権藤さん
社内でも1%しかいない、最高評価です。ざっくり言えば、実際に2つ上のランクの職種や役割を担っている、という評価でした。あの時の変化は、自分のキャリアにおける大きなターニングポイントでしたね。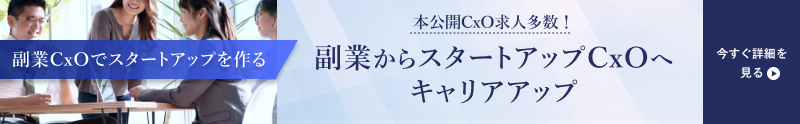
S評価を得るための秘訣──「強みの生かし方」と習慣化の工夫
藤澤
S評価を得るために意識していたことや、コンサルティングファームでの経験が浅い方に向けて何かアドバイスはありますか?
権藤さん
当時は、自分の強みである行動力を最大限に生かしました。もう少し広義に言うと、全体的なPM(プロジェクトマネジメント)力が自分の強みだったと思います。それをお客様への価値提供にしっかり転換できたことが、評価につながった大きなポイントだと感じています。
藤澤
具体的にはどのような取り組みをされていたのですか?
権藤さん
コンサルのプロジェクト内では、As-Is(現状)とTo-Be(理想)のギャップを埋める作業があります。これは自己研鑽の中で磨いておくべきスキルです。デロイトの良かった点は、この仕組みが整っていたこと。
個人に関しても「Check In」という制度があって、メンターや上司と定期的に1on1を行い、PowerPointやExcel分析などの具体的なスキルレベルを指標として評価・フィードバックしてもらえたので、このおかげでPDCAを回す環境が自然に整っていました。
藤澤
習慣化できる環境があったのですね。
権藤さん
そうです。自分を客観的に研鑽し続けるためには、定点的に振り返る仕組みや行動の習慣化が大事です。それと、私が習慣化で特に意識していたのは「よく寝ること」ですね。
藤澤
意外な答えですね。
権藤さん
コンサルの仕事は、長時間働くのが当たり前になりがちですが、それでは非効率になります。頭を休ませて俯瞰する時間を確保しないと、自分の状況もお客様の状況も正しく見られません。第3者として価値を提供するには、視点を引いて見ることが必要で、そのために睡眠は欠かせません。
藤澤
仕事以外の時間の使い方も工夫していたのでしょうか?
権藤さん
はい。Googleで有名な「20%ルール」のように、普段の業務とは異なることに時間を使うことも意識していました。新しい経験や知見に触れること、そして休むことも大切な要素です。寝ることもその一部ですが、それが結果的にパフォーマンスを上げる土台になると思っています。