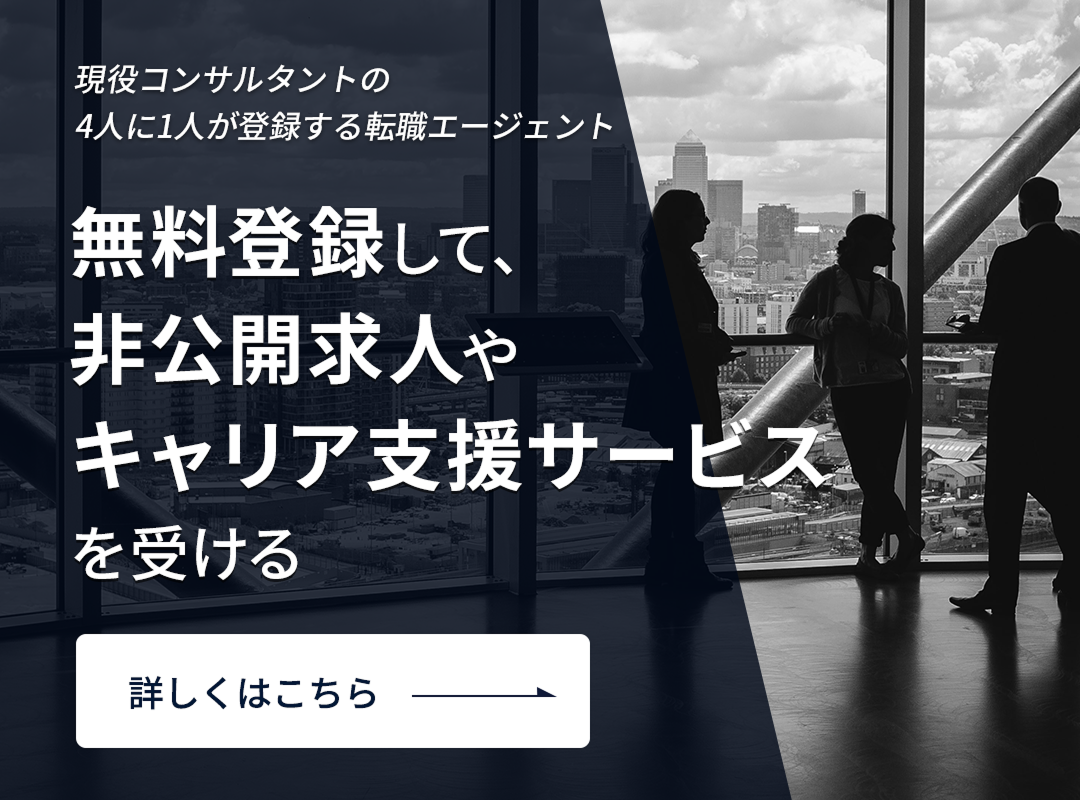【元ITコンサル起業家】宮田和也氏が語る「キャリアをつなぐ力」──TCS・キャップジェミニから起業に至る“4つの経験”
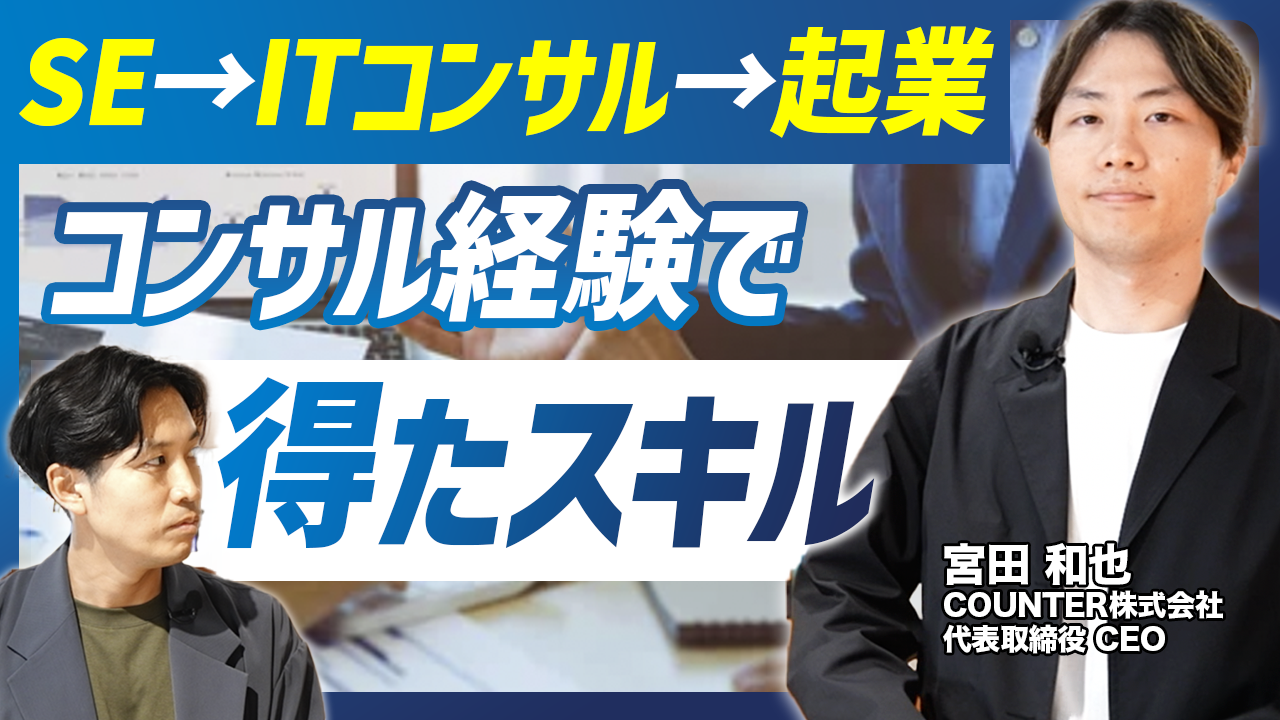
元コンサルタントとしてキャリアを歩み、現在はCOUNTER株式会社の代表を務める宮田和也さん。TCSやキャップジェミニで培ったエンジニアリングとITコンサルの経験を経て、SEO領域で革新的なプロダクトを日本に初導入し、名を広めました。
そこからデジタルマーケティングとUXデザインを掛け合わせた独自のソリューションを提供する事業を展開し、成長を続けています。
本記事では、教育への関心から始まったキャリアの原点、起業に至るまでのステップ、そしてコンサル出身人材を惹きつける理由まで、宮田さんのリアルなキャリアストーリーをお届けします。ゲスト:宮田 和也(COUNTER株式会社 代表取締役 CEO)
青山学院大学経済学部卒業後に外資系ITコンサルティングファーム2社にてエンジニア・ITコンサルタントとして複数のERPシステム導入・運用プロジェクトを経験。
その後、株式会社CINCにてWebマーケティングアナリスト、株式会社バンケッツにてメディア事業責任者を経験し独立。提案・プロジェクトマネジメントスキルを活かし、ニュートラルワークスで執行役員、SEOコンサルティング部門責任者を経験。
2024年1月、COUNTER株式会社を創業。事業貢献するSEOコンサルティングを得意とする。
モデレーター :藤澤専之介
RPA業務を自動化するテクノロジーの会社を2018年に立ち上げ、2022年にクラウドワークスにM&Aでイグジット。その後、子会社の社長やスタートアップの支援などを行い、現在はM&A支援に従事。

Index
教育志望からIT・コンサルを経て起業へ
藤澤
まずは自己紹介と経歴について教えてください。
宮田さん
株式会社の代表を務めております、宮田と申します。弊社はSEOを起点としたデジタルマーケティング支援とUXデザインのソリューションを提供している企業です。私は青山学院大学経済学部を卒業後、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社(TCS)に入社し、その後キャップジェミニ株式会社へ第二新卒として転職しました。キャップジェミニではERP、特にSAPの導入コンサルタントとして経験を積み、そこからWeb業界へ進出し、新たに創業することになりました。
藤澤
学生時代からコンサルティングファームを志望されていたのでしょうか?
宮田さん
研究では統計や計量経済学を学んでいましたが、大学時代はNPOでインターンをしており、教育分野に強い関心がありました。特に教育に関わるソーシャルベンチャーでの経験が印象的で、最初は教育業界でのキャリアを考えていました。
上流志向とデジタルへの関心──TCSからキャップジェミニへ転職した背景とその葛藤
藤澤
TCS(日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ)での業務内容について教えていただけますでしょうか。
宮田さん
TCSでは、SAPのミドルウェアと呼ばれるインフラ領域に携わっていました。具体的には、システムインフラの構築を担当するエンジニアや運用エンジニアとして、約1年半の経験を積みました。
藤澤
その後、キャップジェミニに転職されたとのことですが、その背景はどのようなものだったのでしょうか?
宮田さん
私は「専門性を生かして社会に貢献したい」という思いが強くありました。TCSでの経験はテクニカルな色が濃かったのですが、徐々に「もっと上流の領域に関わりたい」と考えるようになったのです。
単にシステムを構築・運用するだけでなく、アプリケーションの要件定義や業務フロー設計など、ビジネスに直結する領域に挑戦したい気持ちが強まり、アプリケーションコンサルタントとしてキャップジェミニに転職しました。
藤澤
SAPコンサルタントとしての業務は、理想とされていたものと一致していましたか?
宮田さん
正直に言えば、若干のギャップがありました。ITコンサルタントの仕事は、業務の一部をプログラムやシステムに落とし込むことが中心です。私がやりたかったのは、さらに上流の戦略的な領域。振り返ると、当時の私はまだその辺りの理解が浅く、期待とのズレを感じていました。
藤澤
では、より上流の戦略コンサルに近い仕事を求めていたのでしょうか?
宮田さん
そうですね。ITのテクニカルなバックグラウンドを生かしつつ、「IT戦略」というさらに広い視点を持ちたいと思うようになりました。そして次第に、「もっとデジタル領域にフォーカスし、そこから新しい価値を生み出したい」という方向へと考えがシフトしていきました。
段階的なキャリアステップを経て──責任ある役割の積み重ねが導いた独立と起業
藤澤
前職の経験が現在の起業には、どのようにつながったのでしょうか?
宮田さん
私がTCSやキャップジェミニで経験していたのは、基本的にエンジニアやITコンサルタントとしての業務でした。具体的にはシステムの要件定義を行ったり、設計書を扱ったりしながらプログラムを組むという仕事です。プログラムを書いていると自然と論理的思考力が鍛えられ、ミーティングでのアジェンダ整理や、プロジェクト進行などのスキルも身に付きました。その点は社会人として頭一つ抜けた強みになったと感じています。
藤澤
そこから起業に至るまでの流れについても聞かせていただけますか。
宮田さん
エンジニアとしてキャリアを積んではいましたが、いきなりデジタルの上流工程に携わるのは難しいと感じました。そこでまずはSEOに強いデジタルマーケティング企業に入り、アナリストとして修行する期間を持ちました。
その後、友人が運営するオウンドメディアやポータルサイトの事業を手掛ける会社で、事業責任者を務めて。そこからフリーランスを経験し、さらに広告代理店で責任者や執行役員を任され、こうした1・2・3のステップを経て、最終的に起業に至りました。
藤澤
かなり段階を踏まれた印象ですが、入念な準備をして起業されたのでしょうか? それとも流れの中で自然と起業に至ったのでしょうか?
宮田さん
実はもともと「自分の事業を持ちたい」という強い気持ちがあったわけではありません。どちらかというと一生懸命に仕事へ打ち込むタイプで、責任あるポジションを任されれば全力で取り組む。その延長でキャリアが進んでいった感覚です。
たとえば、先ほどのメディア事業で責任者を務めた後、フリーランスになりました。すると広告代理店から執行役員就任のオファーをいただいて。そこでは業界内で名を知られるサービスを立ち上げ、発信を通じて大きく成長することができました。
ただ、役員としてさらに上を目指すのか、それとも株式を100%保有して自分の会社を作るのかという二者択一を迫られたのです。その時に「自分でやった方が良い」という結論に至り、独立して法人を設立しました。
名前が広がるきっかけとなったプロダクト
藤澤
宮田さんの名前が広く知られるようになったきっかけとなるプロダクトについて教えていただけますか?
宮田さん
検索エンジンマーケティングの中で「SEO」という領域があります。今では生成AIを活用した新しいSEOの形も登場していますが、当時は既存SEOの「内部対策・外部対策・コンテンツ対策」の3つが中心でした。
その中で、私はGoogleが推奨する形でリンクを獲得できるサービスを、日本で初めて導入しました。このプロダクトが爆発的にヒットしたことで、当時所属していた会社にも大きな実績が生まれ、私自身もリードの一人として認知されるようになりました。
日本初のリンク獲得サービスから進化──SEO×広報・SNS・UXで展開するデジタルマーケ企業へ
藤澤
現在の会社の形態や事業内容についても教えていただけますでしょうか。
宮田さん
検索エンジンをAIで成長させる流れがある一方で、私たちは広報・PR・SNSといったSEO以外の領域を強化することでSEOを伸ばす手法を確立しました。さらにUXデザインも組み合わせることで、「SEO ×(広報・SNS・UXデザイン)」という他社にはないソリューションを生み出しています。
結果として、単なるSEO会社ではなく、SEOを起点に多角的なデジタルマーケティングのサービスを提供できる体制を構築することができました。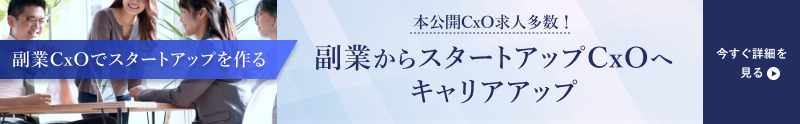
コンサル出身人材が集まる理由と活躍の場
藤澤
御社では、コンサル出身の方を積極的に採用・活用されていると伺いました。具体的にはどのような形で参画されているのでしょうか?
宮田さん
実際によくあるのが「今コンサルをやっているのですが、副業として関われませんか?」「コンサルを辞めてフリーランスになりたいのですが」といったご相談です。ただ、デジタルマーケティングの領域に参入した場合、最初は年収が下がりやすい傾向にあります。その中で条件が合えば、ご参画いただく形を取っています。
藤澤
どのような経路でコンサル出身者とつながることが多いのでしょうか?
宮田さん
弊社の場合はSNSが大きな入り口になっています。それから、埼玉県の越谷市で起業しているのですが、たまたま埼玉県の優秀な高校出身の方とつながり、コンサル出身者をご紹介いただき、実際にご入社いただいたケースもあります。
藤澤
優秀なコンサル人材が御社に集まってくる理由はどこにあるのでしょうか?
宮田さん
戦略コンサルの方が直接弊社に来るケースは多くありませんが、総合系コンサル出身の方々で「デジタルの領域に挑戦したい」「フリーランスとして活動したい」と考える方は多いです。
私自身、コンサルの方々の思考や特性を理解していますので、そのフィット感が大きいと思います。コンサル出身の方は論理的で保守的な傾向がありますが、一方で「感情タイプの人と働きたい」という希望を持つことも多い。弊社の環境はそうしたニーズに合いやすく、結果として「働きやすい」と感じていただけるのだと思います。